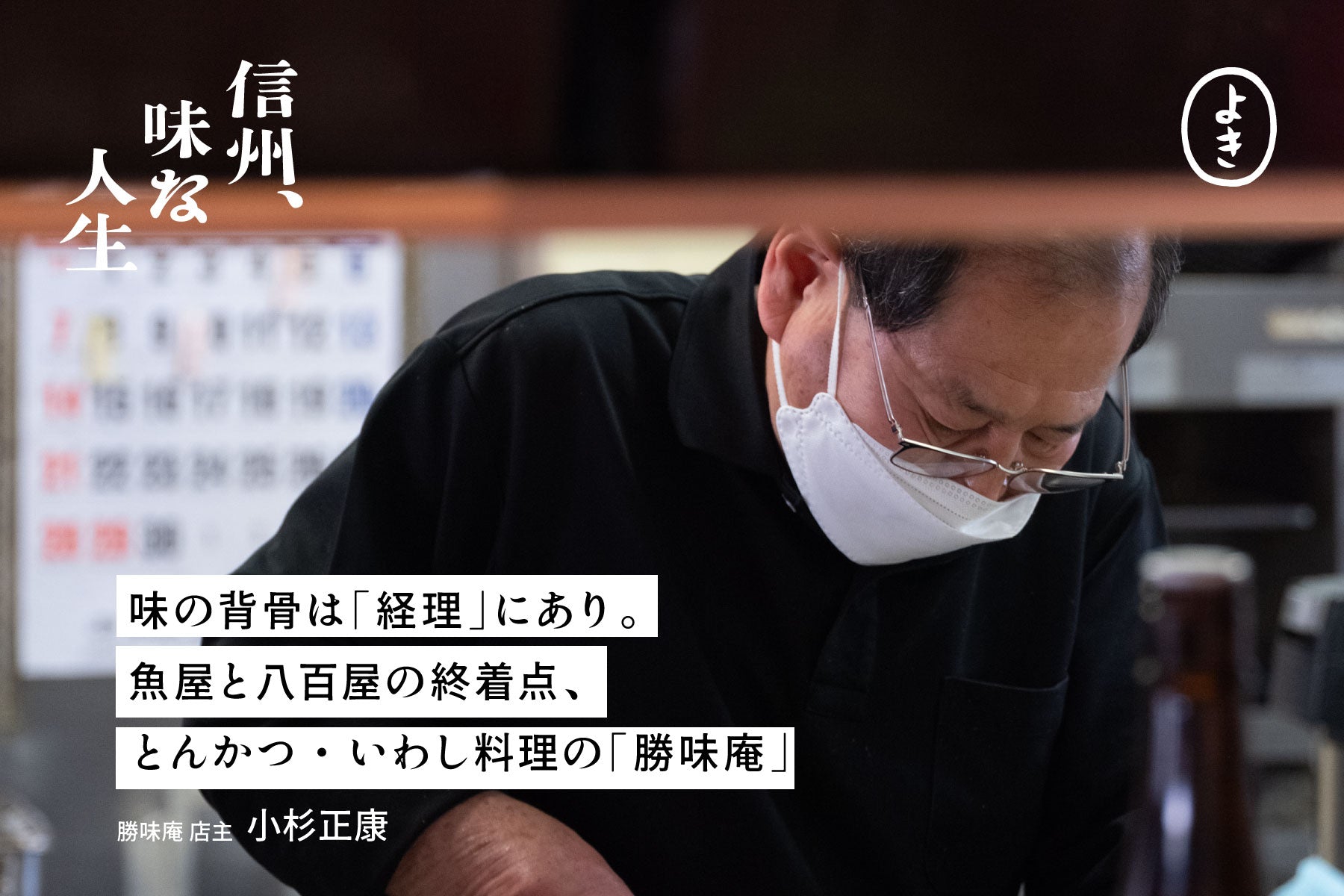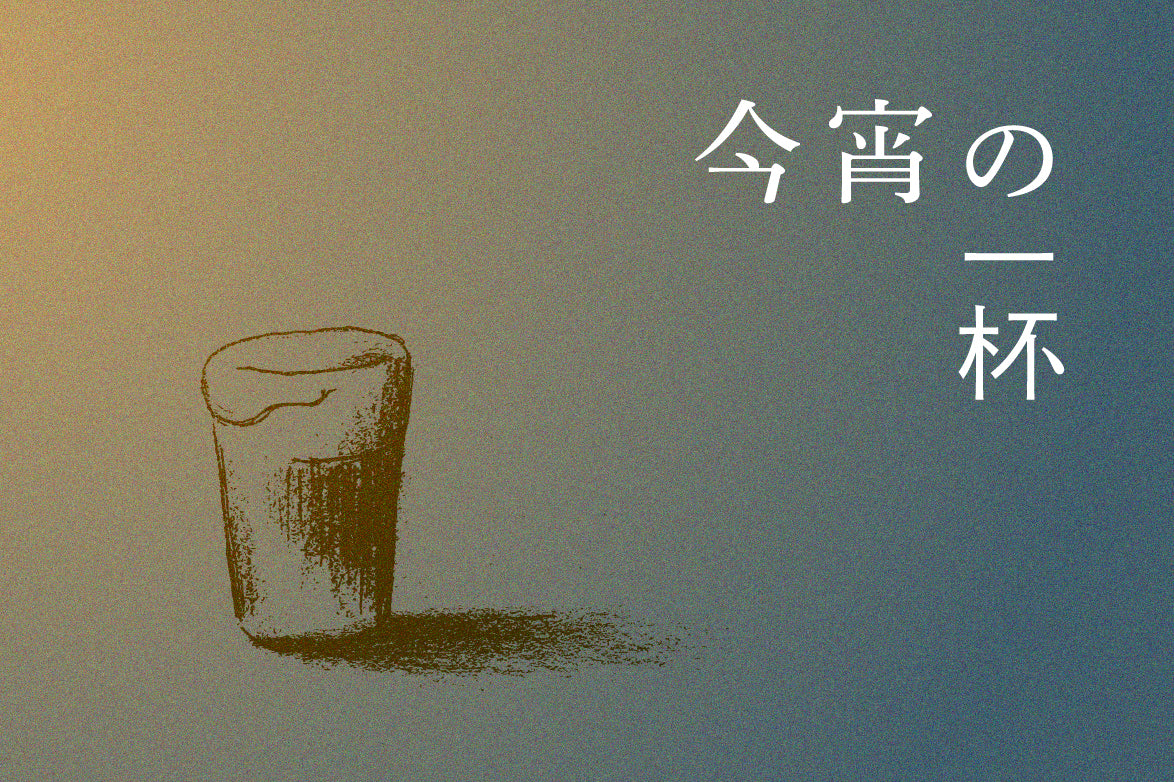取材の約束は昼下がりの14時だった。14時だというのに店内はほとんど満席で、たくさんの人で賑わっている。そんな中、「いらっしゃい!」と満面の笑顔で言って迎えてくれたのは、店主の吉田智子(ともこ)さんだ。

用意してくれていたカウンターの席に荷物を置いて名刺を取り出していると、吉田さんは「ごめんねえ、私、名刺はないんだけど!」と代わりにショップカードを渡してくれた。そのカードには、店名に添えて、「いきで、いなせで、がらっぱちで」の文字が。

けれども僕は、「がらっぱち」の意味がよくわからなかった。仕事に取り掛かろうとする吉田さんに恐る恐る「がらっぱちってなんですか?」と聞くと、「言わない? がらっぱちって。いまの人たちは言わないのかな。うーん、方言じゃないわよね?」とどうやら悩んでいるご様子。
そのやりとりを見かねてか、蕎麦湯を飲みながらくつろいでいた周囲のお客さんたちが、口々に助け舟を出し始めた。
「今の言葉で言うと、ヤンキーみたいな?」「上品じゃない、って感じよ」「ワイルド!」「自然体、でもいいんじゃない?」

好き好きに語られる言葉を背中で受けながら、テキパキと手を動かしていた店主・吉田さんは「まあ、そういうことよ。いとこが考えてくれたんだけどね。がらっぱちに見えたんじゃない、私のことが!」とカラッと笑う。まさに自然体でワイルド、どこか格好良さのある佇まいだ。
さて、今回僕たちが訪れたのは、東御市にある「そば茶屋 さくら」。「がらっぱち」な店主・吉田さんが15年ほど前に、居酒屋だった建物を借り上げ、開いたお店だ。その蕎麦の確かな腕前や、吉田さんをはじめとするスタッフの方々が紡ぎ出す心地良い雰囲気を求め、いまでは県外からもお客さんが訪れる。


陽の光が落ちる、穏やかな店内。「何を食べようかな……」とメニューを眺めながら、更科そばと粗そばの逢わせ盛りを注文した。
取材に同行していたわざわざの平田は、この店10年来の常連だ。「私はさらしなの粗そばで」と平田が注文すると、「平田さんはきのこじゃなかった?」と吉田さんが欠かさず問いかける。がらっぱちでも、よく好みを覚えてくれている。そんなギャップにやられてファンになってしまう人も多いだろうな、と簡単に想像できてしまう。
注文をとった吉田さんは、厨房の奥へと引っ込んでいく。そっと中を伺ってみると、何人もの女性が素早く、でも誰にも何にもぶつからずに動き回っていた。
そこに漂う熟練した空気から、このお店に流れてきた時間の長さを感じる。



カウンターに戻り、店内を見回しながらゆっくりしていると、店内に置かれたさまざまな道具やアートに目が行った。
相撲の絵のついたお茶碗、静謐で美しい絵画、ついさっき近所の人から持ち込まれたばかりの、袋に入ったたくさんの野菜や果物……。何も聞かなくとも、随所から吉田さんのこだわりがひしひしと伝わってきた。



そうしてしばらくしたあとに、目の前に蕎麦が運ばれてきた。「はい!話すより先に食べちゃってね。賞味期限は3分だよ!」

箸で上げれば途切れてしまうかと思うほど、細い細い蕎麦。つゆにサッとつけて啜る。久しぶりに食べたそばの香りと、繊細なかみごたえに思わず嬉しくなる。これだけ細いそば、しかもつなぎを使わない十割そばを打つのはそう簡単じゃないはずだ。
「そばを打ちはじめたのって、何年くらい前なんですか?」
「25年くらい前に、そば教室に通ってたのよ。そこで師匠の打った細いさらしなそばを食べたらハマっちゃって。凝り性だったから、そこから毎日のようにそばを打つようになって。当時の旦那と一緒に、この近くで店をはじめてね」。

吉田さんは旦那さんと別れ、そのお店から独立する形で「そば茶屋さくら」を開いたという。それにしても、そばをうちはじめて25年。赤ん坊が成人して仕事に悩みはじめるくらいの長い長い年月だ。なぜそこまでして続けられたのだろうか?
「毎日打ってるとね、違うな、って気づくことがあるんですよ。それが面白くてね。でも、そばだけにハマってたわけじゃないのよ。これまでいろんな仕事をしてきたから」
会社員として働き、結婚したあとも自分の興味関心の赴くままに突き進んできた吉田さん。東京と長野を行き来しながら手芸を学び、上田にテディベアショップを開いたこともあれば、経営者たち御用達の小料理屋で働いて「次の女将にならないか」と言われるまで信頼されたこともあった。やりたいことも居場所も選べた吉田さんが、いま続けているのがそばだった。
「自分でお店をやると、頑張っただけ自分やお店が良くなっていくでしょう。それがいいと思ってね」
そばを食べ終え、前のめりに吉田さんの話を聞くうちに、気づけば店内にはお客さんたちがいなくなっていた。

「せっかくだし、打つところ見ていきますか?」。言われるがままに、お店の奥にある製麺室を見させてもらう。
広いバックヤードの一角に、壁で仕切られた製麺室があった。広さは1.5畳といったところだろうか。吉田さんひとりが入ればもう窮屈になるほどの、小さくて清潔な部屋。開店からの15年、吉田さんはここで毎朝、蕎麦を打ち続けてきたらしい。
「みんな、10月〜11月に収穫されたばかりの『新そば』が美味しいっていうでしょう。でも私は、収穫したあとしばらく経って、そばの実の水分が少し抜けた1月、2月の頃のほうが美味しいそばが打てると思うのよ」
毎日毎日そばを打つから、気づけることがあるという。「毎日食べてると、『これは違うかもしれない』って思うときがある。私が美味しくなかったら、お客さんだって絶対おいしくないじゃない?」
吉田さんの“私”基準のこだわりが、そば打ちを楽しく続ける理由になっているのだ。


戦場のようだった厨房もすっかり静かになっていた。のれんをあげて、3人のスタッフさんが出てくる。
「私たちも、まかないをいただいていいかしら?」そう言うと彼女たちは、カウンターに横並びになってまかないのそばを食べはじめた。

「うちがラーメン屋だったら続かなかった、って言うスタッフもいるのよ。ラーメンだったら毎日は食べられないけど、蕎麦だから毎日出てきても食べられるって」。
そんな話をして笑い合う4人からは、教室でたむろする同級生のような仲の良さが垣間見えた。スタッフの中には、吉田さんがそば教室で出会って以降、店を手伝い続けてくれている方もいるそうだ。

「お店をやめようと思ったことは、無いですか?」
取材の終盤、平田は聞いた。平田にとって、大切な店。やめてほしくないと考えながらも、25年間も同じ営みを続けてきた吉田さんのいまの気持ちを確かめたかったのだろう。
「考えるよ。いまは趣味でロードバイクに乗っていて、辞めたら毎日自転車に乗れるしね」と笑う吉田さん。「そうなったら、平田さん、ここを使って何かやってよね」という言葉に、平田は「そんなこと言わずに、そばをもっと打ってくださいよ!」と涙を浮かべて返す。
「辞めるときのことは話してるけど、みんなからも『この店はともちゃんの思いがあるから、誰かが継ぐって言っても簡単じゃない』って言われててねえ」
周囲からの「やめてほしくない」という希望はよくわかりつつ、「好きなものが多いから、また何かはじめたくなるかもね!」とカラッと笑う。探求したい凝り性ではあるけれど、湿っぽい執着は感じられない。まっすぐに、がらっぱちな勢いで、吉田さんは自分の思うままにこれからも進んでいくのだろう。
お客さんがいても、営業を終えて厨房のメンバーが集まっても、吉田さんは「ともちゃんはさ〜」と愛称で呼びかけられながら、話題の中心にいた。突き進む強さも、周りを気にかける愛嬌も兼ね備えた吉田さんの人柄がそうさせるのだろう。そんな大先輩がいる店に、元気をもらう人も多いはずだ。
現に自分も、はじめて行ったこの日を境に、自分のなかに「吉田さんのような格好よさ」という基準が増えたような気がする。そしてさくらに行けば、そんな吉田さんの姿を拝める。
吉田さんにはきっと、やりたいこともはじめたいこともいくらでも見つかる。それでも、「もう少しだけ長く、蕎麦に興味を持ち続けてもらえたら」と、願わずにはいられなかった。