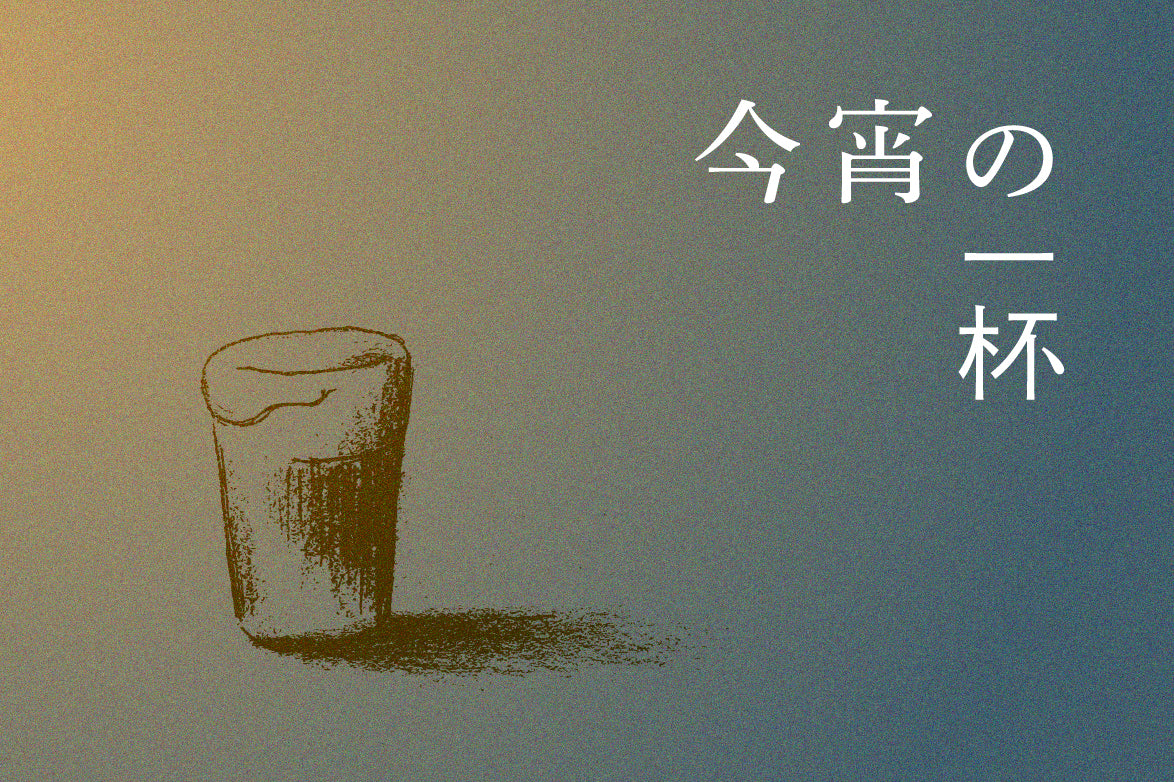耳を傾け、服を作る。石徹白洋品店
- 執筆:わざわざ編集部
- 撮影:若菜紘之
小さくて開けたまち、石徹白。

2月の石徹白の世界

手作りの「古い物資料館」

資料館の様子
私はその言葉に本当に驚いたのです。見ず知らずのよそ者が、人口およそ250人の地域に入ってきたのに、寛容に受け入れてくださって、ありがとうと言ってくださる。その前日に泊まった宿でも大変親切にしていただき、この町の方々は誰でも丁寧に受け入れてくれる。辺境地の村という印象とは程遠い開けた印象を受けたのです。これは衝撃的な出来事でした。今までの取材経験からも、こんな印象を受けた街はなかったのです。

宿での一コマ。平野さんご夫妻の子ども達を実の孫のようにかわいがる様子に心を打たれました

馨生里(かおり)さんと彰秀(あきひで)さん。
石徹白への移住

雪の中の石徹白洋品店
平野さんご夫妻は岐阜県出身で、石徹白へ移住をされています。お二人とも東京の大学を経て東京で就職をされていますが、故郷への思いがあり、岐阜のまちづくり活動の団体の東京支部に入ったことで出会ったそうです。
そして、2007年の夏に石徹白に初めて訪れたことがきっかけで、どんどん石徹白の魅力にのめり込み、移住を決意したそうです。3回冬に来ないとダメだよと言われ実践し、移住をしたのが2011年9月のことです。その間に馨生里さんは岐阜市の洋裁学校で学び、ご夫妻で石徹白へ水力発電を作る取り組みを実行されています。この話も壮大なストーリーがありますが、またいつかの機会に。

やぎも飼ってます
話は、馨生里さんの大学生の頃に遡ります。馨生里さんは大学2年生の頃から、ゼミでフィールドワークとして国際協力についての研究をしていたそうです。国際NGOにボランティアにいくこともありましたが、「施してあげる」という雰囲気に違和感を感じていたと言います。
そんな中で難民支援で草木染をしていた森本喜久男さんの「メコンにまかせ」という本に出会います。桑を植えて蚕を育て布を織り染め、現地の人と一緒に村を作る。アンコールワットから1時間の場所に地雷除去をして村を作ったその様子に感銘を受けたそうです。そして、森本さんに連絡を取り、馨生里さんは毎年1ヶ月ほどそこに滞在し、現地の方々にお話を聞く「聞き書き」をしながら滞在するという体験をしたのです。

石徹白洋品店をオープンした際に、森本さんから贈られた布
そこで「織物を中心とした循環型の社会を見た」と馨生里さんは言います。そして、これを石徹白でやってみたい!と思ったのです。
もともと、アトピーで肌が弱く市販の服が着られなかったこと、服が大好きで、服は自分をアイデンティファイするものなのに、遠い国でどんな人がどんな状況で作っているのかよくわからないものを着ているのが嫌だったということ、大学時代から望んでいた循環型の社会、3つが繋がり石徹白洋品店は2012年5月にオープンすることになりました。最初はオーガニックコットンとヘンプで作った服、がらぼうのふきん、布ナプキンなどを並べてスタートしたのです。
たつけの誕生
その後も師匠である森本さんとは連絡を取り合っており、石徹白に遊びに来てくださる日がきました。森本さんと一緒に先の資料館に行くと、一つの服が展示されていることに気がつきました。「たつけ」でした。

手織りの藍染で作られた不思議な形のズボン。いつから着られていたかはわかりませんでしたが、農作業の時にはかなり重宝されて着られていたことがわかりました。森本さんは「これを絶対に作った方がいい」と言いました。
「たつけ」は直線断ちの洋服です。アパレル産業には廃棄問題がありますが、実は端材の廃棄が多いのです。ですが、たつけは直線断ちで作るので、ゴミが出ません。布を余すことなく作ることができます。
これこそ日本人が着るべき服なのでは?と馨生里さんは言います。
こんなものを日本人が作ってきたんだという驚きと発見。かしこい日本人が、自然の成長量の中で慎ましく生きてきた。布が貴重だった世界で、自然の中での相応の生活。「たつけ」を見てそんな気持ちが湧いてきたそうです。
そして、大学時代の「聞き書き」が繋がってきました。作り方はどこにも載っていませんが、確かにここにいる人たちの心の中にはあります。作り方を聞き書きして教えてもらった寸法や作り方を真似して作りますが、現代人の体型には合いません。四苦八苦しながらオリジナルの「たつけ」を生み出し、サイズ展開をさせていったのです。


石徹白の人々の話の聞き書きはライフワークとして続けており、地元の仲間と本を自費出版している
そして、イベント出店などを重ねていくとちょっとずつお客様が店舗にやってくるようになりました。石徹白に移住者も増えていったのです。人気が出てくると生産が追いつかなくなり、当初は馨生里さんだけで作っていた服を、地域の方たちが作るのを手伝ってくれるようになりました。そして更に受注量が増え、現在は縫製所に依頼して制作をしています。
その後は、四人の子供の出産や育児と並行して、事業を少しずつ拡げていきました。2016年には新しく店舗を作ります。どんどん環境も変化して2017年に一人目のスタッフを雇うために法人化をされました。
10年経つと実現する世界

石徹白にきた時に、ご夫婦でこれから10年の間にしたいことを紙に書き留めていったそうです。二人で石徹白でどのように暮らしていきたいのか?を話し合い、どんなことをやりたいのか書き留めていく。
- 服を作る
- 藍染をする
- 羊を飼う
…などと思いつくことを並べていったそうです。
驚くことにその願いは、7、8年の間に全て実現できたということです。書くと実現する。その言葉にハッとさせられました。お二人は未来をきちんと見据えて今を生きている。大学時代から今へ繋がっていくのは、どんな風に生きたいか?がある程度ビジョンとして明確になっているからなのでは?と感じたのです。

これから10年でどんな未来を想像していますか?と質問をすると、馬を飼う、宿を作る、子ども達が石徹白で働けるような選択肢を作りたいと、スラスラと答えてくださいました。どのような人生の航海をするのかは、その指針次第。ビジョンがあるとまっすぐにそこに向かうことができるのかもしれません。

そして、もう一つ、感銘を受けた話があります。それは「聞き書きがある地域とない地域では未来が変わってくる」というお話です。おじいさんやおばあさんに、1対1で聞くとその人を好きになる。そうするとその人たちが住んでいた地域が好きになる。花を植えるのが好きだという話をそのまま聞けば、そのままだけど、その人がどのような気持ちで花を植えているのかを知ることができると、私もやってみようと次々と花を植える人が増えるかもしれない。そうすると地域の景色が変わっていく。

敬意をはらっている。教えていただいている。暮らしていると、地元の人を尊敬しているという気持ちが湧いてくる。馨生里さんの言葉です。お二人の人生の中で、石徹白という土地との出会いの必然性を感じざるを得ない、そんな取材の体験をさせていただきました。まさに文化を作るお仕事をされている平野さんご夫妻に尊敬の念が湧いてきます。
ぜひとも、石徹白洋品店の思想を纏ってほしい。そんな風に心から思います。