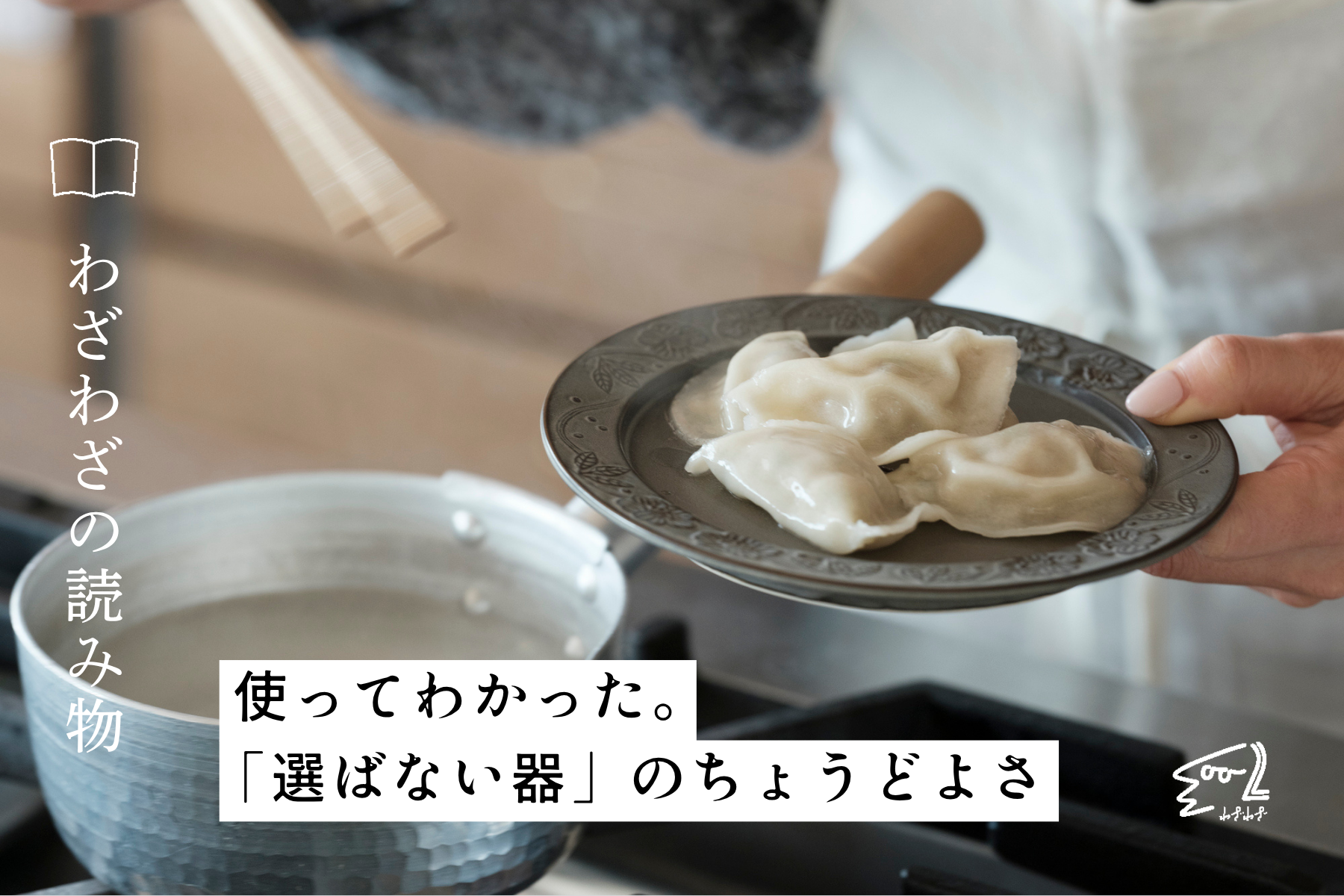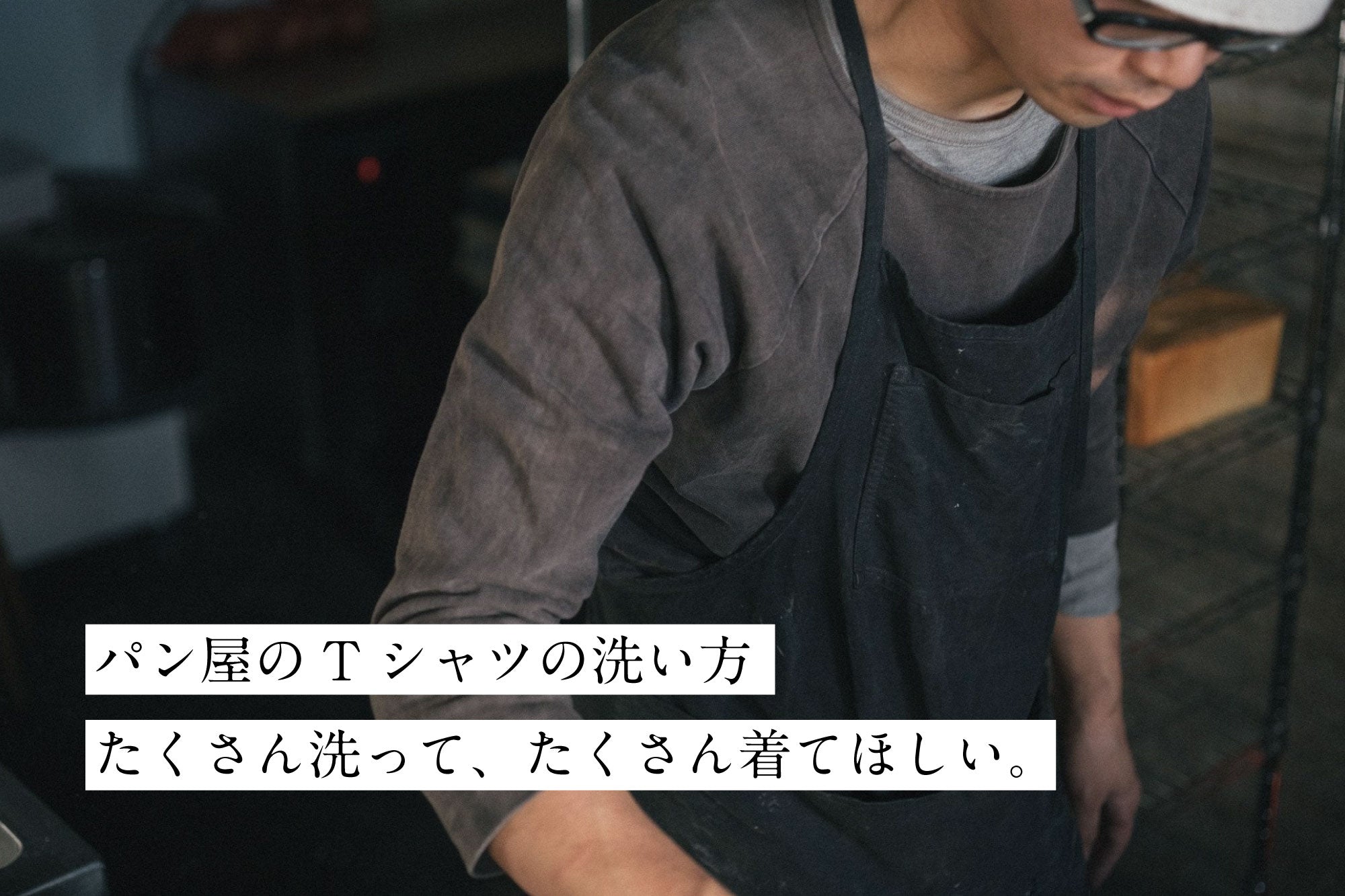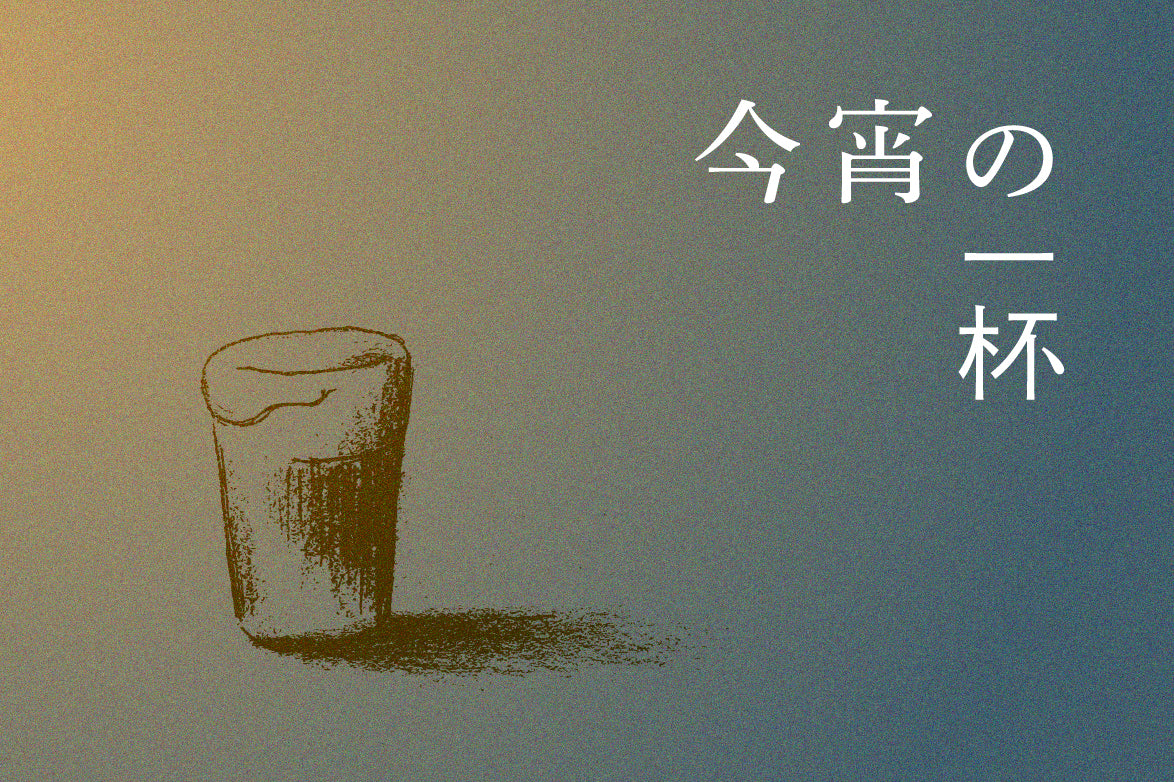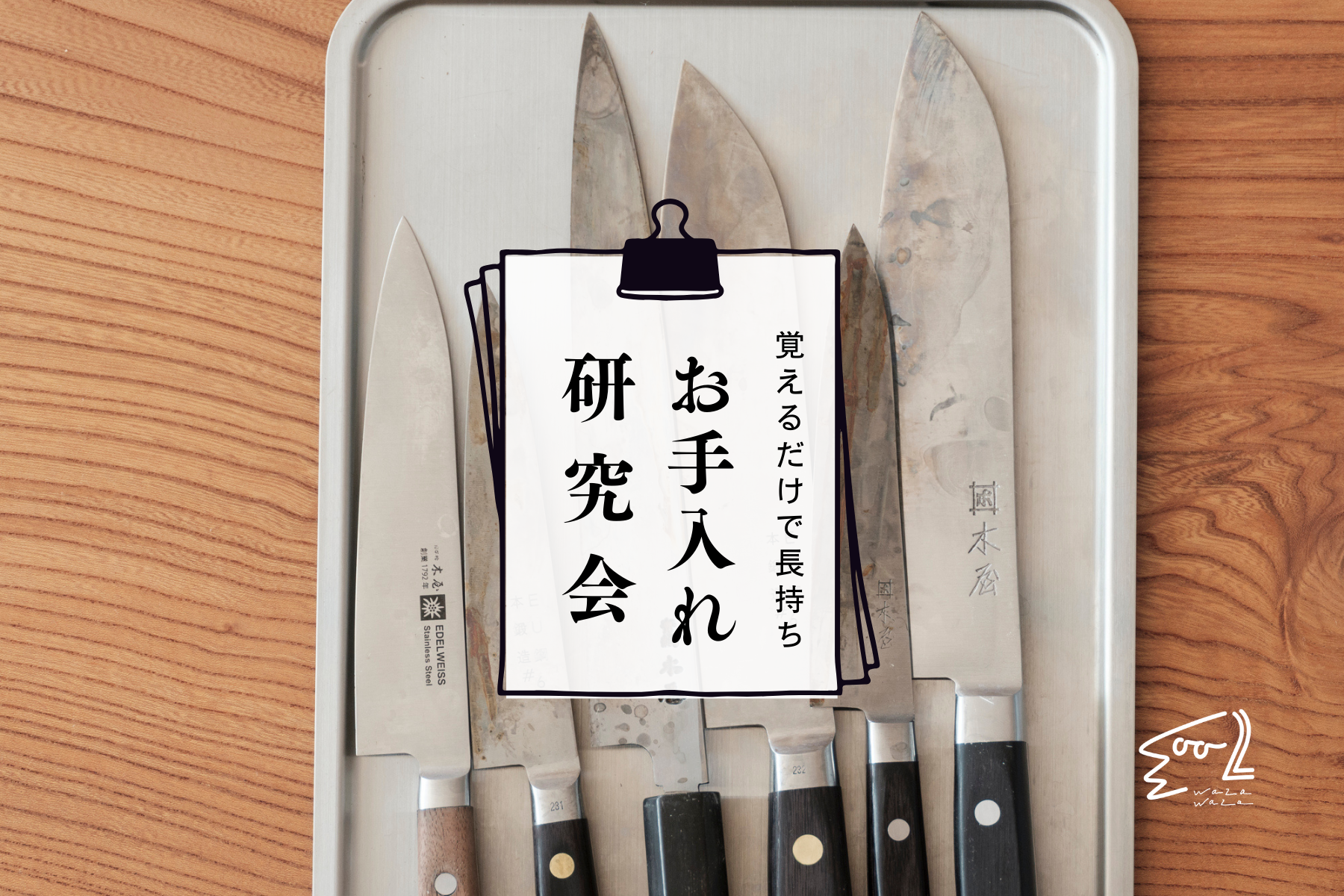
砥ぐ、たしなみ。初心者もできる包丁の砥ぎ方
- 執筆:わざわざ編集部
- 撮影:若菜紘之
料理をする人なら毎日使うであろう、包丁。ちょっと切れ味がイマイチになってきたと感じたとき、どうしていますか?そのまま使い続けている人も多いかもしれませんね。わざわざのスタッフ内でも、包丁砥ぎはやってるけどよくわからない、買ったお店に砥いでもらってる、という話も出てくるほどで、かなりハードルの高いお手入れであることは間違いありません。
「できることなら、自分で砥げるようになれたらいいのだけど……」と感じている皆様。今この記事にたどり着いたのも何かのご縁です。包丁砥ぎをたしなんでみませんか?
今回、初心者でも簡単に砥げる方法をプロに伝授してもらいました。包丁を砥ぐと、切れ味がよくなり、不思議と気持ちも整いました。包丁砥ぎは一生使える技術です。一緒に身につけましょう!
<今回教えてくださったのは>

キング砥石の代表取締役社長、渡辺敏郎さん。キング砥石は焼物で有名な愛知県常滑市で創業80年以上にわたり砥石を作っている老舗メーカーです。渡辺さんは全国各地で包丁砥ぎのワークショップを開催されており、だからこそ初心者の目線に立ったわかりやすいレクチャーをしてくださいました。
包丁を砥ぐ前に、まず包丁の汚れ落とし

今回は、よき生活砥究所にある鋼(はがね)の包丁をお手入れします
まずは砥石を10〜20分ほど水に浸します。この時間を使って包丁のさび取りや柄のケアを進めておきます。このさび取り作業が、さっそく気持ちいいんです!

砥石から泡が出なくなるまでが目安です。

やることは、包丁の刃をさび取りゴムで軽くこするだけ。そこまで力を入れなくても、汚れた水が出てきて、きれいになっているのがわかります。さびが取れにくいところは力を入れて、ゴシゴシとこすりましょう。

取れにくい汚れは、消しゴムのように持ってこすると力が入りやすいです

背中部分も磨きます。この時はさび取りゴムを置いて、包丁を動かします
市販のクレンザーやジフを併用すると汚れが落ちやすく、さび防止にもなります。さびは食材に移りますし、刃で広がりやすいので早めに処理するのが大切です。

柄の部分もそのままこすっていきます。刃砥ぎ教室をしていると、柄がベタベタしている包丁によく出会うそうです。特に木製の柄だと油分などが残りやすいので、この機会にしっかりと汚れを落としてあげます。しっとりさらさらとした握り心地に変わって、不思議と握りやすくなった気がしました!

刃の変色が落ちてピカピカ!まだ砥いでないのに、もう嬉しい!
「切れ味をよくしたいだけなのに、さび取りや柄のケアも一緒にするなんて、やることが増えた…」と一瞬思いましたが、これも包丁を長く使うために大切なことですし、何よりきれいになっていくのが快感でした。砥石を水に浸している間の待ち時間で、サクッと行いましょう。

ここで切れ味チェックのため、紙を切ってみます。新聞紙やチラシ等でも大丈夫です。柄に一番近い「刃元」の部分を紙に当てたら、手前にスッと引き下ろしていきます。引っかかる場所があればそこが切れにくい所。砥ぐ時に参考になるので、ここで確認しておきます。
砥いでみましょう

さあ、いよいよ砥いでみます!
中指から小指で柄を持って、口金に親指を添えて、人差し指で背中を支えてあげると持ちやすいです。人差し指が背中にあると、砥ぐ時の角度をキープしやすくなります。
包丁を砥ぐときは、一気に刃全体を砥ぐのではなく、何か所かに分割して砥いでいきます。1箇所目で10往復したら、次の場所で10往復して……を繰り返していき、全体を砥ぎます。これを表面・裏面とそれぞれで行います。表面は自然に動かして、裏面は押す意識で刃を砥石に当てていきます。

刃を砥石に当てる角度は、表面の時は斜めの長い線、裏面なら横方向の短い線に合わせます(この写真は裏面の角度で当ててます)

刃を起こす角度は20度。10円玉2枚を挟んだ角度とはよく言いますが、それだと少し浅いです。結構寝かせがちで砥いでる人が多いそう

キング砥石のトーグッドシリーズに入っている取扱説明書を指定の箇所で折ると20度を作れます。こういうの、初心者には本当にありがたい…!

渡辺さんは小指をここに挟むとちょうど20度を作れるので目安にしていました。こうやって自分の指で基準を作っておけたら、毎回迷わなくて済みますね。

左指で砥ぎたい部分を押さえると、その真下が砥げます

まずは表面から砥ぎます。砥石全体を使うように、ストロークを長く取りながら前後に10往復しましょう。ガイドの線付近をなぞるように前後に動かすのではなく、砥石の端から端まで目一杯使うイメージで動かします。

白い矢印のように、砥石全体を使って砥いでいきましょう
砥ぐと刃や砥石に黒い粉が出てきます。この泥は砥磨剤になりますので、そのまま流さず使っていきます。
10往復したら、左手の位置をずらして、また10往復。この繰り返しで、4~5回くらいに分けて刃元まで砥いでいきます。

刃元まで砥げたら今度は裏面です。小指で20度の角度を確認したら、押す方に意識をもっていきながら、同じく10往復を繰り返します

左手の位置に注目です。表面は刃のギリギリを押さえたのに対し、裏面の場合は少し上に変わります。

砥いでいる時の音がいい。無になれるというか、癒されるというか…

表面と同様に、10往復できたら刃元方向に左手をずらして10往復。これを刃元まで繰り返します
両面一通り砥ぎ終わったら、刃先を触ってみてください。砥ぎ上がりの目安となる「かえり」というざらつきが出ているはずです。これを指先で感じられたらOKです。

親指の腹で刃先に触れたら、白い矢印の方向になでおろします。刃と平行に動かすと指が切れるので注意
今回の包丁は鋼なので砥ぎやすいのですが、ステンレスの包丁だとかえりが出にくいことがあります。その場合は一段階荒い砥石を使って砥ぐと、かえりが出やすくなりますので試してみてください。
「かえりは素人が触ってもわかるのか…?」という疑問がありましたが、ちゃんとわかりました!ざらざらを感じられたら十分です。ちなみに、ざらざらの程度は気にしなくて大丈夫。包丁砥ぎに慣れてきたら「少しざらついたな」と感じる位で終わらせるのがおすすめです。初心者ならまずは砥ぎすぎることを怖がらずにやってみてください。

かえりが確認できたら、仕上げです。今度は力を抜いて5往復、先程と同じ要領で包丁を分割して砥ぎます。今度は指の位置を変えるたびに水をかけていきます。さっきと同じ動かし方ですが、水が多いので音が優しく変わりました。
一通り砥いだ後に触ってみて、ツルツルしていたらかえりが取れています。ざらざらとした場所はまだ残っているので、追加で砥ぎましょう。

刃先を触ってかえりが無くなったことを確認したら、新聞紙で仕上げをします。包丁を拭いたら、新聞紙を置いて、刃を軽く当てて何回か動かします。細かいかえりを取りきれるのと、新聞紙に含まれているインク等の油分が包丁のさび予防になります。

撫でるように動かすだけで十分です

再び切れ味チェック。刃元を当てて……

スパッ。切れ味復活!!
砥石のお手入れ
最後に、砥石のお手入れまで済ませます。包丁を砥ぐうちに砥石は中央部分を中心にへこんでいきます。そのままへこみを残していると、せっかく砥いでいるのに砥げてない!という事態が発生します。
そこで「面直しやすり」で砥石を平らに戻していきます。

まず、砥石全体に鉛筆で斜線を書きます。そして面直しやすりで砥石を削っていきます。水を出しながら、前後に動かしたり、クルクルと円を描いたりしながら削ります。

へこんでいる場所はいつまでも線が残っているので、それが消えるまで削り続けます。鉛筆の線がすべて消えたら、平らに戻せたことになります。

お手入れしたい茶色の砥石よりも目の荒い灰色の砥石を重ねてこすり合わせる方法もあります。こうすると茶色い砥石だけが削れます
砥石のお手入れも、包丁を砥ぐたびに行うのが理想とのこと。さび取りから始めて色々とやることがありましたが、包丁を砥ぎ終わった今、なんだか心も砥ぎ澄まされていて、このままの勢いで砥石も平らに整えられそうです。

お手入れ完了!ちなみにさび取りゴムでシンクも磨いていました。どこまでもきれいで気持ちいい…!
包丁砥ぎは、日本人のたしなみ

包丁の切れ味が落ちてきたから砥いだ方がいいんじゃないかと気になってくるのは、砥いだ経験にかかわらず、包丁砥ぎが日本の生活文化として実はDNAのように受け継がれているからではないか。そんな話になりました。
包丁が切れないのを我慢して使っている人が多い中、シャープナーを使ったり、お茶碗の裏で砥いでみたりと、簡単にできる方法で対処するのはとても良いことではあるので、せっかくならレベルアップして砥石で砥げるようになりましょう。日本人のたしなみとして、一生モノの技術になります。
ご自宅に眠っている砥石はありませんか?平らにお手入れしてから、ぜひ使ってみてください。
砥石をお持ちでなければ、わざわざでも砥石を取り扱っています。今回の記事中で使っていた、砥ぎの角度のガイドが入ったタイプだと初めてでもやりやすいと思います。砥ぐたしなみ、一緒に始めましょう!