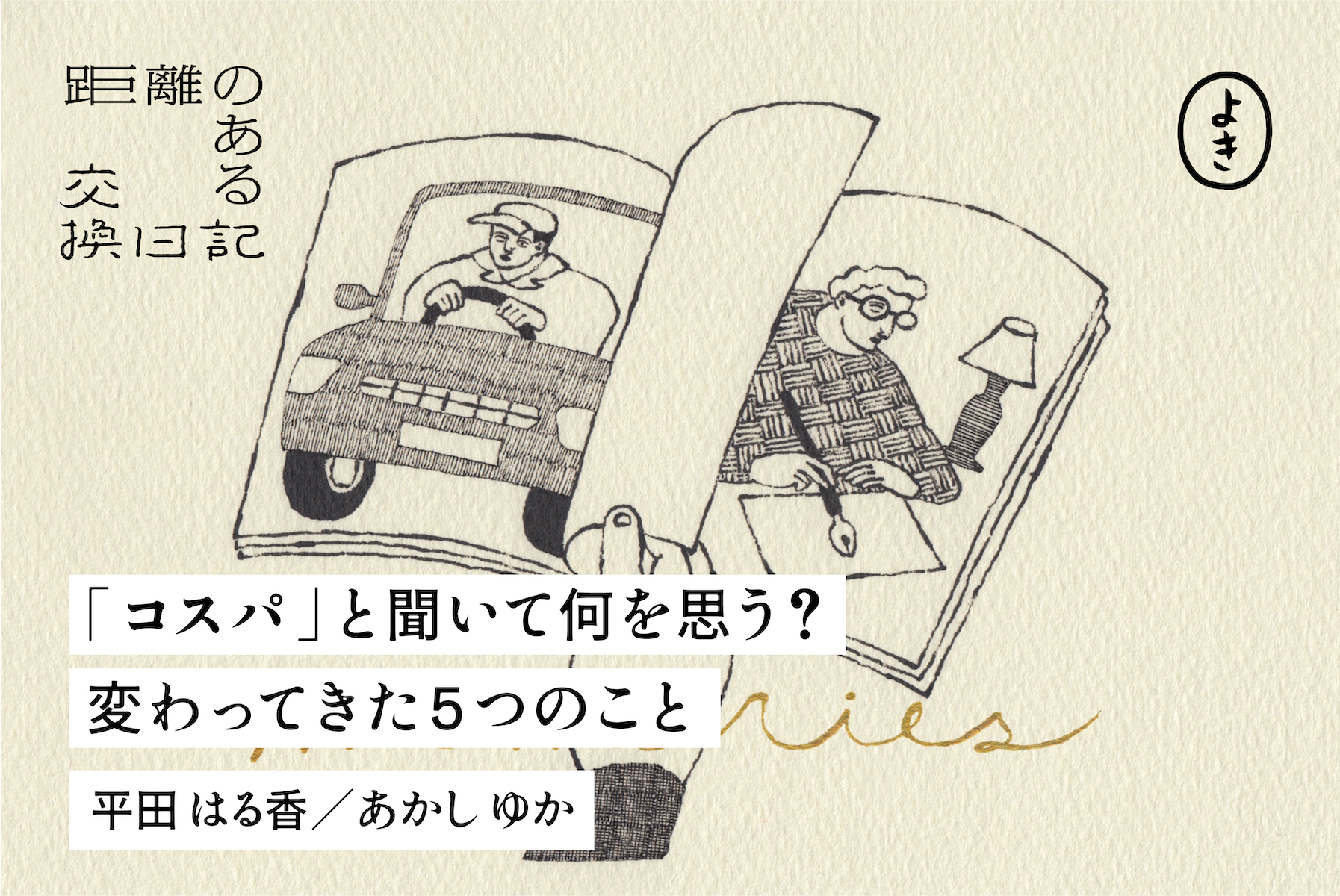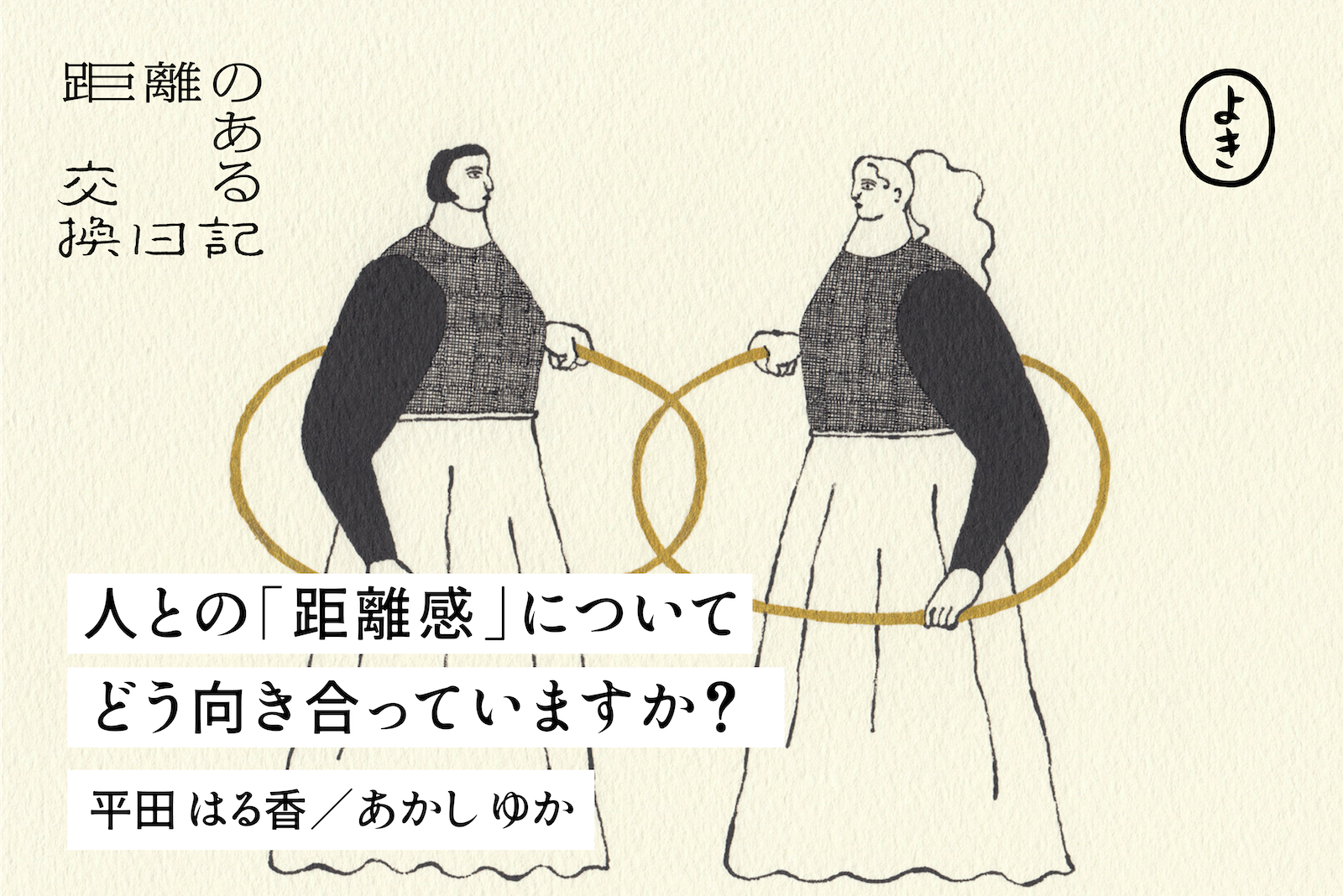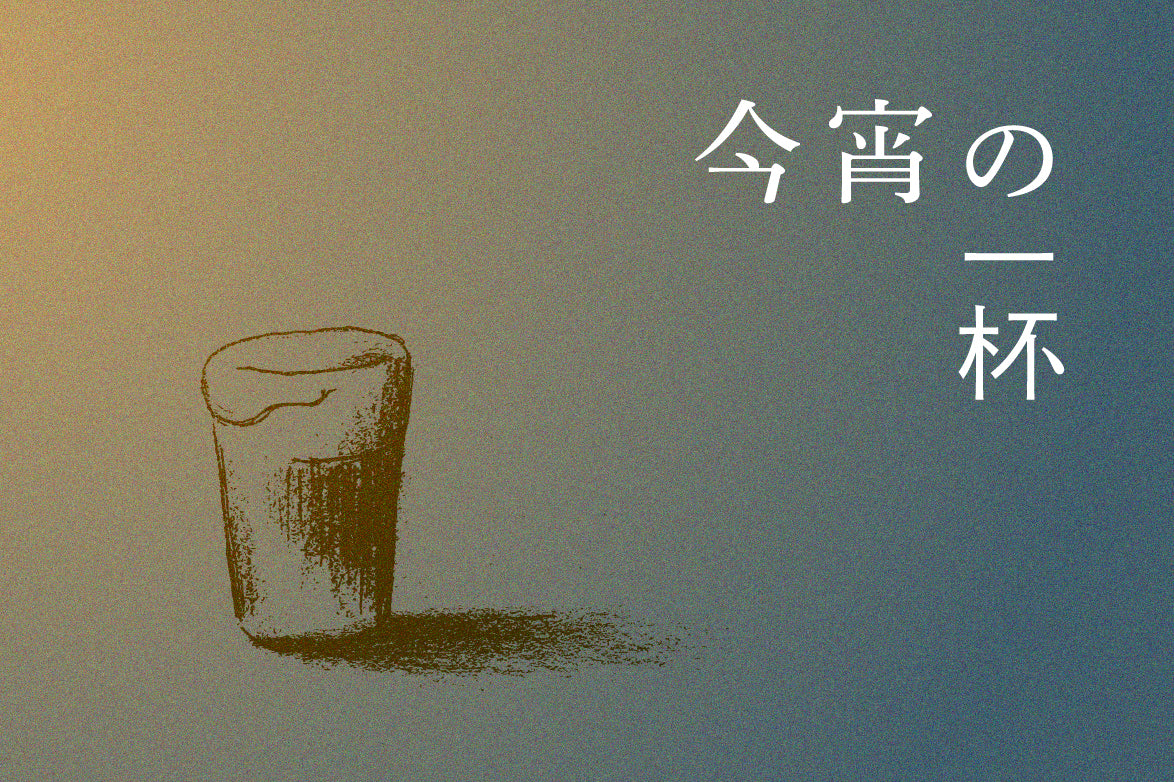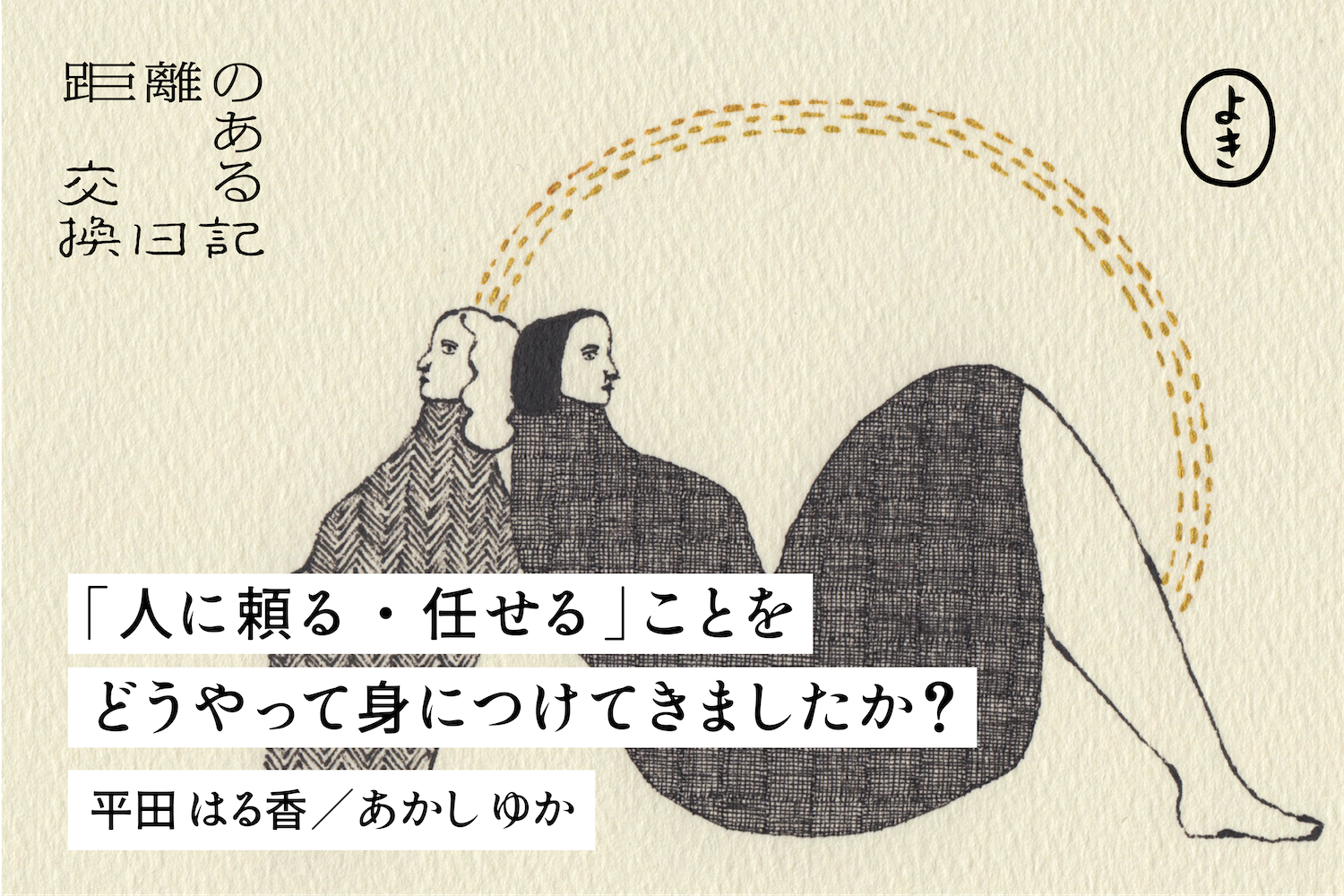
あかし→平田さんへ
平田さん、こんにちは。平田さんの「50歳で勝つ」話、何度聞いても大好きで、そして実際に歳を重ねるごとにどんどん素敵になっていく平田さんを尊敬しています。
平田さんの「50で勝つために気をつけてきたこと」の5つがすばらしかったので、5つの括りで何を書くかすごく悩みました…!笑
私はまだまだ未熟者なので、これから変わっていかねばならぬという自戒も込めて、32歳の時点で「変わったこと」と「変わらないこと(これから変えていきたいこと)」をそれぞれ5つ書いてみます。
<変わったこと>
①他者の目があまり気にならなくなった
わたしは幼い頃、とにかく周囲の目を気にしてしまう性格をしていたのですが、今では他者の目がほとんど気にならなくなりました。私が人の目を気にする性格をしていたのには生まれ育った環境が大きく影響していると考えているのですが、数年前に自身の過去に向き合うタイミングがあり、それを経たあとは他者ではなく自分の感情を大切にできるようになった気がします。
②「この人に分かってもらえたらそれでいいや」と思える友人が増えた
おそらく①にも影響していると思いますが、不特定多数の目線を気にするよりも、本当に自分が大切に思える数少ない友人たちからの目線を気にしていこうと思うようになりました。今では嫌なことを言ってくる人がいても、「私が大切な人にしか私を傷つけることはできない」と思っています。笑
③自分の底力への信頼が出てきた
5年ほど前に「人生どん底だ!」と思うほど落ち込んでいた時期があり、それを乗り越えた(むしろそれが人生の転機になった)ことで、これから先の人生で悩んだり苦しんだりしても「なんだかんだ自分はきっと大丈夫だ、乗り越えられる」という底力に対する自信を得られた気がします。
④コンプレックスがなくなってきた
私が好きな河合隼雄さんの『コンプレックス』という本の中に、こんな一節があります。
「コンプレックスというかぎり、それは感情によって色どられていなければならない。感情のからみつきのない、自分の劣等性の認識は、むしろコンプレックスを克服した姿である」
昔は体も心も自分に劣等性があると思っていた部分がたくさんあって、それが嫌で恥ずかしくって隠すように生きていましたが、自分の特徴を受け入れて付き合えるようになってきたように思います。「足がもっと長かったらよかったのにな〜」などと思う日はありますが、感情のからみつきはもうほとんどなく、「そういうもの」として自分自身を客観的に捉えられるようになった気がします。
⑤物事を続ける力がついた
昔は何かを続けることが苦手だったのですが、選択における失敗と成功を繰り返してきた結果、「選ぶこと」の精度が高まってきたと思います。もちろん続けることだけが正義ではないですが、続けたいと思えるものが側にある幸せを感じながら、それを守るための力をつける努力をしていたいです。
<変わらない(これから変えたい)こと>
①考えすぎる
これは長所でもあり短所でもあるので大事に取っておきたい部分でもありますが、自分自身に対して少々考えすぎだなーと思うことがあります。不安に飲み込まれそうになる時があるので、考えずに何もかも忘れる瞬間をもっと作っていきたいです。
②物理的に自分を大切にできていない
平田さんのお手紙を見ていて気づいたのですが、私は食生活や運動習慣、肌や髪のケアなど、まだまだ物理的に自分を大切にできていないなと思います。背筋を伸ばしたり足を組む癖を直したりと、物理的なことに対する意志の強さが圧倒的に足りないので、意識改革をしていく必要があるなと感じています。
③人に頼るのが苦手
2店目の本屋を作ってみて、まだまだ私は人に頼るのが苦手だなとひしひし感じています。頼るのが下手ということは、「自分が成し得たいことに対して自分だけの力では足りない部分がどこなのか」という、未来を描く力や自己理解が欠如していることだと思っているので、もっと自分自身を分析して、適切に人に頼る力を身につけていきたいです。
④衝動を抑えられない
これは夫に言われたのですが、私は「これだ!」と思うと脇目も振らずに突き進むところがあるそうです。マンションの部屋を決める時など、「ここだー!」と思い込んだら最後、俺の話を聞いてくれなくて困ったと……。笑 たしかに「こうだ!」と思ったら猪突猛進、周りが見えなくなってしまうところがあるので、直感を得たとしても一度冷静になって考える力はもっと必要だなと感じています。
⑤データが苦手
お店の収支表や自分自身の売り上げ把握、さらには自分の基礎体温など身体のことまで、数字をつけたり見たりすることが苦手です。ただ数字は真理を表すものだと思うので、もっとうまく付き合っていく努力をせねばと感じています。
*
5つずつ書いてみて、ここ5年ほどが自分自身の内面に大きな変化を与えた時期だったんだな、とあらためて感じました。
これから変わっていきたい「②物理的に自分を大切にする」「③人に頼る」は、平田さんが日々大切にされていることだと思います(データも平田さんは得意ですよね!)。
特に「人に頼る」ことについて、平田さんはいつ頃からできるようになりましたか? それとも最初から得意だったのでしょうか。2店目の本屋をオープンしてはじめて自らチームを作り、いま特に気になるテーマなので、平田さんのご経験談を聞きたいです。
もちろんほかの話題でも大丈夫です。
またお返事お待ちしています!
あかし
平田→あかしさんへ
あかしさん、丁寧なお便りありがとうございました。5つ教えてください!という質問が10個になってかえってきてびっくりしました。これが倍返しですね(←ドラマ見てませんし、ちょっと古いですね笑)これから変えたいことにドキッとしますね。自分にあてはめたらどうなんだろうか?と興味深く読みました。
特にこれから変えたいことの4番「衝動を抑えられない」が驚きです。確かに岡山に移住して2拠点にした件にしかり、2店舗の出店しかり、私が出会ってからのあかしさんの積極的な行動も、この衝動からきていたとすると納得できますね。何らかの衝動的な原動力がないと、こういう決断ってなかなかできないですよね。そうすると、持ち味なのかもとも思いました。旦那様には申し訳ないですが、まだまだ衝動を抑えられないあかしさんを見ていたいと思いました。
さて、今回の「人に頼る」ですが、これは私が経営者という立場になってから身につけたスキルになります。正直、デフォルトでは全くこの機能はありませんでした。。自分でやりたいタイプだったので人に任せる、頼るがあまりできなかったと思います。過去の経験と性格特性を含めて振り返ってみたいと思います。
前提条件として
1.私の場合、能力に凸凹がある。得意なこととできないことの差異がすごい。だが、若い頃はこの特性についての理解がまだ十分ではなかった。
2.なのにも関わらず、自分でやってみることが好きなので、一度はトライする性質があった。
3.リソースに限りがあることに気が付いていなかった。
そんな、はる香32歳。パンと日用品の店わざわざを開業します。一人でできることだけやってみたいという気持ちから、個人事業主として一人で開業しました。パン焼きから売り場設計、仕入れ、店頭接客販売、経理、オンラインストア、何でも一人でやります(今のあかしさんと一緒ですね)。
割と早く話題となり、パンを焼いても焼いても足りない状況がやってきます。ですが、誰かと一緒にパンを作るという考えは持ち合わせていませんでした。自分の労働時間を増やし、製造量増加の解決を図っていきますが体に大きな負荷をかけ、睡眠時間も減り、気絶したように眠る日々でした。
そこで1年後、アルバイトさんが入社する運びとなります。掃除、レジ、店頭での販売業務を主にお願いすることになりました。店を始めてから接客が苦手だということは気がついていたので、ここはスムーズに受け渡すことができました。また掃除などの業務はそこまでスキルを必要としないため、指示すればほとんど人ができたと思います。
ですが、当時は事細かに指示を出していたと思います。認識としては「店は自分のもの」であり、あくまでも自分が主役でアルバイトさんは脇役ですね。自分の分身が欲しかったと思いますし、自分と同じように同じクオリティを担保できる人が欲しかったです。
なので、アルバイトさんは合う人は合う、合わない人は合わなかったと思います。相性がたまたまよければ継続して働いてもらうことができましたし、そうでなけば1年ほどで退社という感じでした。初期のキーワードは「自分の分身を求めがち」でしょうか。殆どの人が陥る可能性がある気がします。
そんなこんなで5年が経過します。はる香37歳、初めての社員を雇うことになりました。この頃には製造にもスタッフが入っていましたが、薪窯で焼く工程やレシピ作成などの重要な領域にはアルバイトさんを参加させることはなかったです。そして、正社員を雇うとなった時に、考え方を変えないといけないと強く感じました。
入社された方はシェフ経験がある方だったので、レシピをいろいろと教えてもらったりカフェの提供メニューの作成もアドバイスをもらいました。またパンの製造もどんどんと任せていって、最終的には一人で焼いてもらっていました。たった1年の経験でしたが、劇的に人への仕事の振り方が変わった瞬間でした。「志や考え方は伝えるが、自分で考えてやってもらう」ということをかなりやった年でした。
いろいろな人と働いた5年の気づきとしては、
1. 自分よりうまく仕事をやる人は死ぬほどいると気づいた
2. 自分が人よりかろうじて優れていることは想像力と考える力。ここを強みにしてポジションどりをする。他は全部得意な人がやればいい。
3. いくら強みがあったとしても人間のリソースは限られている。時間も体力も何もかも足りていないので、チームを作ることをやりたい。
そんなことで仕事を振りまくるはる香がこのあたりから登場します。その後、人に頼りすぎ、仕事を任せすぎ、全体を管理することを忘れて、一度はうまくいったチーム作りが崩壊していく失敗も経験しました。これが創業してから10年後の大量退職につながっていきました。
任せるって本当に「塩梅」なんですよね。任せた後もある程度ハンドルを握って管理はしないといけません。人間ってとても難しくって、任された後も誰かがその仕事もみてくれなけばつまらなくなるし、かといって人に指示されてばかりもつまらない。ある程度の領域を区切ってあげるのがよいですね。経営用語でいうと権限委譲です。権限の範囲を定めた上で仕事の裁量をふってもらうことが大事ですよね。
例えばAさんには1店舗丸々任せます!あとはよろしくお願いします!というのが丸投げでNG。この店舗は売上予算は〇〇を達成とか来店人数とか、店の陳列ルールや設えなどのレギュレーションを決めて、お互い合意が取れている状態で任せるという感じです。そして月に何度かのMTGで進捗を確かめながら相談に乗っていく。なんか経営の話になっちゃいましたね。ごめんなさい。
「頼る」も塩梅ですよね。先にあげた経験から殆ど私が無能なことには気が付いていたので、基本的に仕事は人に頼ってます。データを見て分析するのはまだできる方ですが、肝心のデータ作りができないので(エクセル苦手)、指標は指示しますが、全部作ってもらってますし、店頭での接客などは全て店長とアルバイトさんにお願いしています。
あとはもう本当に忘れ物が多いので、どこかにいくときは皆んなに忘れ物が多いことを共有して指摘してもらうようにしたり。あと、タスクが基本的に多いのでタスク漏れもしてしまいがちなので、メールのCCには関係する人を皆んな入れさせてもらい、気が付いたらリマインドしてくださいと社内には伝えてます。
とにかくいつも自分ができないことを共有して、助けてくださいとかなりの頻度で言ってます。あぁ、この人、本当にこれが苦手なんだなという意識で周りの人が動いてくれるのは感じてます。でも、そればっかりだと信頼が得られないので、先に話した自分のポジション「想像力」「考える力」を活かした仕事は自分で積極的にやって、みんなをひっぱっていくような行動をとるようにしています。
トップとしてやらないといけない、資金調達やプレゼンなどは全部自分でやりますし、大きなトラブルがあればトラブル対応は私の仕事です。やっぱり人がやりたくない仕事は率先してやることで、頼りになるなと思ってもらえたら嬉しいです。というか、それくらいしかできることがないので、やっているという感じです。
書いていて気が付いたのですが、頼ることができるから任せられるということではないのかもですね。「任せる」というのはこちら側の意思決定から作為的に動いている気がするので、認識を変えればスキルとしてセットできそうです。誰でも学べば習得できる可能性がありそうですね。
一方、頼るというのは性格特性に近くて、もともと私の場合、プライドが低いというか、立場を気にしないというか、誰に対しても謝ることを何とも感じないですし、子供にも平気でごめんと謝れます。それは自分のことをあんまり信じてないんです。
でもそうじゃない人っていますよね。自分の立場や経験を重んじる人であれば、なかなか頭を下げることができない人もいます。年齢や学歴が高かったり、職種として先生と言われる立場や政治家だったりすると、なかなか誰にでも頭を下げるということはしにくくなるのかもしれません。今までこういう人たちが使うのは頼るのではなくて命令だったんですよね。そういう意味では時代が変わってきていて、命令・指令から頼るマネジメントに変化してっているんでしょう。
そうなると「人に頼る」という行動は、相当意識をして改革していかないとできないことのような気がしてきました。自分がやった方がいいと思っていないことが前提条件として発動して、頼ることができるのですから、自分や相手をよりよく観察し、謙虚な気持ちでいることが大切なのかもしれません。
なんか、壮大な話になってすいません。書きながら自分でも腹落ちできました。経営の面で「平田さんは早期に人に仕事を任せられたことがすばらしかった」と褒められることがありました。個人事業主になると家族経営以外選択肢がないことがよくあります。なぜなら人に仕事を任せられないからです。何でも自分でという方は職人タイプで、経営タイプではないんでしょう。わたしは、素養として経営者タイプだったんでしょうね。
あかしさんは今、仕事で本屋2店舗運営とライター、編集という沢山のわらじを履いている状態だと思いますが、自分自身としてはどんなタイプだと思いますか?またどんな風にaruや編集業を未来に紡いでいくのかとても興味があります!ぜひ聞かせてください。
この日記を書くのがとてもいい振り返りの機会になっています。いつも楽しいお便りをありがとうございます。