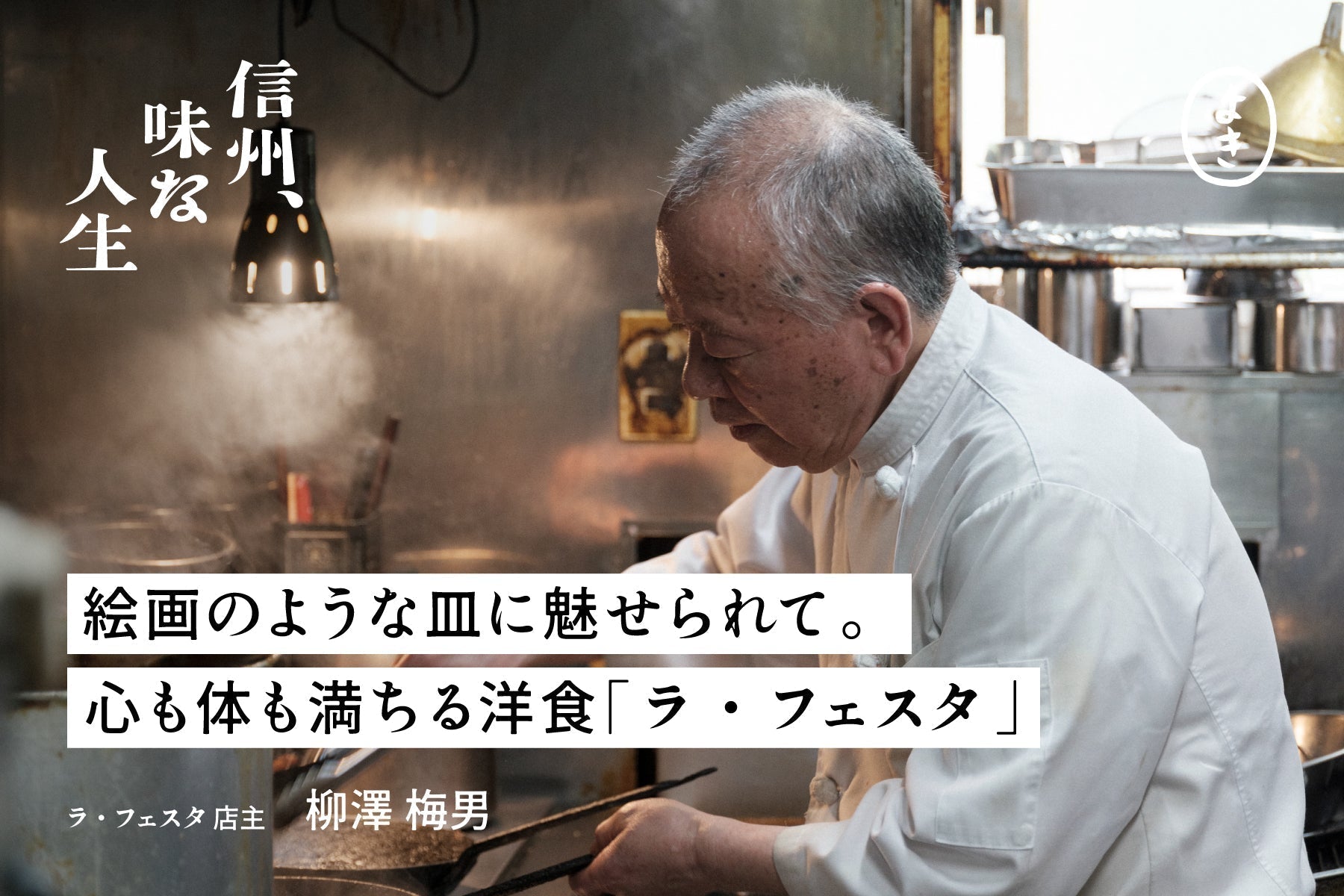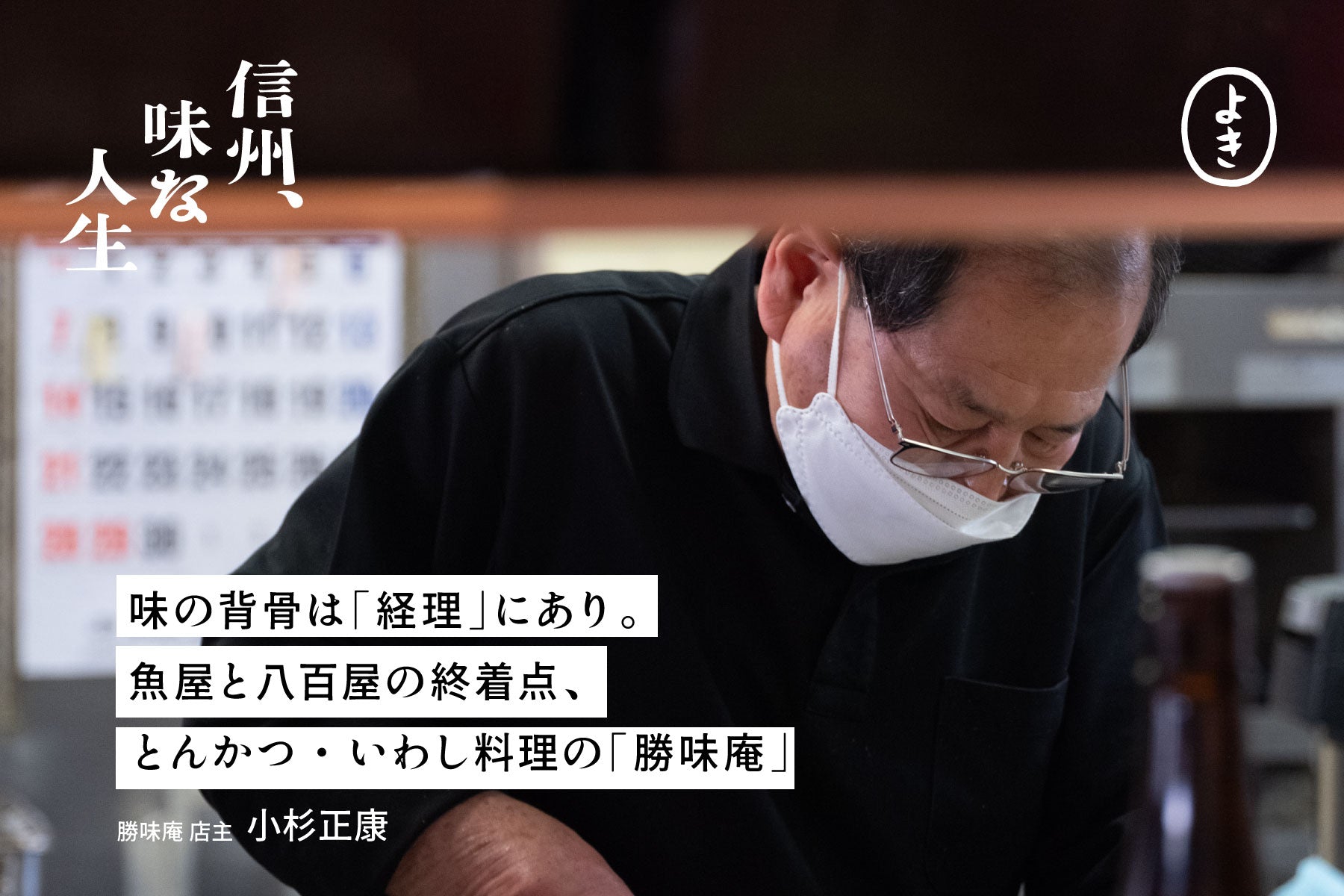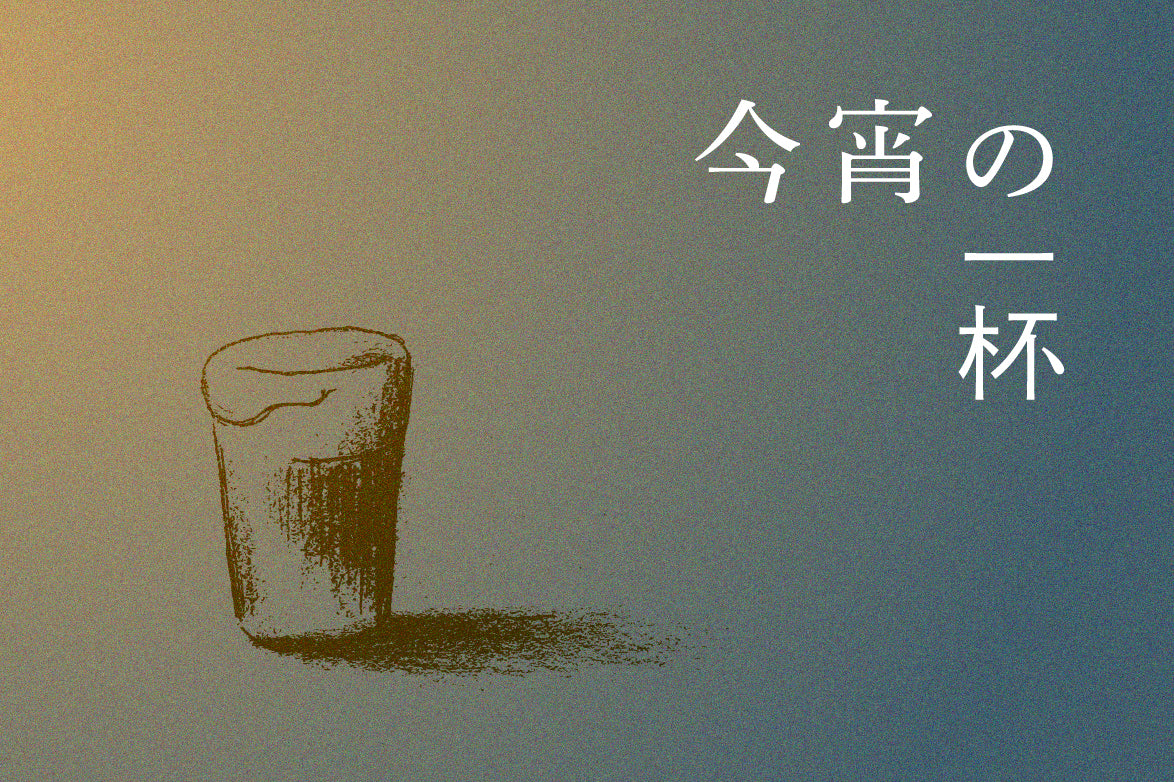「信州、味な人生」の取材を信州以外でやることがあるとしたら、味な店を知っていそうな人に、いつも通っている店を案内してもらいたい。そして「味な店を知っていそうな人と言えば、松野さんしかいないね」と、トントン拍子で案内人が決まった。
松野さんは、荒物雑貨や自社製品のバッグの卸を生業とした松野屋の代表だ。わざわざが創業した2009年からお取引をさせていただいている。松野さんは多分、最初にわざわざに訪ねてきてくれた経営者の一人だと思う。いくつになっても興味関心のアンテナを高く張り巡らせ、足を使って移動して、現地に赴いて話をして見て感じとったことを実行していく、本当に少年のような心を持った人だと感じている。
そんな人がいつも通う店に連れて行ってもらう夢のような企画が実現した。今回は、松野さんがずっと暮らしている街、浅草橋を中心にブラブラと歩きながら、食べて飲んできた話。

ご自宅で待ち合わせてラーメンがある甘味処へ
8月の中旬、一番暑い時間帯の14時、東京の気温は35度に達していた。待ち合わせは下町のど真ん中、松野さんのご自宅だ。初めて伺ったのだが、近くについたら松野さんの家だろうなとすぐにわかった。家の前の道路には鉢植えが並んでおり丁寧に手入れされているのがわかる。玄関は開け放されて、藍染の暖簾が涼しげに泳いでいた。あぁ、暑くても目で涼しさを感じることができるんだなとじんわりと胸が高なった。


通してくださった客間は、今年101歳で大往生されたというお母様のお部屋であった場所だった。置いてある家具やかご、まるで昭和にタイムスリップしてしまったかのような落ち着く部屋で、冷えた(多分)ルイボスティーを松野さんが出してくださった。今日の取材のコンセプトやタイムスケジュールなどを確認していき、この時、決めていたのは2軒のはしご。なのに、結果的に大盛り上がりして時間内に4軒はしごして、いやはや飲みすぎました!
最初に連れて行ってもらったのは、谷中の松野屋の実店舗からもほど近い1945年創業の「花家」だ。甘味処に行きたいです!というリクエストに対して提案してくださった花家は、ラーメンや餃子もある甘味処だった。お店に着いて店頭のショーケースを見るも、ショーケースの中の食品サンプルは、殆ど中華料理屋の様相だ。


おいしそうな料理と甘味が並ぶショーケース
松野さんによると、昔の甘味処と言えば、ラーメンがあることが普通だったと言う。松野さんは高校生の時から花家に通い、もう60年も通っているというのだから驚いた。私はまだ60年生きてさえいない。60年通い続けている松野さんもすごいけど、それ以上に営業している花家もすごい。とりあえず、松野さんの教えにしたがって、ラーメンと餃子セットを頼んでクリームあんみつを頼むことになった。

周りを見渡すと、ラーメンと餃子のセットを頼んでいる割合が高い。後で入ってきた観光客と思わしき方々はかき氷を頼んでいる。地元民は中華屋として認識し、観光客は甘味処として認識しているのか?松野さんは学生の頃に、ラーメンと餃子を食べた後にクリームあんみつを食べていたというのだから、松野少年の食欲恐るべし。
だが、確かに運ばれてきたラーメンは、あっさりとした醤油の色合いのスープにストレート麺と、シンプルでペロリと食べられてしまいそうだった。そして、大きめなふっくらとした餃子はこんがりとした焼き色が食欲をそそり、かぶりつきたくなる。街中華の名店と言っても良さそうなクオリティのラーメン餃子セットで、取材チームから歓声があがり、松野さんもニコニコしてその様子を見ている。


おいしいものを食べながらの会話は弾み、松野さんの若い時の話になった。松野さんは大学在学中に、アメリカに色んなモノを見にいく一人旅をしていたそうだ。そして、ものづくりがしたいと大学卒業後に、京都の一澤帆布に就職しバッグの作り方を習得した。なかなか修行を許してくれなかった一澤帆布さんに何度も通い潜り込む話では、3カ国語話せないとダメと言われて「日本語・英語・落語」で3ヶ国語できると言って小噺をやる件を、松野さんはそれこそ落語のように話してくれて、爆笑してしまう。
松野さんの口から沢山の人やブランド、概念の話がポンポンと出てくる。今では日本で当たり前のように認知されているブランド(THE NORTH FACE、L.L.Beanなど)もかつてはそうではなかった。と思えば、話は民藝運動に飛び、柳宗悦、河井寛次郎などの話が出てくる。モノの話をしていたかと思えば、落語やお笑い、喫茶店の話になって、それが不思議と松野さんの人生に一本の筋、骨格のようなものを与えていて。多種多様な要素が松野さんになっているのだなと感じざるを得ない。
この京都時代の話も大学時代のアメリカ放浪の話も、何でもかんでもべらぼうに面白い。松野さんはずっとお喋りでしたか?と聞くと「うん」とニコッと笑ってくれたのがとても印象的だった。

松野屋に行って、呑みに行きましょう。
花家を堪能して、散歩しながら松野屋に向かうと、見たことのあるおせんべい屋さんが目に留まった。「あのお店はいつも松野さんがお土産にくれるお煎餅屋さんですか?」と聞くとそうだと言う。お店の名前は「谷中せんべい信泉堂」。松野さんは長野にくる時にいつも軽い東京土産をくださるのだが、それがとってもおいしくてセンスがいい。ぜひ!と立ち寄らせてもらうことになった。


日よけの暖簾がかかっていても趣を感じる外観

海苔巻き、ザラメ、ゴマなど種類が豊富で選ぶのがたのしい
手土産を片手に、いざ松野屋へ。奥様のきぬこさんもちょうどいらっしゃって、少しお話をして買い物を楽しんだ。私はわざわざでは取り扱っていなかった布団叩きをこの場で購入。酔っ払って落として行かないか心配だったけど、無事持って帰ってこれたのでほっとした。
松野屋が荒物の卸をし始めたのは、1980年代の頃だった。一澤帆布での修行後、東京に戻ってきた松野さんが作った帆布バッグが松野屋で大ヒットすることになる。そして、時代が過ぎバッグの販売が低迷し、アメリカのヘビーデューティー(激しい使用や過酷な環境に耐える実用性が高いアイテム)の概念を、日本の荒物の中に見出して卸販売することになったのが、今の松野屋の形の原型である。


松野さんは色々なところで見つけたエッセンスを自分なりに解釈して、元々あったものに新しい価値をつけることができる人だと思う。実店舗には次々とお客様が来店し、昔ながらの荒物雑貨を手にとって購入していく。きっとそれぞれの家で日常的にヘビーユースされて、使い倒されていくことが想像できて、まさにヘビーデューティーじゃんと思った。

開店前なのにお客さんがいっぱいの店
時刻は16時半。松野さんの自宅に戻り、松野さんが一番通っているという居酒屋「むつみ屋」に向かう。16時半の開店と同時に暖簾を潜ると、何故かもう半分以上の席が埋まっていた。ど、どういうこと?!暖簾がかかる前に常連さん達は店に入って呑み始めるらしい。何とも寛容な店である。

松野さんに続き…

平田も入る
注文はとりあえず生ビールで、私は好きな小肌を頼んで、松野さんがマグロのブツ、枝豆などを注文する。壁にかかったメニューは、THE居酒屋のお馴染みオンパレードで来たことがないのに、メニューを見ないで頼めそうで、それだけでもう楽しくなってしまう。食べたことのないメニューが並ぶ驚きや発見も悪くないけど、いつもの店でいつものメニューが、いつもどおり美味しい。そういう店は安心と落ち着きを心に与えてくれる。

そして、店の入り口がガラガラっと開いたと思ったら、店員さんが生ビールを運んできた。一旦厨房から勝手口を出て、正面入り口から運ばれてくるスタイル。キンキンに冷えたグラスになみなみと注がれたビールにきめ細やかな泡。見るからにおいしそうで早く乾杯の撮影をおえて欲しいと切望する。
実は、私は初見の店では生ビールは頼まない主義を貫いている。というか、店の技量がわからないと生ビールがおいしいかわからないと思っているからで、生ビールが怖い。最初の一杯が期待通りでないと楽しさが半減してしまうから、毎度妥協の瓶ビールをついつい頼んでしまうのだ。だが、この店の生ビールは最高だった。クリーミーな泡、キレのある炭酸と冷たい喉越し。暑さも相まってぐびぐびっと⅓を飲み干してしまった。


松野さん、いい顔して飲まれます!
安心だ。松野さんのおいしいは私のおいしいと一致しているぞと期待感が増す。続いて到着したマグロのブツ。トロトロのいいところがブツになっていてとってもよい。小肌の酢加減もちょうどいい。これならアジのたたきも食べてみたいと追加で注文。松野さんはずっとお喋りをしていて面白すぎるんだが、話もそこそこに聞きつつ、私はひたすら目の前の食事に取り組んだ。あぁ、東京の居酒屋の魚はこんなに安くておいしいのか。梅きゅうもください!酎ハイに梅干しを入れてください!

開店から30分過ぎた17時すぎ。信じられないけど、おじさん達でほぼ満席だ。本日は木曜日で平日です。皆さん、お仕事はどうしたんでしょうか。もちろん、私たちも含めてですけれども。これは本当に仕事なんでしょうか。仕事と遊びが溶けていて最高だ。松野さんはいつもは19時頃にくるからこんなに早い時間から混んでいるなんて知らなかったと言う。でもいつも満席だよ。そりゃそうだ。安くておいしいって東京にはあるんだなぁ。東京っていいなぁと少し思ったのだった。

1時間ちょっとお邪魔して18時すぎに会計をして失礼をすることになった。店主の笑顔も気持ちがよく、お礼を言いながらとってもいい気分で外に出る。まだ空は明るくて酔っ払っている自分が少し恥ずかしくなる。松野さんが焼きとん屋さんに行ってみようと言う。一杯と一串食べれば大丈夫だよ。行きましょう!行きましょう!歩いて飲み屋をはしごするのが東京らしくてかっこいい。松野さんはむつみ屋も20分か30分しか滞在しないと言う。えっ、1杯だけ飲んで出るんですか?と聞くと、2杯。粋ですねぇ。
冷凍庫のテーブルで立ち飲み
3杯飲んでほろ酔いデス。まだ明るい下町を歩きながら、雑談を繰り返して着いた店もお客さんで一杯だ。奥も少し空いているけど、手前の冷凍庫をテーブルにして一杯やりましょうということになった。約束通り一串と飲み物各自一つ。


話題は、また松野さんの過去に飛ぶ。「松野さんはいつも明るくて元気でこちらも元気をいただいてますが、嫌になったり辛いと感じる時もありますか?」と聞いてみた。松野さんもやっぱり仕事の上では辛く感じる時もあると言う。そして河井寛次郎の詩を教えてくださった。
仕事が仕事をしてゐます
仕事は毎日元気です
出来ない事のない仕事
どんな事でも仕事はします
いやな事でも進んでします
進む事しか知らない仕事
びっくりする程力出す
知らない事のない仕事
きけば何でも教へます
たのめば何でもはたします
仕事の一番すきなのは
くるしむ事がすきなのだ
苦しい事は仕事にまかせ
さあさ吾等はたのしみましょう
サラサラっと暗唱して聞かせてくれたこの詩が心にとても残っている。仕事が仕事をしているから我々は楽しむと言っているが、実際、私の中の仕事が仕事をしているわけで、仕事がいちばん好きなことは苦しむことだと言っているけど自分自身が苦しむことでもある。
河井寛次郎にとって仕事は、単なる職業ではなく、生き方そのものであり、暮らしと切り離せないものだった。暮しが仕事、仕事が暮しであるとも言っていて、この詩は仕事をしてくれる仕事への深い尊敬と感謝の気持ちが入り混じったものであると思った。
今日の取材はまさにそんな1日であった。仕事が仕事をしてくれる間に我々は楽しみましょう。松野さんに教わったこの詩は忘れられないものになったのだった。

さて、この後、我々は4軒目のバーで新幹線までの時間を惜しむように語らったわけだが、こんな楽しい取材はなかったなと思うほどの充実した時間を過ごすことができたのは、紛れもなく松野さんの人柄によるものです。
どのお店もとても居心地がよく、松野さんが店主と交わす言葉の雰囲気から、長く通ってきた客と店の信頼感を感じました。新しい店をいつも開拓する人もいるだろうけど、自分はやっぱりこっちがいい。言葉が濃密であるより、顔を合わせる回数が多い方がいい。ということで信州味な人生番外編はここまで。また旅をするように粋な方に馴染みの店を案内してもらうこの企画の続きを書きたいです。どうぞ、次回をお楽しみに。



取材でお邪魔させていただいた店舗一覧
◾️花家
住所 :〒116-0013 東京都荒川区西日暮里3丁目2−2
電話番号:03-3821-3293
営業時間:11時00分~19時30分
定休日 :火曜日
◾️谷中せんべい 信泉堂
住所 :〒110-0001 東京都台東区谷中7丁目18−18
電話番号:03-3821-6421
営業時間:10時00分~17時30分
定休日 :火曜日
◾️松野屋
住所 :〒116-0013 東京都荒川区西日暮里3-14-14
電話番号:03-3823-7441
営業時間:11時00分~19時00分
定休日 :火曜日
◾️むつみ屋
住所 :〒111-0053 東京都台東区浅草橋1丁目18−6 塚田ビル
電話番号:03-3866-5078
営業時間:16時30分~22時00分
定休日 :日曜日
◾️西口やきとん
住所 :〒111-0053 東京都台東区浅草橋4丁目10−2
電話番号:03-3864-4869
営業時間:16時30分~23時00分
※土曜日は16時00分〜22時00分、日曜日は15時00分〜21時00分まで