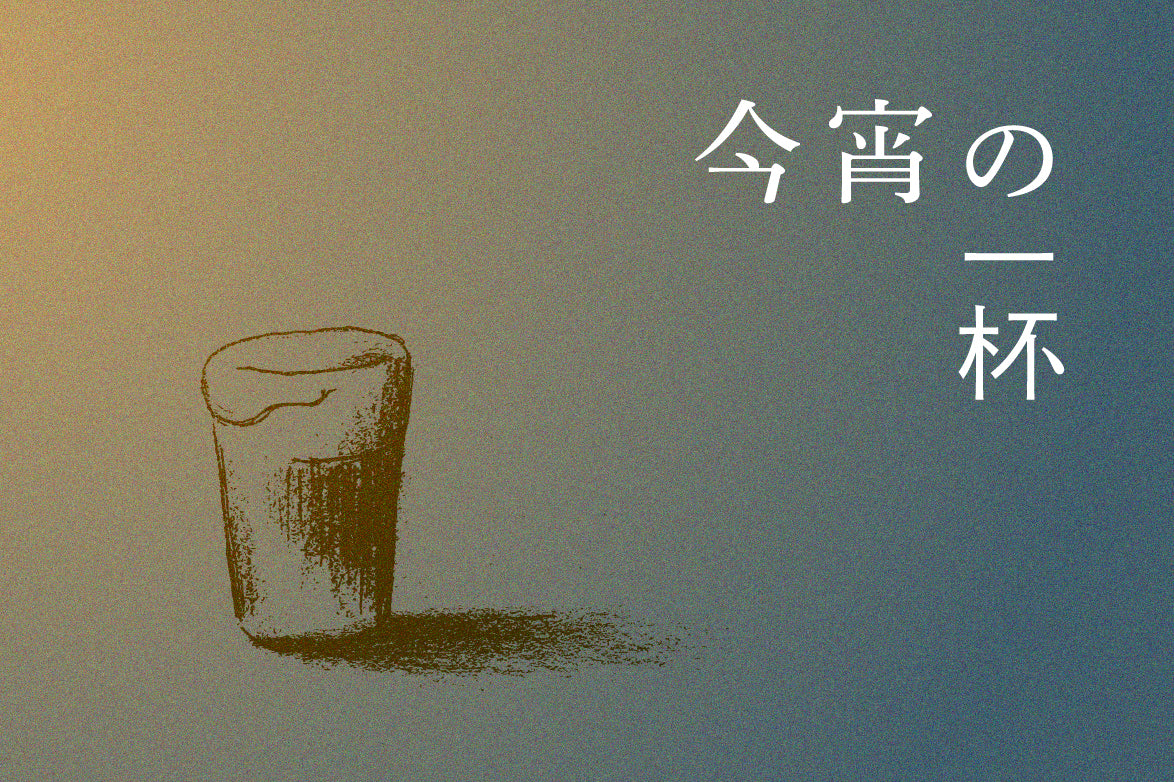目次
カーペットメーカーが開いた宿
日本全国、どこにでもあるような住宅街。そのなかの細い道をぐんぐん進んでいくと、開けた土地に目を引く建物が現れる。ヨーロッパの郊外で見かけるような、落ち着いた雰囲気のモダンな二階建て。広々とした敷地を多彩な植物が囲むこの場所は、2025年3月、大阪府和泉市に誕生した「TACTILE HOUSE OSAKA(タクタイルハウスオオサカ)」だ。

「タクタイルとは、英語で『触覚』『触って感じる』という意味になります」と堀田将矢(ほった・まさや)さん。数百メートル離れた場所に本社を構える堀田カーペットの3代目で、この宿のオーナーだ。
「1階はショールームで、2階が1日1組限定の宿になります。1階のショールームには、2階で使用している建材や家具、カーペットのサンプルを展示します。2022年にこの土地を購入してから、とことんこだわってこの施設を作ってきました。ここは日本の工芸建材を体感できる場所になります」

ここでふたつ、疑問がわく。
なぜ、カーペットメーカーが宿泊業を?
なぜ、カーペットメーカーが日本の工芸を?
その答えは、堀田さんの歩みとともにある。
日本最大のカーペット生産地・泉州
堀田さんは1978年、和泉市で生まれた。和泉市を含む大阪の南部、泉州と呼ばれるエリアは日本における最大のカーペット生産地として知られる。全国で製造されるカーペットのおよそ80%が、泉州を中心に大阪府でつくられている。
カーペットには大きくわけて「織物」と「刺繍」の2種類の作り方がある。織物のひとつが18世紀にイギリスのウィルトンという町で発明されたカーペット専用の織機「ウィルトン」で、ウールの経糸(たていと)と横糸を重ねて織りあげる「ウィルトンカーペット(以後、ウィルトンと表記)」。刺繍で作る代表的なものは、ファブリックや樹脂を貼り合わせて布に縫い付ける「タフテッドカーペット」などがある。
簡単に説明すると、ウィルトンは伝統的な技法で作る織物で、タフテッドはウィルトンの約30倍の速度で生産できる、量産を目的とした低価格帯のものになる。1930年代にタフテッドが登場すると、日本の一般家庭にもカーペットが普及した。その一方で、職人の高い技術が要求されるウィルトンの需要は激減する。
堀田さんの祖父が和泉市でウィルトン専門の「堀田カーペット」を立ちあげたのは、タフテッドが普及し始めた1962年のこと。市場縮小の逆風のなかで、堀田カーペットは気を吐いた。
同社はウィルトン専門業者のなかでも糸から開発している稀有な存在で、特許の糸を数種類、オリジナル糸を30種類ほど持っている。また、世界中で生産されているウールの特徴や適性からニーズに合わせた商品を提案できるのが、大きな強み。さらに、ウィルトンならではのデザインや色を表現できる技術力、タフテッドよりも高い耐久性と機能性が評価され、誰もが名を知る高級ホテルや高級ブティックにカーペットを卸していた。


祖父から後を継いだ父親も、家業に誇りを持っていたのだろう。堀田さんは、父親が愚痴ったり、大変そうにしているところを見たことがないという。
「家族でいる時も仕事の話を普通にする父親で、糸の特許を出したとか、こんなブランドを始めたとか、ものづくりから戦略的な売り方まで、よく話していました。それがいかにも楽しそうで、子どもの頃から、面白い仕事をしているんだなと感じていましたね」
ただし、カーペットに関してはいい印象を持っていなかった。
「詳しく知っているわけじゃないけど、ダサいというイメージしかなかったですね。僕が物心ついた時にはカーペットを敷いている家がどんどんなくなって、おしゃれな家の写真は全部フローリングでしたから」

「奇跡」で入社したトヨタで学んだこと
私立の中高一貫校を出た後、1年浪人した堀田さんは、北海道大学に進学。あえてフローリングの部屋を選んで、ひとり暮らしを始めた。「田舎のなかの都会に住みたくて、ずっと憧れていた」という札幌での生活は、「最高でした」。
大学3年生の秋に入ると、就職活動が始まる。堀田さんは似たようなリクルートスーツを着て企業をまわる同級生を冷めた目で見ていた。
「いま思えば、実家の存在が頭にあって、自分だけは大丈夫だろうと思っていたんだと思います。でも、当時は将来なにがしたいということもなく、とにかく就職活動がイヤで避けていました」
とはいえ、父親と家業に就くことについて話をしたわけでもない。なんとなく不安に感じた堀田さんは、大手住宅総合メーカーとトヨタ自動車の2社にだけエントリーした。住宅メーカーは家業とのつながりも頭にあったが、トヨタに関しては、特に車が好きだったわけでもなく、ただ名前を知っている大企業に過ぎなかった。そのトヨタでなぜかとんとん拍子に面接が進み、採用が決まる。堀田さんは「奇跡です」と苦笑した。
2002年、トヨタに入社すると、調達部に配属。車に使うタイヤ以外のゴムやガラスの仕入れを担当することになった。
「世界で一番安く、安定的に早く部品を調達するのがミッションでした。決裁をもらうためには、上司に世界一安い理由とその背景を証明しなきゃいけないんですよ。社会人1年目、2年目で予算は何百億円レベルなのでプレッシャーもあったけど、鍛えられましたね」
父親からの電話
調達部での仕事は思った以上にハードだったが、「すごくやりがいがあったし、楽しかった」と振り返る。1年目に社内結婚し、公私ともに充実していた。 だから2006年、ある秋の日に父親から電話がかかってきてきたときは、戸惑った。
「(家業を)継ぐか、継がないのか、決めてくれ」
それまで跡を継ぐのかどうか父親と話し合ったことがなかったから、戸惑った。すぐに返事をすることができず、「わかった。少し考えさせてほしい」と答えた。
それから1年半、悩み続けた。仕事は充実していたし、給料も待遇もよく、そのまま夫婦で働き続ければ、なに不自由ない生活が待っているとわかっていた。
それでも、大阪に戻ることを決めた。堀田さんの頭のなかには、いつも笑顔で仕事の話をしていた父親の姿があったからだ。
「一度、オヤジと一緒に仕事をしてみたい」
これが、トヨタを辞める最大の理由だった。
2008年1月末日にトヨタを退社し、翌月から堀田カーペットで働き始めた。役職のないイチ社員で、給料は半分になった。過去の決算書をチェックすると、父親から「好調や」と聞いていた通り、悪くない内容だった。

工場内には、創業者の祖父の銅像がある
ところが半年後の9月、リーマンショックが起き、不景気の波が直撃。翌年には「来月、織るものがない」という苦境に陥った。固定費を抑えるためにアルバイト、パートも含めると30人程度のスタッフの勤務時間の調整が必要になる。その担当になった堀田さんには、いまだに忘れられない出来事がある。
「当時の工場長は60歳を超えていて、年金をもらえる年齢だったから、僕はなんの重みも感じずに、勤務時間を短くし、その分給料も減らさせてもらうねと言いました。そうしたら、『こんな条件では生活できへん。やめるわ』と言って家に帰ってしまったんです。大企業で働いていた僕は、勤務時間が減ることが生活に直結するという感覚がなかったので、本当にショックでしたね」
中小企業の現実を知らなかった堀田さんは、この後も迷走する。
笛吹けども誰も踊らず
リーマンショックの影響が収まらず、「大変なことになってるな」と感じていた堀田さんは、自分にできることはなにかを考えた。思いついたのは、「トヨタ式カイゼン」だった。
「トヨタでは、論理的思考能力を鍛えられ、問題解決を学びました。あるべき姿があって、現状があって、その乖離が課題だと。その課題の原因を探って、ひとつひとつ解決する。経営も同じだと思っていました」
堀田さんが最初に手を付けたのは、組織改革だった。その頃の堀田カーペットには「組織」がなく、社内の「担当」も曖昧だった。そこで、組織をつくり、それぞれの部署の現状とあるべき姿を書き出し、課題をまとめて、会議を開いた。そこで課題を改善しようと声をかけたものの、笛吹けども誰も踊らず。堀田さんの後に続く者はいなかった。
例えば、工場内で「整理」「整頓」「清掃」「清潔」の「4S活動」をしましょうと呼びかける。しかし、なにを捨てていいのか、どこにしまえばいいのか、誰が担当するのか、就業時間にやるべきことなのか、勝手には決められないという現場の従業員たち。「そこは自分たちで考えてほしい」という堀田さんとの溝は、どんどん深まっていった。

リーマンショックの余波で、2011年には売り上げが過去最低の4億3000万円にまで落ち込んだ。このままではらちが明かないと危機感を募らせた堀田さんは、当時、工芸メーカーの経営支援を始めていた中川政七商店の中川淳さんにコンサルティングを依頼した。しかし、意思決定の所在が社内であやふやになってしまい、思ったようにうまくいかなかった。
このコンサルの件も含め、父親からはやることなすことに反対され、衝突が絶えなかった。
「自分の人生のなかで一番しんどかった時期ですね。良くも悪くも小さい頃からずっと、きれいに敷かれたレールに乗りながら過ごしてきたので、自分自身で考えなきゃいけないことがなかったんです。与えられた環境でベストを尽くすのはすごく得意だし、好きでした。でも経営って、誰も環境を与えてくれませんよね。本当になにかをやりたい、やらなければいけないという自分の意志がなかったし、責任を負うことを怖がっていたから、誰もついてこなかったんだと思います」

0.2%の市場への挑戦
霧が晴れたのは入社から6年後の2014年、目指すべき道がはっきりと見えた時だった。堀田カーペットはホテルやブティックなどBtoBの売り上げが大半だったが、堀田さんはBtoC、一般の消費者向けのカーペットに目を付けた。家庭用の床材は、フローリングが圧倒的シェアをもつ。カーペットは追いやられていた。
1980年代、「カーペットにはアレルギーの原因になるダニやホコリがたまりやすい」という悪評が広まった。これが主な原因で、新築住宅にカーペットを敷く人の割合が0.2%にまで減ってしまったのだ。
しかしカーペットは、他の床材に比べて空気中に舞い上げるほこりの量が1/10になるので、部屋の空気をきれいに保つことができる。羊毛はキューティクルがあるので、汚れがつきにくく落ちやすい。高級ホテルや高級ブティックは、ウールの高級感や質感だけでなく、合理的な理由で堀田カーペットのウィルトンを採用しているのだ。

堀田カーペットで働き始めてから改めてウィルトンの魅力を知り、新築した自宅のトイレと風呂場以外、すべての床面にカーペットを敷くほど惚れ込んだ堀田さんには確信があった。すこぶる快適なウィルトンのカーペット生活を気に入る潜在顧客がいるはずだ。
しかし、悪評は根強く、そもそも消費者と接点がない。そこで堀田カーペットの技術を活かして肌触りのいい、デザイン性の高いウールのラグを開発することで、ウィルトンを知ってもらうための窓口をつくろうと考えた。
堀田さんは、以前から気に入っていたマルコモンドという靴下ブランドのアートディレクター、池田充宏さんに相談した。大きな転機となったのは、ロンドン出張。池田さんが参考になるとリストアップした50軒すべてに足を運んだ。そのなかで「S.E.H KELLY(エスイーエイチケリー)」というテーラーを訪ねた時に「これだ!」と直感した。
「夫婦ふたりでやってるブランドで、誰も行かないような路地裏にある10坪ぐらいの店舗なんですよ。でも、ものづくり感をはっきりと示しているアパレルショップで、洋服もすごくシンプルなんだけど、質の高いものだと一目でわかる。そのトンマナがすごく素敵で、うちの目標になるブランドを見つけた!と思ったんです」
同じ頃、もうひとつの重要な出会いがあった。たまたま社員から聞いた、ウイスキーメーカー「BOWMORE(ボウモア)」。シングルモルトウィスキーの聖地と呼ばれるスコットランドのアイラ島のウイスキーメーカーだ。ここもホームページを見て、記事を読み、一目惚れした。
「彼らは、世の中がどんな味を必要としているかを考えているわけではなくて、自分たちが本当にうまいウイスキーを作るということしか考えていないと思うんです。だから、熱心なファンもいれば、アンチもいる。そのものづくりの姿勢に惹かれましたね」
大反響の新ブランド
迷いが吹っ切れた堀田さんは、池田さんに「こういうブランドにしたい」というありったけのイメージと想いを伝えた。それから池田氏との濃密なキャッチボールが始まり、構想に1年、開発に1年をかけて、2016年にリリースしたラグブランドが「COURT(コート)」。


第一弾はフィッシャーマンズセーターをモチーフにしたデザインで、技術的にも「面倒くさすぎて、誰もやらないだろう」という作りにした。この時、堀田さんは「これで売れなかったら、もう諦めよう」と考えていた。それほどにやりきったという実感があったし、絶対にうまくいくという手応えもあった。
「根拠のない自信ではあるんですけど、市場全体を眺めた時に、これといったラグのブランドが存在しなかったし、僕たちがやる意味はそこにあると思っていました」
コートの反響は大きかった。リリースしてすぐ、ライフスタイル系のメジャーなメディアに取り上げられ、インテリアショップでの取り扱いも立て続けに決まった。
コートを知った人は、堀田カーペットに興味を持つ。そのタイミングを逃さないために、翌年、リブランディングを行い、「S.E.H KELLY」や「BOWMORE」をイメージした新しいホームページを作った。すると、それまで1年に1、2件程度だったホームページからの問い合わせが1カ月に数件くるように。しかも、送り主は、ほとんど縁のなかった設計事務所や個人。それまで、BtoBのビジネスが大半だった堀田カーペットにとって、大きな変化だった。この年、堀田さんは三代目に就任している。
「父から直接言われたわけじゃないけど、僕がくすぶっていた時、結局お前はなにがしたいんだ? と問われていたんだと思います。入社してから初めて強い意志を持って、コートを作りました。父は、そういうことを待っていたのかな」
BtoCの扉が開いたら、オフィスを訪ねてくる人が増える。そこで2018年、オフィスを全面リニューアルして、近代的な居心地のいいスペースにした。カーペットが敷き詰められ、訪問者が靴を脱いでその心地よさを体感できるオフィスは、好評を博した。

最大の危機に陥ったコロナ禍
2019年は東京オリンピック向けの注文と納品が重なったほか、コートをきっかけに一般住宅へのカーペット販売も増え、売り上げは過去20年で最高となる7億円に達した。
ここで手を緩めず、「DIY市場(新しい市場)」と「ニーズへの対応」をするために開発したのが、DIYカーペット「WOOLTILE(ウールタイル)」だ。これは1枚50センチ四方、8色のカラー、4つのパターンを持つ100%ウールのタイルカーペットで、部屋の形に合わせてハサミやカッターで簡単にカットすることができることから「DIY」と名付けた。

そもそもカーペットは、購入機会やコンタクトポイントが小さいプロダクトである。新しい市場にアプローチすることで、潜在顧客をとりこめる可能性があると堀田さんは考えた。また、認知が拡大すると共に「カーペットを敷き込みたい」というお客様の問い合わせが増えたが、敷き込みには施工が必要で、地方など対応することができない案件が多かった。であるならば自分で施工をしてもらえる商品をつくろう、という発想から生まれたのがWOOLTILEなのだ。
好きなカラーや模様を並べて置くことで、自宅の子ども部屋や店舗の片隅などちょっとしたスペースでもカーペット生活を楽しむことができる。この商品も、カーペット導入のハードルを下げると同時に、カーペットへの関心を高める狙いがあった。

さらに、オリンピック需要が終わった後の対策として、2020年にECサイトもオープン。どん底の低迷期を経て、軽やかに前進し始めた堀田さんの前に立ちはだかったのは、新型コロナウイルスのパンデミックだった。
ホテル、ブティック、オフィス、展示場など主要なクライアントからの依頼がストップし、再びウィルトンの織機を止める日が来た。そのうえ、コロナのダメージで外注先の廃業が相次いだ。これはリーマンショックを超える危機的状況だったが、堀田さんは混乱のなかで次々と手を打っていった。
まず、入社時の28人から38人にまで増えていた社員には、「月給を保証する」と宣言。パート、アルバイトにも「これだけの給料は支払います」と約束した。リーマンショック時の苦い経験が、この判断につながった。

さらに、社内の製造技術を磨き、自社でできることを増やすため、外注先に頼んでいた仕事の内製化を進めた。例えば、カーペットの裏材にあたる「バッキング」を加工する作業も自社で手掛けるようになった。また、在庫管理のシステム、織機の中枢を担う「ジャガード」と呼ばれるコンピューターを入れ替えるなど、時間に余裕ができた時だからこそできる作業を進めた。

カーペットの未来を語るための決断
しかし、決して冷静沈着だったわけではない。2020年の売り上げは5億1000万円、2021年の売り上げは4億2000万円と激減。コロナの終息が見えないなかで、堀田さんは「僕たちがカーペットを作る意味ってなんなのか?」を自問し続けた。
「コロナになったら、誰もカーペットを買ってくれませんでした。その時、本当に俺たちカーペットだけやってて大丈夫なのかって思ったんですよ。でも、いわゆるスタートアップみたいに事業をピボットしたり新規事業を始めようにもアイデアがないし、そもそもそういうことがしたいという根本的なモチベーションがわいてこなかった。カーペットに関わること以外、やりたくなかったんです。そう自覚したうえで僕らはなにを未来に繋ぎたいのかを真剣に考えたら、ウィルトンカーペットのメーカーであることを諦めちゃいけないと思ったんですよ。それは個人的な思いだけじゃなくて、ウィルトンには商品としての競争力があるという確信がありました。その魅力が伝われば、まだまだ商品としてポテンシャルがあるんです」
ウィルトンのメーカーであり続ける。そのための最大の課題は、織機だった。すでにウィルトン織機を製造しているメーカーは国内に存在せず、堀田カーペットの織機のパーツが壊れた時には自分たちで修理したり、中古のパーツを手に入れて交換したりを繰り返してきたが、それも限界がある。堀田さんは10年先、20年先、もっと先を見据えて、「織機メーカー」になることを計画している。

「いま、うちには8台の織機があります。3年後にそのうちの1台を止めて、ばらします。その時にすべての部品を3Dスキャンして、図面化する予定です。1台を完全に止めても経営が成り立つように、タフテッドの商品も作ろうと考えています。おそらく初期投資は、織機が大きいので土地建物への投資が必要となり、5億円程度。織機としては2億から3億かかる試算です。織機を止めて解体する時点で3人必要なので、3人分の人件費も新たに抱えなきゃいけない。そのあたりも含めて本当に経営として成立するのかどうかを見極めています。カーペットの未来を語るためにも、実現させたいですね」

「作れない時代」にできること
まさに社運を賭けたプロジェクトと同時進行で進めてきたのが、冒頭で紹介した「TACTILE HOUSE OSAKA」だ。このホテルはもともと、「カーペットを体感できる場所」を作ろうと、2019年から構想されていた。そのため、当初の名称は「CARPETLIFE BASE(カーペットライフベース)」だった。それが、「日本の工芸建材を体感できる場所」に拡張されたのは、あるきっかけがあった。
「設計が始まった時、たくさんの建材メーカーやユニークな商品を知りました。そのなかには、『こんなに面白いのになんで世の中に知られてないんだ?』っていうものが山ほどあるんですよ。そのうちに、これらを『つなげる』ことをビジネスにできないかと考え始めたんですよね。」
そして堀田さんはこう続ける。
「当時、ご来社いただくお客様から『この壁はどこのメーカーのものですか? この椅子はどこのメーカーのものですか?』など、カーペット以外のご質問をいただくことがたくさんあって。お客様は『カーペットそのもの』を探しているわけではなく、『自分がつくりたい空間』に必要なものを探しているんだなということに気がついたんです。だから、『つなげる』ということも、カーペットを売っていくためには必要なんじゃないかと思ったんですよね」
これは儲かる! と閃いたわけではない。堀田さんは、他人ごとに思えなかったのだ。
「作れば売れた時代から、作るだけでは売れない時代になり、いまは設備の問題や人手不足で作れない時代に突入したと感じています。この作れない時代に、僕らのカーペットだけじゃなくて、工芸も含めたモノ作りの分野でなにかできることがあるんじゃないかと思いました」
その「なにか」のヒントになったのが、中川政七商店との仕事だった。中川政七商店によるコンサルティングを受けた期間は短かったが、この時に前会長の中川淳さんと良好な関係を築いた堀田さんは交流を深めた。そして2022年から2024年3月まで、ものづくりの知見と経験を中川さんに見染められた堀田さんは、逆に中川政七商店の商品開発のアドバイザーを務めるようになっていたのだ。
「日本の工芸を元気にする!」をビジョンに掲げる中川政七商店は、生活雑貨を中心にものづくりをしている。一方で、より大きなスケールのものづくり――インテリアや建材もまた、工芸を元気にする重要な選択肢だと考えていた。なぜなら大きいからこそ、魅力が伝わる素材や技術もあるからだ。ただ流通や顧客も雑貨とは全く異なる中で、どうやろうかと探しあぐねていたという。

商品開発アドバイスをする中で、堀田さんも同じような想いを感じたという。
「例えば和紙を文具にしたりするけど、和紙の本質的な魅力って光の透け方にあると思うんです。それを体感するためには、もっと大胆に使った方が絶対にいい。堀田カーペットでやりたかった“カーペットを体感できる場所”と、中川政七商店がやりたかった“工芸のものづくりのよる建材”。この想いを掛け合わせられないか、という話になりました」
話し合いの結果、堀田カーペットと中川政七商店で合弁会社「Tactile Material(タクタイルマテリアル)株式会社」を設立。新会社は製品の企画と開発を担当し、製造は外注する「建材のファブレスメーカー」となり、建材との出会いの場を創出する。そのデビューを飾るのが、「TACTILE HOUSE OSAKA」だ。

国産建材と家具の見本市
TACTILE HOUSE OSAKAの客室は、国産の建材と家具の見本市のようだった。
壁面の棚板や一部の柱の漆塗りは、福井の漆琳堂が担当。ウールを混ぜた和紙で作られた建具には、福井の滝製紙所の和紙が使用されている。ベッドは岐阜のメーカーwohlhutte、浴室やテラスのタイルは岐阜のエクシィズ、伊達冠石を使った洗面台は宮城県のメーカー大蔵山スタジオ、浴槽は奈良のメーカー日ポリ化工、個室の壁紙は京都の小嶋織物のものを採用した。ほかにも、そこかしこに厳選された建材と家具が配置されている。



ばらばらのメーカーのものなのに統一感があるデザインに仕上がったのは、建築やインテリアの設計を担当した建築家の工藤桃子さん、部屋全体のスタイリングを手掛けた大阪・福島のインテリアショップ「Essential Store」の店主・田上拓哉さんの手腕によるものだろう。

各メーカーを訪ね、ものづくりの現場を見てから採否を決めてきた堀田さんは、このホテルを完成させるために、1年かかりきりだったという。同じような施設をほかの地域につくることも想定しているそうだ。
ウィルトンのポテンシャルを信じ、織機メーカーへの道を模索しながら、埋もれた建材に光を当てるキュレーターへ。堀田さんの人生の第二章が、幕を開けた。
「ものづくりをしている仲間たちと伊勢神宮の式年遷宮会館に行ったとき、すごく勉強になったんです。伊勢神宮では約1300年前から20年に一度、社殿を新しく建て替え続けているんですよね。そのことによって技術が次世代にまで継承され、未来に残すための合理的な仕組みができているんです。もちろん、すべてを過去と同じように続けることは難しい。”なにを残し、なにを変えるのか?”を考え続けていると思うんですよね。未来に残る。それがどういうことなのか、僕も考え続けます」