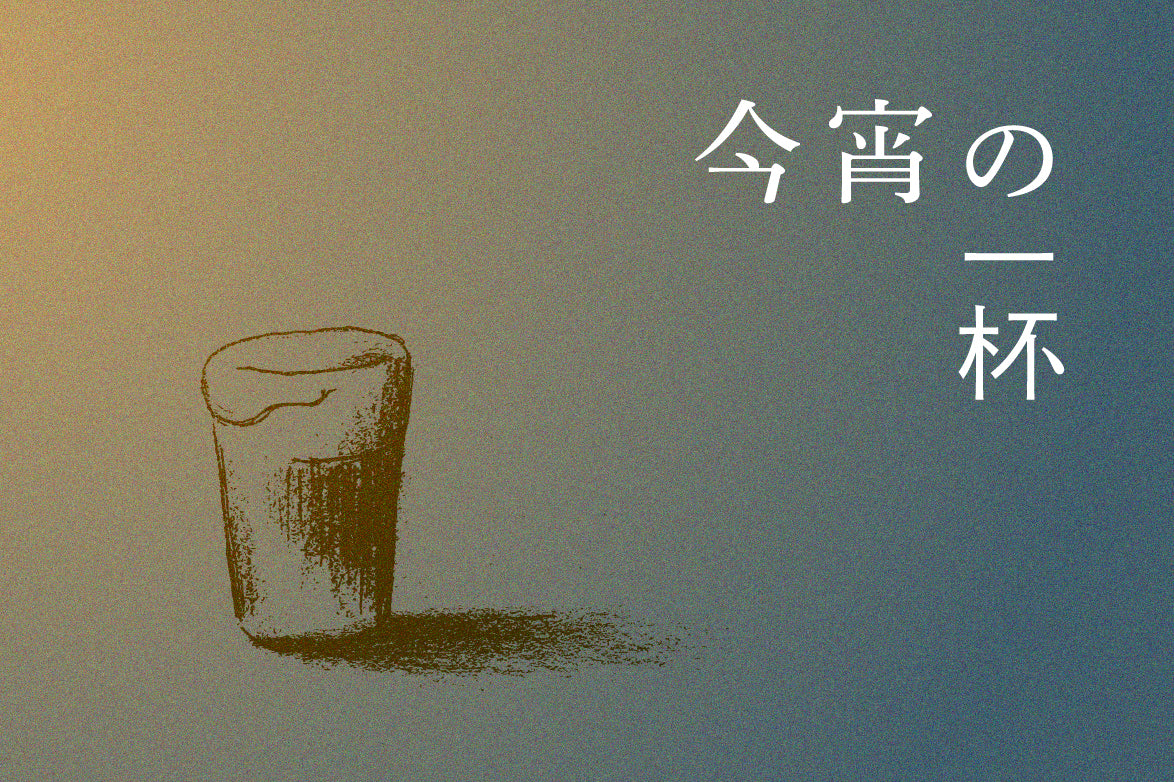昆布を、だし文化を、途絶えさせたくない。(こんぶ土居)
- 執筆:わざわざ編集部
- 撮影:若菜紘之
昆布に今、何が起きているのか

土居純一さん
大阪で広まった真昆布とだし文化

一番上が真昆布。この他、長昆布や細布昆布、ガゴメ昆布などがある
昆布は、日本近海に生息している海藻で、産地によって品種が分かれています。昆布の中でも、こんぶ土居が看板商品として取り扱っている「真昆布」は高級品。江戸時代の書物にも真昆布を指して「是を昆布の絶品とす」との記述があり、献上品に指定されてきた歴史があります。
江戸時代、大阪は「天下の台所」として栄え、北海道の産物が船で集まりました。品質の高い真昆布は大阪から他地域に流通することはほぼなく、大阪で消費されていく中で、かつお節との組み合わせで「だし」が誕生しました。
そして、だしを活用する調理方法は「だし文化」となり、広まっていったのです。
1908年、グルタミン酸の発見とうまみ調味料の普及

1908年、昆布にとって大きな転機が訪れます。東京帝国大学(現在の東京大学)の池田菊苗博士が昆布のうまみ成分「グルタミン酸」を発見したのです。翌年、グルタミン酸を活用したうま味調味料が発売され、家庭に普及していきました。家庭でだしを引く機会は減少し昆布の販売量も減り、その流れは今も続いています。
うま味調味料の発明によって、確かに「うま味」という観点だけなら昆布は無くてもよくなりました。ただ、昆布には「旨味」があると土居さんは言います。人間が感じる5つの味覚(甘味・塩味・酸味・苦味・うま味)のひとつがうま味であり、昆布が出せる「旨味」はうま味を含みつつ、もっと幅の広い、昆布だからこそのおいしさを指しています。

淡味真。本物の味とは、水や空気のようにただ淡泊な味のものであるという、こんぶ土居が大切にしている言葉です。
うま味が発見されていなかった時代は、素材の味を引き立ててくれる昆布の存在は画期的なものでした。現代では様々な味付けが可能なだけに「淡味真」の味わいを薄く感じる人もいるでしょう。
昆布を今の時代を生きる人たちが求める形に変えながら、本物の味を届け続けたい。その一心で、こんぶ土居はだし用の真昆布の他にも、だしパックや濃縮タイプのだしで家庭料理にだしを簡単に取り入れられるようにしたり、佃煮などの昆布加工品は伝統調味料だけを使用して作るなど、あの手この手で本物の味を用意し続けています。
獲れなくなった真昆布

実は、天然の真昆布は平成27年度から不作続きで危機的状況になっています。北海道大学の研究チームによると地球温暖化の影響で他の昆布も今後採れなくなる可能性もあり、生産現場でも昆布は危機に瀕しています。

昆布がふわっと香る熟成庫。昆布は採れてから1年寝かせておくと風味がグンと良くなるのだそう

川汲浜(かっくみはま)産の養殖真昆布。天然の真昆布は過去の収穫分を販売している

現在は養殖で真昆布の生産量を確保していますが、本当は2年かけて厚みのある昆布に育てたいところを1年で収穫してやりくりしていると言います。漁師の後継者不足もあり、悩みは尽きません。
ここ30年で現場が変わっていない感覚があり、イノベーションが必要だと感じている土居さん。産地に何度も足を運んだり、北海道の学生に昆布の話をする機会を設けたりと、手を尽くしています。2022年には、大阪のこんぶ土居の店舗の近くに昆布の歴史や食文化、そして現状を伝えるために「大阪昆布ミュージアム」を開業しました。

館内には数々の展示や資料、実際の道具などが並ぶ

4mを超えて育った、珍しい特大真昆布

こんぶ土居と大きく書かれた大漁旗は、三代目店主の引退に際して漁協から記念品として贈られたもの
昆布の生き字引として
ところで今、日本で和服を日常的に着て生活している人がどれほどいるでしょうか。ほとんどの人が洋服を着ていて和服文化から遠ざかっています。和服以外にも、一度作り手がいなくなった伝統工芸品は製品から製法を読み解くことは困難を極め、同じものは再現できないのだそうです。
文化は簡単に作れるものではない。一度無くしてしまったら、もう取り戻せないのです。

土居さんは、今自分にできることはだし文化を途絶えさせないことだと言います。こんぶ土居の昆布でなくていいから、昆布を使ってほしい。家庭でもだしで料理をしてほしいのだと、何度も繰り返していました。
昆布を守っていきたい思い、現状に都度適応するばかりで打開策や最適解が見つからない焦り、それでもだし文化を伝える存在であり続けたいという覚悟。現地との取り組みにも精を出し、昆布のために手を尽くすこんぶ土居に心を打たれました。

わざわざができることは、土居さんの思いと製品を多くの方に伝えることだと考えています。昆布でだしを引くのは何も難しいことはなく、一晩水につけておくやり方が一番簡単です。だしパックや水で割るだけの十倍だしを使うのでも十分です。スーパーに売っている昆布から始めてみてもいいですし、こんぶ土居の昆布ならば料理が間違いなく素晴らしい味わいに仕上がります。
文化を担うのは、今を生きる私たち。どうか昆布を料理に使っていただけたら嬉しいです。