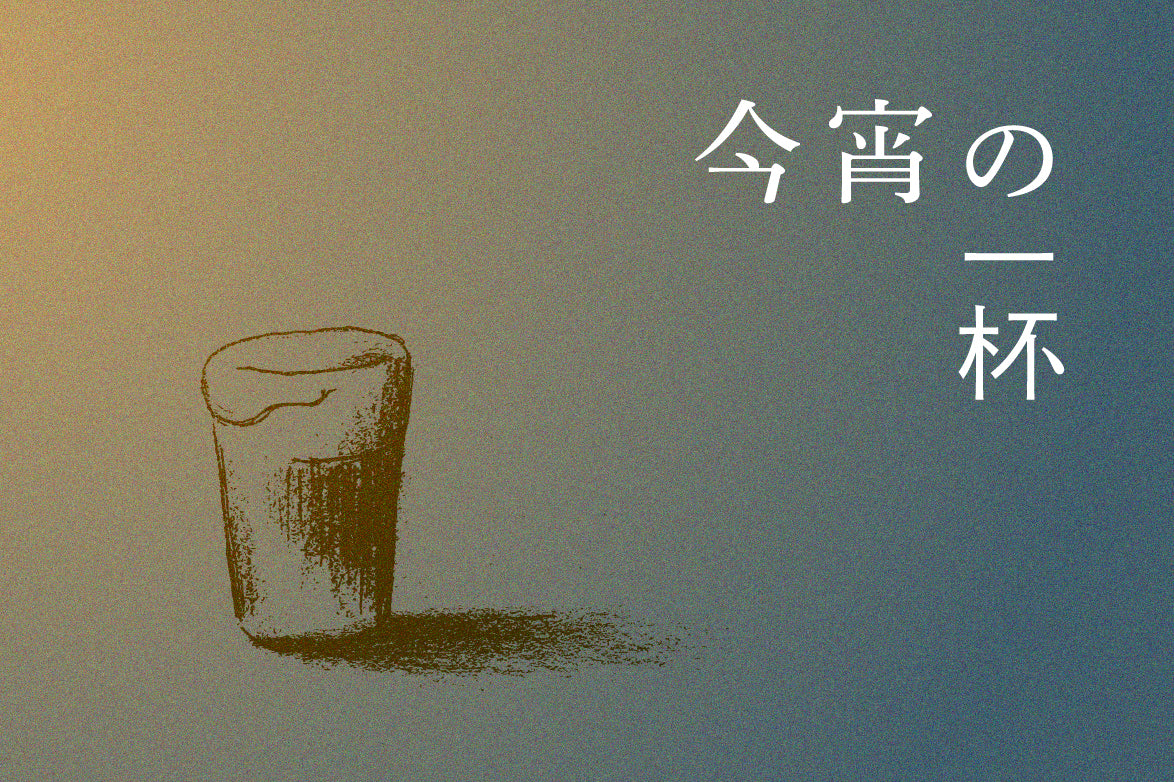目次
指先サイズの赤ちゃんウニ
「ほら、見てください」。
岩手県洋野町の水産ベンチャー「北三陸ファクトリー」を率いる下苧坪之典(したうつぼ・ゆきのり)さんは、水槽のなかに入れた手を広げた。

指先には、わずか数センチの小さなウニ。下苧坪さんによると生後半年ほどの「赤ちゃん」で、この日、北三陸ファクトリーの見学に訪れたメンバーからは、「かわいい!」と声が漏れた。

北三陸ファクトリーのすぐ隣にある「種市うに栽培漁業センター」で生まれた赤ちゃんウニは、生後1年経つと漁師の手によって沖合の海に放流される。そして2年後、洋野町の沿岸に広がる「うに牧場」に移す。
「うに牧場」については後述するが、天然のワカメや昆布が繁茂するように作られた世界唯一の漁場のこと。その場所で1年間過ごしたウニは実入りの良さが特徴で、濃厚なうま味を持つ。これに目をつけたのが、下苧坪さん。洋野町のウニをブランド化し、自力で一軒、一軒、卸先を開拓した。今では、数十軒に及ぶミシュラン星付きの名店で重宝されている。
新たなウニの市場を切り拓いた下苧坪さんはしかし、大きな危機感を抱いている。気候変動による海水温の上昇により、海藻の芽が出る春先に、ウニが活発に動くことで海藻を根こそぎ食い尽くす「磯焼け」が問題になっているのだ。海藻がなくなると海が砂漠化し、魚介類の生育に影響を及ぼすだけでなく、ウニの実入りが悪くなり、商品価値がなくなる。日本では「ウニ」というと高級でありがたいイメージがあるが、実は世界において、ウニは「海のペスト」と呼ばれるほど厄介者なのだ。
日本にとどまらず、地球規模に及んでいる磯焼けの被害を解決するために、下苧坪さんが考案したのは「ウニバースシステム(UNI-VERSE systems)」。ウニをさまざまな形で活用しながら海藻を再生するこのシステムで、世界の海を守ろうとしているのだ。
これは、ウニに懸けたひとりの起業家の物語。

本当は料理人になりたかった
下苧坪さんは1980年、岩手県洋野町で水産加工業を営む家の長男として生まれた。子どもの頃、地元はアワビ、ワカメ、イワシなどを扱う水産業で賑わい、景気が良かった。
しかし1990年代に入ると魚の輸入が増え、価格が低迷。洋野町の水産業も影響を受け、稼業も徐々に傾いた。
「調子が良かった頃は、仲間を呼んで、父が管理していたヨットでよくバーベキューをしていました。でも中学生の時に、そのヨットも手放してね。あ、これはもう水産業やるべきじゃないな、もう水産業じゃ食えないなっていうほど、一気に水産業が落ち込んでいきました」

父親から「英語は勉強しておいた方がいい」と言われ、商業高校の国際経済クラスに進んだものの、将来は中学生の頃から好きだった料理の道に進もうと考えていた。調理の専門学校ではなく大学に行くことにしたのは、担任から「とりあえず大学を出た方がいいんじゃないか」と言われて、「なんとなく」。
大学では、サーフィンと空手に明け暮れる日々。決してまじめな学生ではなかったが、20歳の時、友人を乗せて運転中に事故を起こしたのを機に気持ちを改め、英語の習得に力を入れた。アメリカのシアトルに短期留学したことが、世界に目を向ける最初のきっかけとなった。
「コミュニティカレッジだったんですけど、メキシコ、エクアドル、スペイン、台湾、フィリピン、韓国の学生がいて、本当に多様な環境でした。みんな考え方が違って面白いんですよ。当時、そういう人種のるつぼのなかで生きていくのが自分の性に合っているなと感じたし、こういう多様な人たちと仕事をしたいと思ったんです」

営業の才能が開花
帰国後、青年は通関士を目指した。空港や港で物品の輸出入を管理するプロフェッショナルになることで、「世界とつながることができる」と考えたからだ。しかし、試験は不合格。やむを得ず就職活動をして、大手自動車メーカーに入社した。ここで、営業の才能が開花する。青森の支店に営業企画として配属された22歳の下苧坪さんは、考えた。
――誰から買っても、同じ車が届く。それなら、「下苧坪から買いたい」と思ってもらうように営業するしかない。モノを売るのではなく、自分を売ろう――。
心掛けたのは、誠実であることと、お客さんの最大のメリットを追求すること。たとえば、農業や漁業に従事している人たちは、軽トラックを常用している。彼らの「傷みやサビが目立つ軽トラを新車に買い替えたい」というニーズを逃さず、下取り価格が少しでも高くなるよう会社と交渉した。当時、そこまでする営業マンは珍しく、お客さんに喜ばれ、セカンドカーを購入する際にも下苧坪さんに声がかかるようになった。
「自分を売る」戦略が功を奏し、2年目には全社でトップの成績をあげる。その営業力に目をつけたのが、大手生命保険会社だ。下苧坪さんが取り上げられた業界紙の記事を目にした同社の役員から、ヘッドハンティングを受けた。
生命保険の営業にいい印象を持っていなかった下苧坪さんは当初、オファーを受けるつもりではなかった。しかし、次第に「業界を変える」という同社のミッションに共感するようになり、2006年、26歳で保険会社に転職した。
基本給ゼロの成果報酬制。配属された支社でも「自分を売る」営業で駆け回り、一時は好成績を収めた。収入も跳ね上がったが、まだ遊びたい盛りだった下苧坪さんは高給をプライベートに注ぎ込み、次第に生活が乱れていった。当然、営業成績も下降し、「このままの生活を続けてちゃダメだ……」と悩んでいた2009年のある日、実家から電話があった。
父親がガンになったという報せだった。

曽祖父の写真を見て固めた決意
生命保険の営業マンとして行き詰っていた下苧坪さんは、母親から「戻ってくれば」と言われたこともあり、退職と帰郷を決意。すでに機能していなかった父親の会社を解散し、2010年5月、水産加工販売の「ひろの屋」を新たに立ち上げ、ワカメの販売を始めた。
大企業でバリバリ活躍する生活に未練はありませんでしたか? と尋ねると、下苧坪さんは首を横に振った。
「就職して洋野町を出てからも、いつかは地元で水産業をやるかもなと思っていたから。まったく抵抗はなかったですね」
だが、起業から1年も経たずに東日本大震災が発生。養殖のワカメがすべて流されるという危機のなか下苧坪さんを支えたのは、サーフィンと空手で鍛えた体力と持ち前の営業力。わずかに残った天然ワカメを漁師から買い取り、自分で茹で、塩漬けにして、都内近郊の催事などで販売した。多い日には売り上げが1日に40万円に達した。
こうしてひとりで行商を続けていた2012年のある日、祖父の自宅を片付けていたら、大量の干し鮑を前にした曽祖父と祖父、生産者が写った写真が出てきた。1937年に撮影されたその写真のなかで掲げられている看板には、「下苧坪乾鮑加工所」「香港」という文字が見える。

「この写真はなに?」。祖父に尋ねると、知らなかったエピソードを話してくれた。まだ飛行機が行き来していない時代、曽祖父は船で香港に渡って干し鮑を売り歩き、収益を持ち帰って生産者にキャッシュで気前よく支払いをしたという。
その話を聞いた時、下苧坪さんは胸のうちでボッと音を立てて火が灯るのを感じた。
「生産者や水産加工業者が、いい思いをしていた時代があるんだ。水産物で栄えてたこの地域を世界とつなげることで、もう一度、そういう時代を作りたい」
「北三陸ファクトリー」を設立
世界を見据えた下苧坪さんは、手掛かりを求めて動き始めた。東日本大震災で被害を受けた食産業の販路のマッチング、商品プロデュース、人材育成などを目的に設立された「一般社団法人 東の食の会」の活動も、そのひとつだ。
発起人のひとりで、外務省職員を経てマッキンゼーのコンサルタント、オイシックス(現オイシックス・ラ・大地)の役員であり、震災を機に復興支援に携わっていた高橋大就さんの「三陸のブランドを作ろう、リーダーを育成しよう」という呼びかけに賛同。地域の漁業者、生産者だけでなく、高橋さんの取り組みに協賛する大企業や団体とも活動を共にするようになった。
それがきっかけとなり、2013年11月、飲料メーカーのキリンが主導する「復興応援キリン絆プロジェクト」に採択され、2000万円の助成を得る。この資金を元手に2014年7月、「北三陸 世界ブランドプロジェクト実行委員会」を発足し、同年8月、ひろの屋のスピンアウトブランドとして「北三陸ファクトリー」が誕生した。

北三陸ファクトリーのブランドで世界に打って出ようと考えた下苧坪さんは、タコのオイル漬け、ミズダコの燻製、鮑のオイル煮など次々と商品化。これらを大都市の催事で販売することで、世界進出への足掛かりにしようと考えていた。
全国を訪ね、毎週のように催事の現場に立つ日々。しかし、なかなか思うようにヒット商品が出ず、地道に売っても給料は手取り20万円ほど。このジリ貧状態を抜け出すために洋野町の一番の特産品であるウニを扱いたいと思っていたが、そこには大きな壁が立ちはだかっていた。ウニで商売するためには、新規参入が難しい入札権と加工場が必要なのだ。
転機が訪れたのは、2015年。
「地元の給食センターが移転して、空いたんです。そもそも、加工場がなければ入札権を取らせてもらえません。旧給食センターをウニの加工場にすることができたら、入札権が取れるかもしれないと考えました」

問題は、工場の改修と入札権の取得に必要な資金。ひろの屋は下苧坪さんが「自転車操業だった」と認める事業規模で、自力では用意できない。
そこで2,500万円の資金を申し出たのが、三菱商事復興支援財団。これもまた、東の食の会での出会いが縁となった。
先人が作った「増殖溝」にキャッチ―な名前を
2016年、無事に入札権を獲得し、ウニの加工業に参入した下苧坪さんは、愕然とした。
以前ほどおいしくない……。
原因は、「磯焼け」。下苧坪さんが子どもの頃、海中にはワカメや昆布が大量に生えていて、かき分けるようにして泳いでいたという。ところが、冒頭に記したように温暖化で海水温が上昇し、ウニが活発化し、エサとなる海藻が激減してしまったのだ。エサ不足になるとウニの実入りが悪くなり、味も落ちる。
磯焼けの被害が三陸全体に広がるなかで唯一、豊富な海藻を保っていたのが現在の「うに牧場」と名付けられた場所だ。
洋野町の沿岸部には、約18キロにわたって岩盤がある。そのため、干潮になるとワカメや昆布が干上がってしまうという問題があった。1960年代、その岩盤にできた溝に海水が溜まり、枯れずに残った海藻があることに気づいた種市町(現洋野町)内の漁業協同組合が、数億円の事業費を投じて岩盤に溝を掘った。

「増殖溝」と呼ばれたそこには海藻が繁茂し、ウニを放つとパンパンに実が詰まった濃厚な味のウニに成長した。地域の悩みの種だった岩盤が、海藻とウニを育てる揺りかごになったのだ。その結果を目の当たりにした近隣のふたつの漁協も協力し、最終的に178本の溝が掘られた。
1986年、種市漁港そばに「岩手県北部栽培漁業センター」(現うに栽培漁業センター)が完成すると、より高品質なウニにするため、センターで稚ウニを1年育て、沖合で2年放流、最後の1年を増殖溝で過ごすというサイクルが完成した。
増殖溝のスペースは限られているため、放つウニの数にも上限がある。増殖溝を有する3つの漁協がウニと海藻の密度管理を徹底してきたことで、磯焼けの被害を避けることができた。
下苧坪さんは、先人の知恵によって誕生した絶品のウニに着目。これを世界ブランドにするために、「うに牧場」と命名した。周囲からは反発の声もあったが、押し切った。
「うに牧場って聞くと、養殖の意味に聞こえるじゃないですか。生産者からは、天然モノなんだから牧場っていうのはやめろと言われました。でも、お客様には“増殖溝”という名前だと絶対に伝わらないですよ。それでどうしようかと思った時に、これはウニを放し飼いする酪農だと閃き、キャッチーな名前として“うに牧場”と名付けました」
これまでにない手応え
2016年、ひろの屋は洋野町のうに牧場で採れたウニの販売を始めた。最初は世間の反応は薄く、さっぱり売れなかった。それもそうだろう。「うに牧場」という言葉は下苧坪さんが考えたもので、誰も知らないのだ。
ここからまた、怒涛の営業が始まる。ある時は深夜1時に起き、2時の開店に合わせて築地市場に出向いた。チラシを作り、市場にいる仲卸に配る。その際中、市場の関係者からいきなりラリアットを食らったこともあった。忙しい市場のなか、いかにもよそ者の下苧坪さんが邪魔だったのだろう。名のある料理店で食事をして、そのたびに「一度、サンプルで使ってください」と頭を下げた。これまで通り、百貨店の催事にも出展した。やっていることはウニを扱う前とほとんど変わらなかったが、手応えが違った。
「すべては、先人たちが守ってきた圧倒的な品質のおかげです。ウニはキラーコンテンツなので、一度食べてもらった後、うに牧場の説明をして、生きた状態でここに送りますと言うと、だいたい取り引きが決まりました」

今現在北三陸ファクトリーがウニを卸している飲食店には、17年連続ミシュラン二つ星の「紀尾井町 福田家」、2010年の銀座出店からミシュラン三ツ星を12年連続で獲得した「鮨よしたけ」などそうそうたる名店が名を連ねる。もともと10軒程度だった取引先がウニのおかげで約200軒に達し、売り上げも一気に伸びた。
「今、うちの工場では最盛期になると40人ぐらいの地元の女性が働いています。彼女たちがいきいきと働ける場を作るというのが、三菱商事復興支援財団との約束でした。地元で5万円、10万円稼げたら、孫にお小遣いをあげますよね。そうやって地域経済が潤っていくんです」

確立するまでに 6年を要した革新的技術
下苧坪さんがウニの営業と同時に手をつけたのは、磯焼けを防ぐための研究だ。北三陸でも「うに牧場」以外の地域ではウニと海藻の管理に手が及んでおらず、このままでは北三陸のウニ漁が先細りになると直感した下苧坪さんは、知り合いの縁をたどってウニの養殖技術の研究をしている北海道大学の浦和寛准教授と出会い、2017年より共同研究を進めてきた。
ふたりが目指したのは、増えすぎて実入りの悪くなった「磯焼けウニ」の養殖。「磯焼けウニ」は収穫しても売り物にならず、産業廃棄物として1個あたり5円をかけて捨てられている。
もし、人間の手によって「磯焼けウニ」の品質を改善することができれば、海のなかで繁殖し続けているウニを大量に確保することで、海藻を守ることにもつながる。これまで誰も手をつけてこなかったこの技術の開発に挑んだのは、海と地域を守るためだ。
「海藻をエサにする岩手県産蝦夷あわびの水揚げ量は、1950年の2000トンから、2022年には119トンと、この70年で約20分の1に減りました。ということは、生産者の収入も20分の1になっているということですよね。地域の人口が減ったから水産業ができなくなるのではなくて、資源の枯渇こそ地域の人が減る原因なんです。この問題を先送りしたら、自分たちも生産者の未来もダメになってしまう。だから、海藻を取り戻すことをライフワークにしようと決めました」
「磯焼けウニ」の養殖は、簡単にはいかなかった。1年経ち、2年経ち、4年経ち、5年が経ってもいい結果が出ない。
それでも諦めずに研究を続けていたら6年目の2022年、ついに養殖技術が確立した。実入りの悪いウニをまとめてかごに入れ、北海道大学と日清丸紅とで共同開発した海藻の搾りかすなどの残渣から作ったエサを2カ月間与えると目に見えて実の量が増加し、天然モノと遜色ない味を持つことが分かったのだ。
この養殖ウニを市場に出すと、1つ500円の値が付いた。それまで1個あたり5円の廃棄料が必要だった磯焼けウニが、2カ月の養殖によって100倍の価値を持つ。特許を取得したこの革新的な技術が、「ウニバースシステム(UNI-VERSE systems)」のカギを握る。

海と地域を劇的に改善するポテンシャル
2022年11月、下苧坪さんはオーストラリアのタスマニアにいた。
「海水温が低くないと、昆布は生えません。世界的に温暖化が進み、海水温が低いエリアがどんどん狭くなっているなかで、タスマニアは日本の東北、北海道エリアと海水温が近いんです。オーストラリアの海も磯焼けの被害が拡大しているのですが、海水温が低ければ、ちゃんと管理をすることで海藻が戻ってくることがわかっています」
日本は、ウニの生産量で世界5位。チリ、ロシア、オーストラリア、中国が上位につけている。下苧坪さんは、そのなかでもビジネスがしやすく、海水温が近いオーストラリアに着目した。

オーストラリアのウニは生産量こそ世界3位だが、磯焼けによって中身が乏しい。生産量に数えられていない低品質のものもいれると、ウニの数は日本の数千倍に達する。そのウニを日本の技術で養殖することで、高い価値を持つウニに生まれ変わらせようというわけだ。
11月にフィージビリティー・スタディー(事業化調査)を実施して実現の手応えを得た下苧坪さんは2023年4月、現地法人「KSFオーストラリア」を設立。現地企業とジョイントベンチャーを組み、2024年の秋からウニの養殖を始め、世界の市場に向けて輸出に動き出す。
さらに現在、北海道大学と開発中の技術をオーストラリアで導入する計画もある。
「ウニの殻には、リん、鉄、マグネシウムといった海藻の成長を促す栄養素が豊富に含まれています。この殻を砕き、ある接着剤となる成分と混ぜ合わせて堆肥ブロックを作り、海藻の種を植え付けて海中に戻すことで海藻を再生させます。ウニがたくさんいると食べられてしまうので、先にウニを取ってきて養殖するところから始まるのです」
海のなかから「磯焼けうに」をごっそり回収する。そのウニを養殖して、高く売れば漁師の収入が増え、地域が活性化する。「磯焼けうに」をきれいに取り尽くしたところに堆肥ブロックを置く。海藻が再生すれば、魚が戻ってくるだけでなく、ウニやアワビの生育も促される。
海の磯焼け問題を解決する、世界初の画期的なうにの再生養殖システム──それこそが「ウニバースシステム(UNI-VERSE systems)」なのだ。ウニバースシステムは、海と地域を劇的に改善するポテンシャルを持っている。

「すごく不味い」ウニの意外な使い道
下苧坪さんの壮大なチャレンジは、さらなる広がりを見せる。オーストラリアには、数種類のウニがいる。食用に適しているもの、、そうでないもの……。下苧坪さんいわく、デカいウニは「すごく不味い」。実は、使い道がなく膨大な数が放置されているこのガンガゼにこそ、とてつもない商機があるという。
「僕たちは、ガンガゼをサプリメントにしようと考えているのです。北海道大学の調査によって、ウニは水産物のなかでも葉酸が最も多く含まれ、ビタミンAも豊富だという結果が出ています。どちらも妊活、妊娠中に必要な栄養素として知られます。ゴールドマンサックスのレポートによると、妊活、妊娠中に必要な栄養素を補うサプリは世界で7憶ドルの市場規模があります。今出回っている葉酸サプリは、ケミカルなものしかありません。ウニという天然の海洋資源から作る葉酸とビタミンAを含むサプリが、大きなビジネスになる可能性を秘めているのです」

下苧坪さん率いる北三陸ファクトリーにも、提携するオーストラリアの企業にも、サプリメントを作る資金もノウハウもない。しかし、現地の大学や研究機関との連携により、これから研究を始めて2年後には形にしたいと意気込む。
ウニの養殖やサプリの開発には時間がかかるため、水産物の流通も始める。サステイナブルな漁法の国際的な認証「MSC」を取得し、タスマニア島に工場を持つ水産物加工会社を買収して、新会社「タスマニアシーフード」を設立。この会社を通して牡蠣、イワシ、サーモン、ホタテなどをグローバルに売り込んでゆく。
下苧坪さんの取り組みはオーストラリアでも注目されており、2023年8月にはオーストラリアの経済紙「オーストラリア・ファイナンシャル・レビュー」で大きく特集されている。
生き残りをかけた最後の挑戦
北三陸ファクトリーが、オーストラリアでの養殖うにやサプリ、ほかの水産物の販売を軌道に乗せれば、事業規模も見違える。2032年の売り上げ予想は、200億円。下苧坪さんはその年、IPO(株式上場)も見据えている。
そこから、もうひとつの勝負が始まる。日本の漁業は古くからの既得権益が根強く残っており、現時点ではベンチャー企業がウニの養殖をするなど新しいチャレンジをしやすい環境ではない。そこで、下苧坪さんはこれからの10年、日本の事業は従業員の雇用を守りながらも、大きな成長を求めないことに決めた。その間、オーストラリアでサステナブルな水産業のノウハウと資力を蓄え、10年後、それらを日本に持ち込んで、三陸の水産業を豊かなものにするというのがプランだ。
「長期的な視野に立った漁獲量の管理という当たり前のことを当たり前にやってこなかったから、海に魚がいなくなってしまった。今からでも、それをちゃんとやろうと思っています。まずは世界でサステナブルな漁業の在り方を証明して、日本でも次の世代にバトンタッチできるような水産業を作っていく。これは、地域の生き残りをかけた最後の挑戦です」
一世一代の勝負に打って出る下苧坪さんの口調は穏やかだ。
社会人になってからずっと、最前線で闘ってきたという思いがある。車や生命保険の販売も、水産加工物やウニの営業も、行政との交渉やほかの企業との連携も、誰かに頼ることなくひとりで担ってきた。その重圧で精神的に追い詰められ、従業員を怒鳴り散らしてしまったり、夜、眠れないこともあったという。
しかし今、下苧坪さんの周囲には国境を越えて同じ志を持った仲間たちが集う。「これからの10年、思い切りやるだけです」。そう語る下苧坪さんの視線の先には、北三陸の海がある。
「30年前、僕が遊んでいた頃の海に戻したいんです。あの時と同じぐらいに海藻が戻れば、次の世代も余裕でメシを食べていけますから」