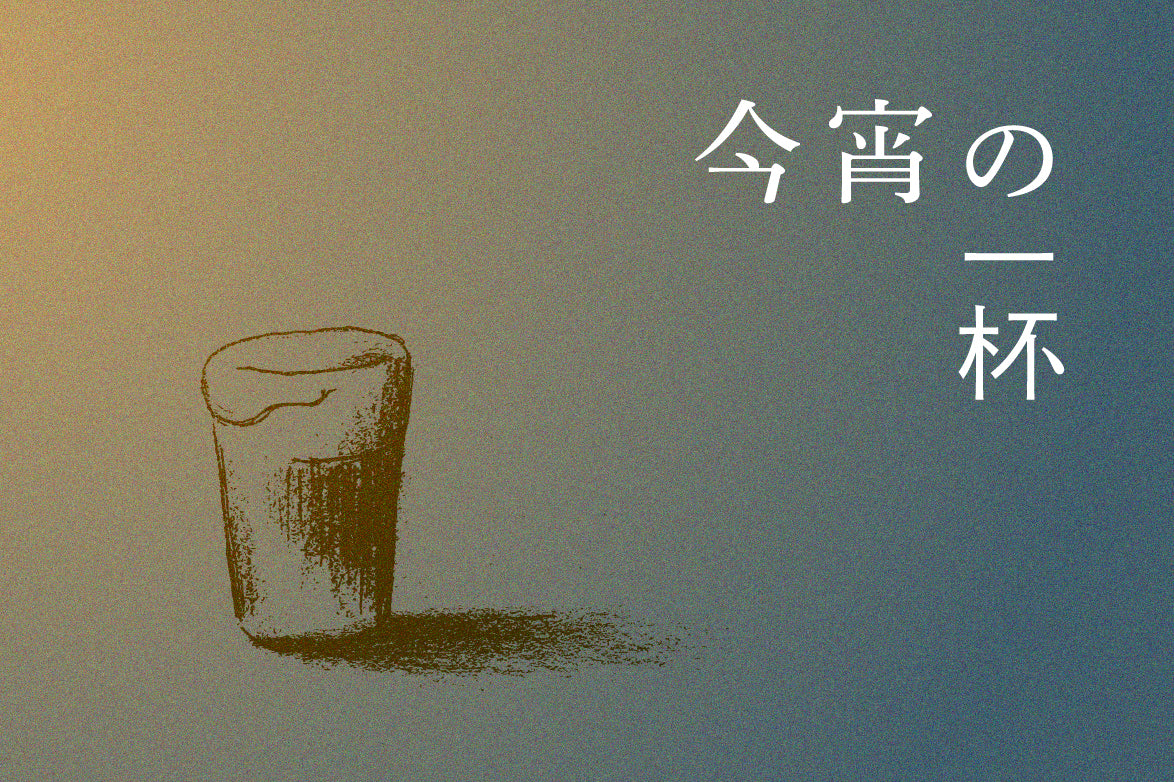目次
諏訪には「ぐるぐる」の輪が広がっている

長野県諏訪市で、古材や建具、古道具を回収し、販売しているリビルディングセンタージャパン(以下、リビセン)。取材で訪ねた1月某日、リビセンにはいつもと違う風景が広がっていた。
カフェが入っている1階では、普段扱われていない揚げたてのナゲットを頬張る人や、アツアツのお汁粉を口に運んでいる人がいる。古道具や建具が販売されている2階の一角には、センスのいい日用品や張子作家の作品などが並べられ、「おもちゃの病院」と名付けられたブースには、続々と親子連れが訪れていた。白衣を着たドクターの手によって壊れたおもちゃが動き始めると、小さな男の子は目を大きく開けて、笑みを浮かべていた。

「おもちゃのお医者さん」には、壊れてしまった大切なおもちゃが運び込まれる
その日、開催されていたのは「ぐるぐるバザール」。前年の秋に次いで2回目で、長野県内、東京、富山などから10社が出展していた。「ぐるぐるバザール」の「ぐるぐる」は、循環を意味する。来場者から紙袋や緩衝材、水筒やタンブラーなど家庭で不要になったものを集めてリビセンでリユースしようと企画されたもので、町の人に足を運んでもらうのが目的だ。

リビセンがある諏訪の町に目を向けると、別の「ぐるぐる」が始まっている。どこもリビセンから徒歩2、3分の距離にあるパン屋さん、花屋さん、カフェ、古本屋さんなど計10軒のお店は、リビセンが空き家のリノベーションを担った。ここ数年の間に続々と新規オープンしていて、その数はまだ増える予定だという。

もともと沖縄で古書店を営まれていた「言事堂(ことことどう)」。店主の方がたまたまインスタでリビセンの投稿を見つけ、連絡をくれたのだという

リビセンから目と鼻の先にあるフラワーショップ「olde(オルデ)」。店内は、東野夫妻とオーナーさんのセンスが光る
リビセンでは、解体される建物から古材や建具、古道具を引き取ることを「レスキュー」と呼ぶ。2016年9月にリビセンがオープンしてから、レスキューに出向いた軒数、約2700回。捨てられるはずだったモノを救い出し、それを使って近隣の空き家に新たな命を吹き込むのもまた、リビセンが目指す循環の形なのだ。
リビセンは、ぐるぐるしながらどこを目指しているのだろう? 代表の東野唯史さんと、取締役として東野さんを支えるパートナーの東野華南子さんの歩みから、振り返る。

(左)東野華南子さん(右)東野唯史さん
唯史さんの人生を変えた最初の授業
1984年に大阪で生まれた東野さんは、小学校5年生から高校生まで福岡で過ごした。父は会社員、母は専業主婦で、「クリエティブやデザインとは縁のない、普通の家庭でした」。理系の科目が得意だった東野さんは、大学進学の時、「消去法」で建築を選んだ。
「やりたくないことを消していったら、建築が残りました。安藤忠雄の名前を聞いたことがあるかな、程度でしたね。構造とか設備はつまらなそう、意匠がやりたいと思ったのと、親に迷惑をかけないように国公立大学にしようと、名古屋市立大学芸術工学部を受験しました」

大学に入学したばかりの2003年4月、当時、グッドデザイン賞審査委員長を務めていた川崎和男さんの講義に出席した。その時に聞いた言葉が、東野さんの原点になる。
「最初の授業で、社会課題を解決して世のなかを良くするためにデザインがあること、分野が違うものを橋渡しするのがデザインの力だということを話していました。この教えがあるから、今があると思っています」
芸術工学部には、建築のほか、グラフィックデザイン、プロダクトデザイン、映像制作を学ぶ同級生もいた。1学年に60人しかいないので、「みんな友だち」。その環境で学ぶうちに、「建築、グラフィック、映像を一体でやっている会社がいい」と思うようになり、卒業後は主に空間デザインを手掛けるベンチャーに入社した。
「ベンチャーなら早いうちから経験をつめるだろう」という目論見通り、2年目には小さな案件を任されるようになった。毎月150時間を超える残業があったが、「30歳までに独立したい。そのために短期間でスキルアップしなければ」と思っていたから、前向きに、どん欲に働いた。

ウガンダの孤児院で感じた「弱さ」
早々にその成果が現れ、3年目にはコンペの勝率が7割に。「普通は3、4割勝てればいいほう」というから、異例の強さだ。しかし、「もっと成長したい」という欲求と同時に、「この仕事は世のなかを良くしているか?」と疑問に感じた東野さんは会社を休職して、世界一周の旅に出た。2010年、26歳の時だった。
「発展途上国に住む人びとが直面する、さまざまな課題を解決してきたデザインを紹介する展覧会『Design for the Other 90%』で、Qドラムというドーナツ型のポリタンクを知りました。それに水を入れて転がすことで、子どもでも50キロの水を運べるようになるんです。このタンクは、水がない環境があるという課題を知らないと実現できないデザインですよね。デザインで世界をよくするんだったら、まず、どんな社会課題があるのかを知らないといけないと思いました。普通の環境で育った自分は、日本人的な価値観で固められいてたと思うんですよ。それを1回なくしたかったし、なるべく触れ合ったことのない場所に行けば、成長できるかなと」
10カ月間で、約40カ国を巡った。それは、見たことのない景色に心を躍らせるだけでなく、自分が持っていないモノに気づかされる旅になった。


例えば、ウガンダの孤児院を訪ねた時に実感したのは、自分の「弱さ」。なにか課題を見つけたとしても、それまでの東野さんのようにキーノートでプレゼン資料を作り、CADで図面を描いてプレゼンすることに長けた勝率7割のデザイナーは、役に立たない。なぜなら、そこには必要な機材がなにもないから。現地で「ギターを弾いて歌える人のほうが、よっぽど喜ばれる」と感じた東野さんは、孤児院でこう思った。
「どこに行っても、デザイナーとしてその場所で誰かに貢献できる人になりたい」
帰国後すぐ休職していた会社を退職し、独立。フリーランスのデザイナーとして数多くの仕事を請けながらも、以前と同じ熱量で向き合えなくなっていた東野さんが、旅で得た感覚を思い出したのは、2012年。
旅の途中で知り合った友人がゲストハウスを作ることになり、そのデザインを請け負った。そのゲストハウス「Nui. HOSTEL & BAR LOUNGE」の施工は、それまで経験したことのないものだった。全国から大工さんが集まり、それぞれのスキルとその場のアイデアを活かす。施主の友だちも助っ人に現れて、自分にできる作業をする。

Nui. 施工時の様子
ひとつの建物をみんなでワイワイ作り上げるスタイルは、東野さんに「こういう作り方もあるのか」と新たな視点をもたらすと同時に、ウガンダで感じた弱さを克服するきっかけになった。DIYのスキルがあれば、デザイナーもその場で手を動かして貢献できると肌で感じたのだ。
夫婦の出会いはツイッター
この時の様子を間近で見ていたのが、パートナーの華南子さん。1986年生まれ、北京、上海、ロンドン、東京で育った華南子さんもまた、ユニークな道のりを歩んできた。

中学生の時、ロンドンの現地校に通っていた華南子さんは、クラスメイトの英語についていけず、学校をさぼって学校の隣りにあるスターバックスコーヒーに足を運ぶようになった。そこで自習をしていたら、休憩時間になったスタバの従業員が入れ代わり立ち代わり英語を教えてくれるようになった。その気遣いへの感謝と、なによりもその時間が楽しかったことから前向きな気持ちになり、華南子さんは再び学校に通い始めた。
16歳で日本に帰国した後、「自分も誰かの背中を押せる人になれたらいいな」とスタバでアルバイトを始めた。竹を割ったようなまっすぐな性格の華南子さんは、「雇ってもらうなら、貢献しないと!」と、ホームページに掲載されている哲学や理念を学ぶのはもちろん、出版されているスタバ関連の書籍をすべて読み込んだ。
その熱量のまま、大学を卒業したらスタバに就職したいと思っていたのに、面接であえなく落選。カフェの仕事に愛着があったこともあり、2009年春、別の大手チェーンのコーヒーショップで働き始めた。
華南子さんはそこでも真剣に仕事と向き合い、休みの日ごとに違うカフェに出向いては、なにかフィードバックできることはないかと分析していた。2011年には、「コーヒーに携わっているのだから、コーヒーの産地についても勉強しなきゃ」と、ボリビア、ペルー旅行を計画する。
陸路で国境を越えるにはどうしたらいいのかを調べていた時に出てきたのが、東野さんが世界一周中に書いていたブログ。華南子さんは東野さんをツイッターで発見し、連絡を取った。
その後、無事に旅を終えたふたりは、なんと偶然出会うことに。場所はゲストハウス「toco.」のバーラウンジ。そこで意気投合し、間もなくして付き合い始めた。

当時の東野さんと華南子さん
大手コーヒーチェーンの社員から、ゲストハウス女将へ転身
父親が新聞記者で、海外を転々として育った華南子さんは、「普通の人」に強い憧れがあった。一般企業に就職し、真っ当に会社員をして、いずれ専業主婦になるという「普通の道」を思い描いていた彼女にとって、フリーランスの東野さんは異質の存在だった。しかし、「デザインの力で世の中を良くしたい」という彼の思いに共感する。そしてそれは、「自分はどう生きるのか?」という問いにつながった。
「私は、お父さんから仕事は楽しくやるもの、社会を良くするためにやるものだと教わりました。私もそう思って働いていたけど、東日本大震災が起きた時、イチ社員としてなにもできなかった。このまま会社員を続けても、世界を良くできる気がしないって思っていたんです」
この頃、東野さんを通して「toco.」のメンバーとも親しくなった華南子さんは、ゲストハウスのポテンシャルに目覚める。ゲストハウスには、国籍も人種も仕事も関係なく、さまざまな背景を持った人たちがやってくる。旅人たちと会話を重ねることで、もし希望を失っている人がいたとしても、「また違う道で生きていけるんじゃないか」と提案できるような気がしたそうだ。
思い立ったら、一直線。2012年3月にタリーズを退職した華南子さんは「toco.」に転職した。それからは東野さんと一緒に暮らしながら、ゲストハウスの女将としてフル回転する日々。
それぞれの仕事に励んでいたふたりは2014年に結婚し、それを機に「medicala(メヂカラ)」という名のユニットを結成する。その理由について、華南子さんが苦笑しながら明かしてくれた。
「職場での意見の違いがきっかけに、私が仕事を辞めることになったんです。東野さんは、その時に私の肩を持ってくれました。この恩は必ず返さなくてはいけないと思っていたら、職場の同僚が長野県の下諏訪町で古民家を改装して“マスヤゲストハウス”というゲストハウスを開くことになって、東野さんに声がかかりました。私もなにかできることがあるかもしれないと思って、手伝い始めたのがスタートです」

華南子さんの開花した意外な才能
夫婦で携わる最初のプロジェクトとなった「マスヤゲストハウス」で、東野さんは「Nui.」と同じく、現場に泊まり込み、施主やその仲間たちと一緒に作り上げる体制で臨んだ。
マスヤゲストハウスは、築100年を超える古民家を利用している。予算を抑えつつ味のある仕上がりにするため、もともと使われていた古材をできる限り活用した。3カ月に及ぶ施工期間中、華南子さんは自分に驚いていた。大手チェーンカフェで多数のアルバイトに仕事を割り振り、管理してきた店舗運営のスキルを、施工現場で発揮したのだ。

諏訪にある「マスヤゲストハウス」
「私はなにもできないって思ってたけど、意外なことに人をマネジメントする才能が開花しました(笑)」
いつも穏やかで冷静な東野さんは、「でしゃばるな」とくぎを刺すこともなく、現場で誰よりもテキパキと指示を出す華南子さんを見守った。
「華南子は、建築の知識はぜんぜんないんですよ。でも行動は早い。こっちが指示するより先にやっているから、僕が口を出す暇もない(笑)。助かりました」

マスヤゲストハウスを作っていた2014年には、「空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)」が制定された。これは所有者に代わり、自治体が「行政代執行」によって空き家を壊すことができる法律だ。当時から、放置された空き家の扱いは日本全国で課題になっていた。
アメリカからの輸入古材がたくさん使われているのに、日本の古材はたくさん捨てられていることに疑問を感じ、「空き家の古材がもっとリユースされ、その文化がもっと国内に広がれば良いのに」と考えるようになった東野さん。
しかし、日本の古材屋さんは車でしかアクセスできない場所にあったり、BtoBがメインで一般の人が購入したり手に取ることが難しかったり、そもそも情報が少ないなどの現状があった。
どうしたものかと考えていた2015年、ふたりは新婚旅行でアメリカのポートランドに向かった。そこで、現地のNPOが運営する「リビルディングセンター」と出会う。

ポートランドのリビルディングセンター
いいお店の条件とは?
1998年に設立されたリビルディングセンターは、約4000平米という広大な建物のなかで数万点に及ぶ廃材や中古品が売られている。約40名のスタッフとおよそ3000人のボランティアスタッフで運営されているのも特徴だ。ここを訪ねた時、東野さんと華南子さんは目から鱗が落ちる思いがしたという。
「僕らはいつも、いいお店ってなんだろう、いい空間ってなんだろうと考えながら店作りをしてきました。リビルディングセンターに行く前までは、店主の個性が立っていて、店主が現場にいる空間がいい空間だろうと思っていたんですよ。だから、フランチャイズのお店になると店長の色が薄まってしまう。でも、リビルディングセンターはあの巨大なサイズでいいお店でした。それはどういうことなんだろうと考えたら、働き手に愛される空間だったんです」
華南子さんが、言葉をつなぐ。
「お会計に行った時に、長い棒の先に筆をつけて高いところにロゴを描いている人がいました。それ、やる必要あんのかなと思ったんですけど、でもきっとやりたいんですよね。スタッフ自ら『やりたい』と思うことがある、もうそれって愛じゃないですか。ポートランドではほかのサルベージショップも行ったけど、その愛があるからこそ、リビルディングセンターは圧倒的に居心地がよかったんですよ」

町なかにあり、便利で、お客さんが多く、働き手に愛されていているリビルディングセンターを見て、「こういう店が日本にほしい」と思った東野さん。帰国後、その哲学や思想を受け継ぐ古材屋を開く決意を固める。
2015年の年末、問い合わせフォームから「リビルディングセンターを日本に作りたいから、名前とロゴを使わせて欲しい」とメールを送ると、拍子抜けするほどあっさりと「OK」の返事がきた。
のれん分けの許可を得たら、次は物件だ。マスヤゲストハウスのプロジェクト以来、諏訪エリアが気に入り、下諏訪に拠点を構えていたふたりは、知り合いに「こういうことやりたいんだけど、物件ないかな?」と尋ねた。すると、すぐに「あるよ」と返事があり、3日後には内見に行った。
それが、今のリビセンが入っている1000平米3階建てのビル。とんとん拍子に契約が決まり、リフォームをするためにクラウドファンディングを始めると、447人から500万円以上もの資金が集まった。さらに、リフォームの「お助け隊」を募ったところ、のべ460人の応募があった。
怒涛の勢いですべてが進んでいき、2016年9月、構想からわずか10カ月でオープンにこぎつける。東野さんは「自分の意志だけじゃない力を感じましたね」とほほ笑んだ。

「お節介を焼ける状況」にしておく
それから7年半、試行錯誤を重ねながらふたりはリビセンを育ててきた。華南子さんは、現在のふたりの役割について、「リビセンと社会を繋げるのが東野さんの仕事で、リビセンとスタッフ、お客さんを繋げるのが私の仕事」と話す。リビセンのスタッフをまとめるうえで、華南子さんの役に立ったのはスタバでの経験だった。

「スタバは学びたいとか知りたいと思った時、必要な情報にすぐにアクセスできるよう設計されているんです。社会人になって、働きやすい環境を作るって学びやすい環境を作ることなんだと気づいたので、そこは意識していますね」
華南子さんによると、リビセンのスタッフの多くは、社会になにかしら貢献したいという思いを持っている。その思いの実現に100%の力を注げるように、わかりやすい情報発信や、気持ちよく働ける環境を整えることに注力する。バックオフィスの業務にシステムを入れて効率化し、ムダをなくすのもその一環だ。

リビセンがリノベーションを手掛けた近隣の店舗も、放っておかない。「設計させてもらったからには、みんなが成り立つようサポートしたい」と、各店舗の紹介が載る「リビセンマップ」を作成。さらに、人手が足りないとなればリビセンのSNSで求人情報を発信する。
「それぞれのお店の売り上げもなんとなく知っていますよ。設計する時に事業計画書も出してもらっているから、最近、売り上げどう? って聞くと、みんな教えてくれるんです。それで、ちょっと売り上げが減っているなと思ったら、そこでお買い物をしたり、SNSにアップしたり。こうやって自分がお節介を焼ける状況、常に周りが見えている状態にしておきたいないんですよね。今、それができているのは、スタッフのおかげです」

創業100年以上の老舗のパン屋「太養パン」も、リビセンが内装を手がけた。老舗から新店まで、街に必要とされていることがわかる

徒歩圏内にあるコーヒーショップ「AMBIRD」。
お客さんの接点づくりで華南子さんが目指すのは、「健やかな循環」。冒頭に記した「ぐるぐるバザール」がわかりやすいだろう。加えて、2023年6月から始めたのは「ぶらぶらタンブラー」。これは、リビセンのカフェを含む飲食店でドリンクをテイクアウトする際、使い捨て容器ではなく、リビセンが回収したタンブラーを使用する仕組み。購入した人はタンブラーを持ち歩き、飲み終わったら「ぶらぶらタンブラー」に加盟する近隣の4店舗で返却できる。この仕組みによってゴミが減るだけでなく、お客さんが協力店に足を運ぶきっかけにもなっている。

リビセンの枠を超えて
一方、東野さんは、リビセンの枠を越えて「健やかな循環」を拡大しようとしている。
「僕は今、リビセンの事業を外向きに広げるものと、地域を深掘りするものとふたつに分けて考えています。外向けには、昨年秋に始めた『リビセンみたいなおみせやるぞスクール』とオンラインコミュニティです。地域の深掘りは、諏訪のエリアリノベーションを進めていきます」
2023年10月に開校した「リビセンみたいなおみせやるぞスクール」では、古材や古道具のレスキュー方法や掃除方法、管理方法、店頭へ出すまでのフロー、地域とのつながりの作り方などリビセンのノウハウを惜しみなく伝える。ただし、リビセンのコピーを作るのが目的ではない。地域や土地の特性、やりたいと手を挙げた人たちの個性と得意を活かす方法を探り、実現あるいは持続可能な事業プランを生み出すのが目的だ。

このスクールを終えた後、同じ志を持つ受講生同士が互いにフォローしあえるように、華南子さんが中心となってオンラインコミュニティを作った。情報交換、そして助け合いやコラボレーションの場として連携していくという。
スクールやコミュニティによって全国でレスキューを加速させながら、東野さんは「諏訪のまちづくり」に本腰を入れる。
東野さんは2022年11月、諏訪信用金庫、サンケイ(不動産)と共同出資で、すわエリアリノベーション社を立ち上げ、代表に就いた。いま、改めて諏訪に着目しているのは、明確な理由がある。
「今まですごい労力をかけていろいろなお店を作ってきたのに、僕らはそのお店に通えないんですよ、遠いから。そこに気づいた時に、なるべく諏訪でエネルギーを使ったほうが、僕らも楽しく過ごせると思ったんですよね(笑)」
信金や地域の不動産会社と手を組み、すわエリアリノベーション社というひとつの会社にすることで空き物件の情報が入りやすくなったり、借りやすくなるメリットがある。同社が最初に手掛け、2023年10月に竣工した物件が、長屋をリノベーションした複合施設「ポータリー」。1階には店舗、2階には事務所が入る。ほかに進行中の新しいプロジェクトもあり、諏訪の空き家活用はますます加速するだろう。そこに古材を使うことで、リビセンとの相乗効果も生まれる。

店舗と事務所の複合施設「ポータリー」。
東野さんは、さらにその先も見据えている。
「空き家や地域の古材が資源として活用されて新しいお店になる。そのお店を巡る装置としてぶらぶらタンブラーがあったり、地域の住民とお店を結ぶぐるぐるバザールという形が見えると、リビセンがある町はこんな景色になるというモデルになると思うんです」

DIY精神とリビルド
東野さんが思い描くのは、スクールやコミュニティを通してリビセンの哲学に触れ、「諏訪みたいな町がうちにもほしい」という人が増えること。空き家と古材を使うリノベーション、お客さんや住人と店を結ぶぶらぶらタンブラーやぐるぐるバザールというハードとソフト両面を備えたリビセンモデルを横展開することで、より持続可能で「健やかな循環」を全国に浸透させようという狙いがある。
「社会の仕組みを良くしたり、自分たちが楽しく暮らすためには、発想の転換とか工夫次第でどうにかなるというのが、DIY精神だと思います。諏訪に来るとそういうヒントがたくさん得られると思われるようになったら楽しいですね」


大きな計画を進める東野さんを見守る華南子さんの想いは、ゲストハウスで働き始めた頃と変わらない。テーマは「リビルド」だ。
「私は、リビルドという言葉が本当に好きなですよ。壊れちゃったらもう直せない、捨てるしかないっていうんじゃなくって、自分にもどうにかできるんじゃないかと思える心強さを持って帰ってもらえる場所にしたいんです。自分の価値観がひとつ変われば、見える世界が変わるかもしれない。自分の人生だってリビルドできると思っているから、その欠片でも届けられたらいいなと思います」