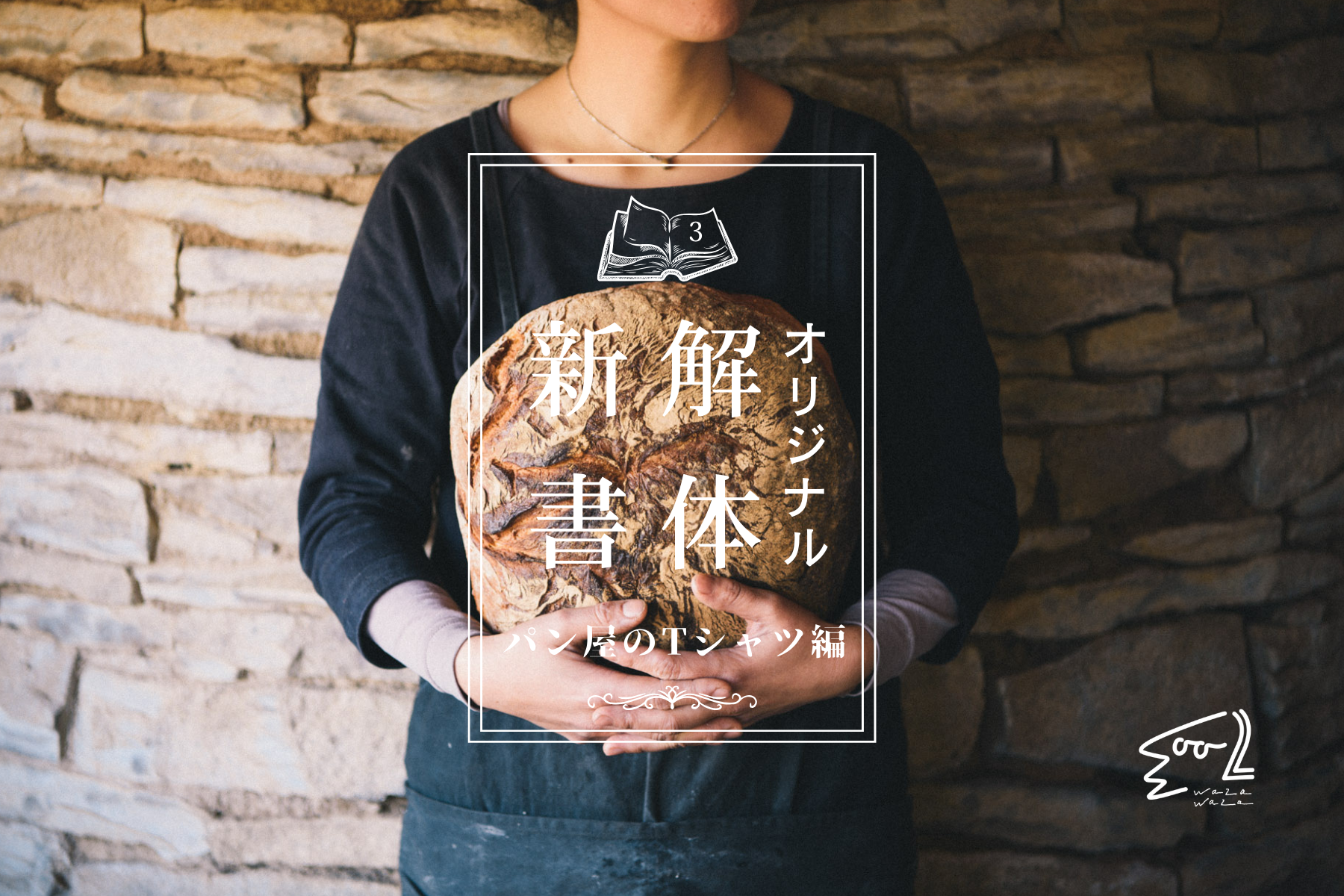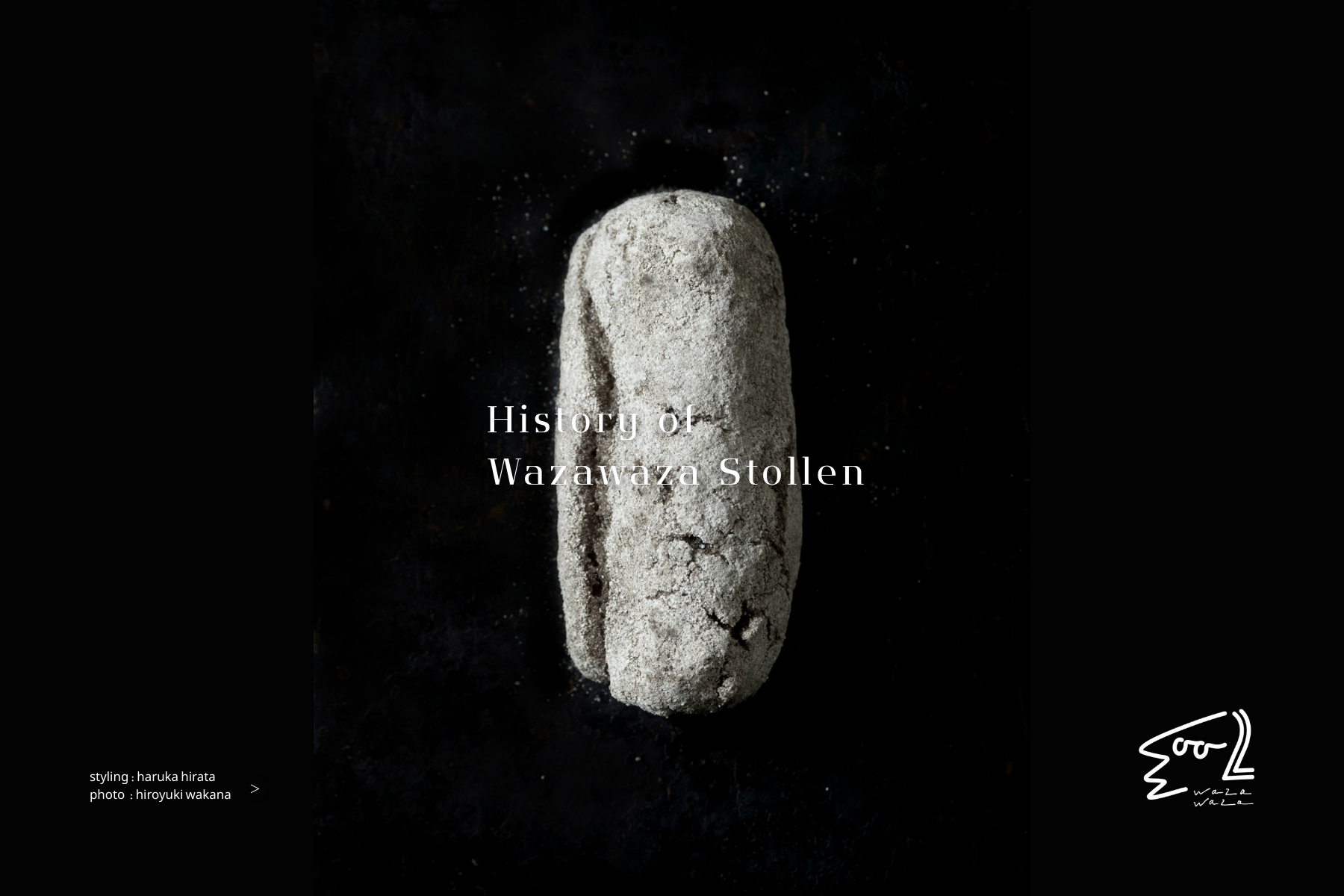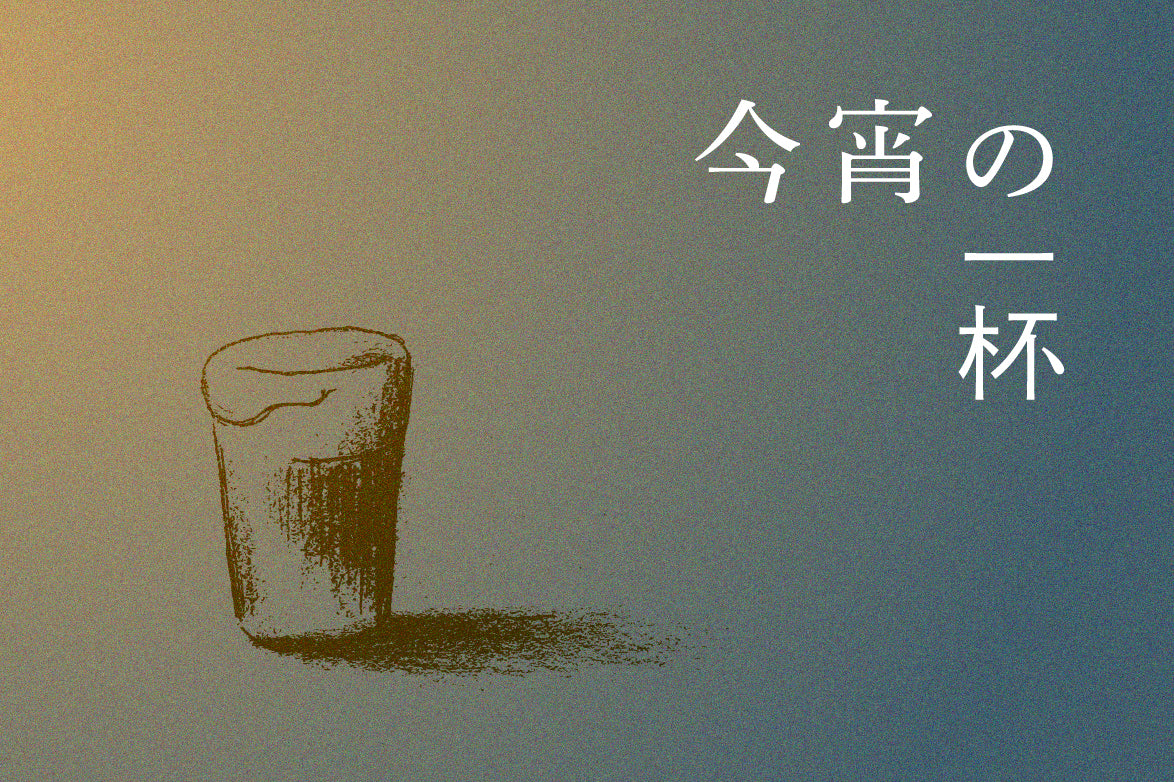オリジナル解体新書/1.残糸靴下編
- 執筆:平田はる香
- 撮影:若菜紘之
残糸靴下が生まれたきっかけ

残糸靴下は2017年に販売を開始した、わざわざのオリジナル商品だ。きっかけは、同じく2012年から湯たんぽみたいなウール靴下を製造している長野県の靴下工場の株式会社タイコー(以下、タイコー)に、足しげく通っていたことだった。
パンを作るみたいな気持ちでオリジナル商品を作ろうと思ったのは、2012年のこと。寒く長い冬の長野県に移住してきて、一番困ったのが足元の冷えだった。それが解消できるようにと作ったのが「湯たんぽみたいなウール靴下」だ。初めて工場と一緒に作ったオリジナル製品は気がかりだったし、お客様から製品に対してのお声をいただく毎にタイコーに通い、どのように改良するか検討していた。そうやって、温かくも丈夫な靴下が完成する頃には、すっかりタイコーの皆さんと仲良くなっていた。

ある時「平田さん、工場に余った糸が沢山あるんですが、どうにかなりませんかね?」とタイコーの神田さんに軽く相談されたのだが、私には工場に糸が余る仕組みがわからなかった。発注された分の靴下を納品するための糸を購入するのだから、余らないのでは?と思ったのだった。
どうしても糸が余る生産背景
「どうして糸が余るのですか?」と聞いてみると、
「例えばなんですが、メーカーから靴下の注文が1万足きたとします。生産過程で全ての靴下が良品で作れるとは限らないので、ロス率を計算しておおよそ1万1千足の糸を発注したとします。そして、靴下が完成した時に、予定したロスが全くなく生産できたとすると、1千足の糸が余るということになります。糸を発注するにもリードタイムがありますので、何かあった時のためにも靴下分ピッタリの糸を発注するということはできません。厳密には必ず、残糸(ざんし)が出るのです。」

そして、あらゆるメーカーから発注依頼がきて、納品してということを繰り返していくと、残糸がどんどん溜まっていく。タイコーの倉庫はいつしか余り糸で圧迫されていった。買った糸を捨てるのはもったいない、いつか使えるはずととっておく。だが、市場はいつも新しいものを求めており新しい糸が開発されていく。残糸は殆ど使われることなく倉庫に眠っていったのだ。
倉庫をみせてもらうと、当時は余り糸だけを保管するために倉庫を借りている状況で、残糸は色々な面でタイコーを圧迫していた。由々しき問題だなと思った。それから、何とか残糸を使ったヒット商品をわざわざで企画して糸を使いきれないか?と考える日々が続いたのだった。

量も糸も様々な残り糸たち
商品のデザインとは問題を解決すること

所謂デザインはしていない。だが思想はデザインされている
【条件】
・糸の組成、太さ、色、量はバラバラであり、同じものを量産することはほぼできないが、中には大量に余っているものもある。
・バラバラの糸だが、同じ商品として売らなければ、様々なコストや手間がかかってしまう。
・タイコーさんの在庫管理はしっかりしており、残糸の棚卸しはできており、何がどれだけ余っているかはわかる。
・倉庫はすでに一杯で、すぐにでも消費しなければ廃棄処分。火急な状況である。
上記のことを踏まえながら、商品を開発することは、不謹慎だが面白いとも思った。それは、パンに似ているなと思ったから。パンも余れば捨てるしかない。だからパンを開発する時に最初に考えたのは、捨てないパンの売り方だった。一番おいしいパンを作って売るということより大切なのは、人様が汗水垂らして作った小麦粉を直接ゴミ箱に投げ入れるような販売をしないこと。ものは大切にしなければならないのだ。
商品の開発で一番意識したことは、今起こっている問題を解決するデザインであること。デザインとは物の形を作る仕事ではなく、双方に利益が生まれるよい循環を作ることなのだな。と、この仕事を通して考えたのだった。パンの時も作っている人の健康について考えたけど、今回は工場の健康も考えないといけない。

【やろうと思ったこと】
・デザインはしない。どんな色や糸がきても、簡単に編める模様のない平編みベース
・いつでも生産できるように年中できるだけ空いている機械で編むこと
・細かく残量の糸を使えるように一足で2色入れるバイカラー
・残糸を消費したいので、沢山売るためには2足組
・でもこの値段でこの品質ならば最高だねという丈夫さを持っている

どのようにしてこの靴下が生まれるのかもわかりやすくパッケージに
上記を踏まえタイコーと協議をしながら、生産の仕組みを作っていった。タイコーの残糸の棚卸し状況をわざわざでも見られるようにして、わざわざの残糸靴下の在庫が切れる時間を予測して、オーダーをかけていく。二人三脚で生産から販売を行っていった結果、2tあった残糸は4年できれいになくなったのだ!
残糸靴下が売れてくると、タイコーさんの元にこれと同じような靴下を作りたいという話が、様々なメーカーからきたと聞いた。タイコーさんは「平田さんのところとじゃないと、この取り組みはできない」と断ったそうだ。他社の倉庫の在庫を調整しながら靴下を作るなど、わざわざでないとやれないと痛感していたと言う。それはそれは、嬉しい言葉だった。やっていてよかったと感じた言葉だった。
実際のところ、残糸がなくなってからは、タイコーに残糸が出た時だけ生産する商品になってしまった。わざわざにとっても人気商品だったので、お客様のご要望も多く、嬉しくも苦しい胸の内だったが、2025年に奈良の靴下工場と出会い、現在協業がスタートしたところだ。これから販売していく残糸靴下は奈良県産のものが含まれていくことになる。今後、奈良県の糸工場とも協議を進めており、ゆくゆくは日本の糸在庫がわざわざの残糸靴下に生まれ変わっていくことがあったら、素敵なことだと思っている。

全ての世代が履けるように設計された2cm刻みのサイズ展開
さて、実際の私はというと。
現在の私の靴下ボックスの中身はこれだ。ほぼ履くのは自社の靴下になった。一年を通して最も履いているのが残糸靴下。服によってリネン靴下を選んで履く。スポーツをする時はリネンアンクルソックスが絶対で、他の靴下は全く履いていない。寒くなるとウール靴下の出番が増えて、また春になると残糸靴下とリネン靴下に戻ってくる。

平田の自宅靴下ボックスは残糸ソックスや自社製品でいっぱい
子ども達も残糸靴下を愛用している。動き盛りの小学生はこれ以外の靴下だとすぐ穴が開くから、残糸靴下が絶対にいいと言っている。タイコーは、スポーツ系のメーカーの靴下の製造を手がけることが多く、残糸も必然的に殆どがスポーツやアウトドア系の抗菌で耐久性の強い糸が多い。その恩恵を受けて、残糸靴下の糸は強いものが多い。また、タイコーはそういったスポーツ・アウトドア系の靴下を作ってきた経験の中から、穴が開きにくい、足にフィットするなどという作り方が得意である。

実は子ども用サイズのパッケージは平仮名で子どもが読める仕様になっている
ということを散々言って販売してきた私も、すっかり残糸靴下のファンである。新しいカラーリングが入ると未だにときめいてしまい、買ってしまう。ちなみに糸の組み合わせは残糸の量を確認して、色や素材の糸帳を見て、全て私が組んでいる。こんな組み合わせは自分では履かないけど、〇〇さんなら好きそうだとお客様の顔を思い出したり、自分がこれは履きたい!と組むこともある。
糸を合わせながら微妙なカラーリングや見たことのない配色を心がけたり、やりがいも感じている。一時期、ここに工数がかかるということで、組み合わせルールを作り、工場で自動的に編んでもらうことを試みたことがある。結果、難しかった。色の組み合わせを職人にさせることは負荷を与えてしまうことにもなるし、売れ筋から遠かったカラーリングになってしまうリスクもある。良いことは一つもないねという事で私の専任となったのだ。
そうやってできた靴下が店に納品されると、試行錯誤して作った組み合わせが実際にどうなっているか気になって必ず見に行く。そして、一番に「かわいい〜」などと言いながらテンションが上がって、買うのが楽しみの一つなのだ。