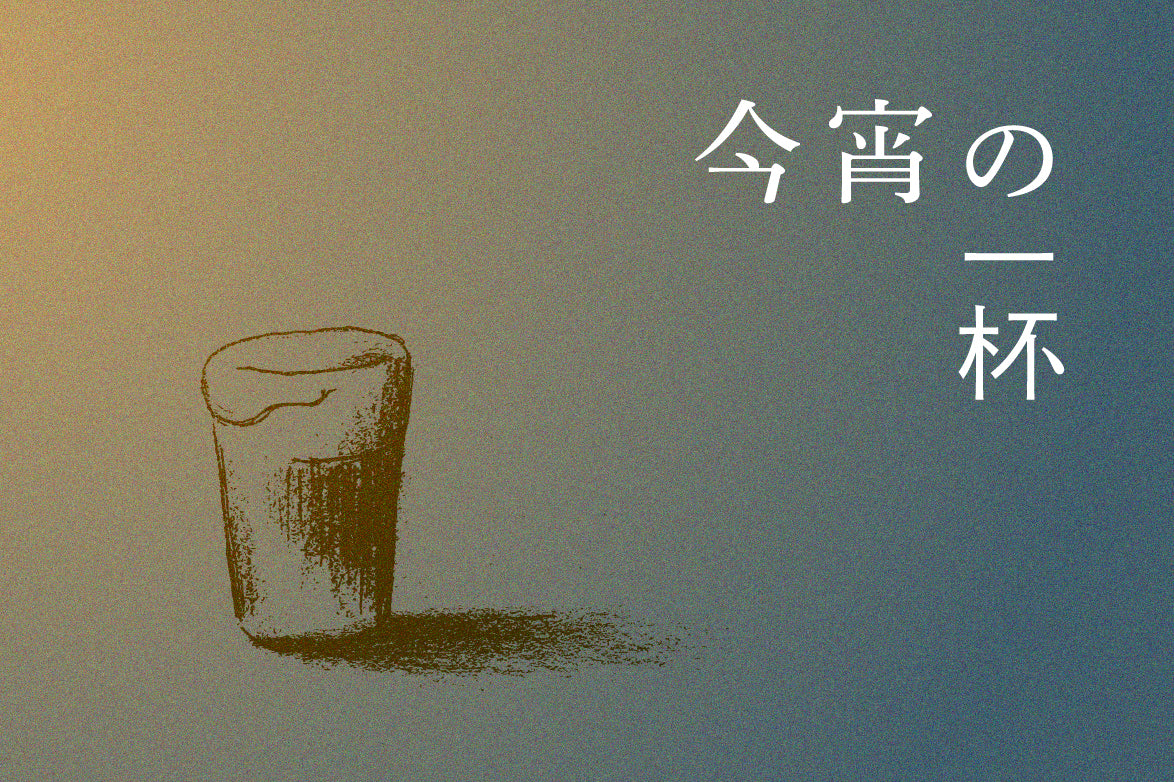今夜はひとりごはん。
仕事柄、出張や旅が多く、旅先でひとりという機会はよくある。が、今暮らす岡山の街でソロの夜は珍しい。どうしよう。自由と慣れてなさとで、そわそわする。いくつもの選択肢が手のひらでむくむくと、膨らむ。映画に行く?サウナ?いや、でもお腹減ったぞ。
2011年、息子が赤ん坊の頃移住してきた岡山市では、基本的に家族3人、または家族ぐるみのともだちと食卓を囲んできた。とても楽しい日々。そんな中、ひとりの夜は何度あっただろうか。片手で足りるくらいだ。
幼かった息子が中学生になり、わたしたち夫婦の仕事量も増えた。夫婦それぞれの出張や仕事が重なってしまう日は、息子はひとりでなんとかできるようになった。作り置きを温め直して食べたり、自分で簡単なものを作ったり、たまに友人とファミレスに行ったり。
もともと「3人の個人が共に暮らしている」という雰囲気の我が家だけど、さらにその色彩が濃くなってきた。
だが、こうやってわたしが夜にひとりで家で過ごすケースはまれなこと。遠い昔、独身時代を思い出す。こういう時わたしはどうしていたのだっけ。おそらく誰かを誘って飲みに行ったりしていたな。エネルギーが余っていて、外に繰り出していた。ひとり静かに食事を作るという選択肢はなかった。
でも、今日のわたしは家にいたい。あたたかいものを食べ、おいしいお酒をすこしだけ飲もう。今夜はそれだ!
料理を作ることはすき。誰かのためだと腕まくり。でも、じぶんだけのためとなると、つい簡単なメニューになってしまう。料理というレベルではない。たとえばひとりのランチは、ごはんと納豆とキムチだけ、とか。ひどい時は豆乳を温め黒酢を垂らして豆ジャン風、なんてことも。食べることよりやりたいことが目の前にあってつい、ミニマルな組み立てになる。
土井善晴先生の著書『一汁一菜という提案』が多くの人を救ったのは数年前のこと。 食事は栄養バランスを考え、たくさんの小皿を作らなきゃ。そんなひとびとの義務感を随分と楽にしてくれた印象がある。わたしも「義務感」とまでは思っていなかったけど、簡単な食事に対する一種の罪悪感のようなものはあった。「わたし、納豆ご飯なんだよね」って自虐的に笑うときなど、特に。専業主婦の母が三食作ってくれた景色と無意識に比較していたのかもしれない。
でも、いいじゃないか。堂々と簡単でおいしいものをささっと準備して食べようじゃないか。ちかごろはそう思っている。
今夜はわたしがわたしを簡素にもてなすのだ。
そして一杯だけじぶんのためにお酒を入れよう。
ごはんを炊き、具だくさんの味噌汁を合わせ、漬物を添える。以上。なんとシンプルなのだ。土井先生、すばらしい提案をありがとう。わたしなりにちょっとだけ丁寧に準備してみることにする。そう、他のタスクに気を散らしながらなんとなく作るごはんは、おざなりな味がして、満足感も低いから。集中だ。
実は近頃、米炊きについて学んだ。友人の料理家のアトリエで習った米炊きのメソッド。これが素晴らしかった。適切に洗い、浸水させ、炊く。技術の有無にかかわらず、誰でも美味しく炊ける。詳細はここでは省くが、簡単なのに目から鱗の仕込み方だった。今夜はその米を愛でることにする。たのしみ!
しっかり浸水させた仕込み済みの米は既に冷蔵庫に眠っている。これを炊く。火加減、時間が命だから、タイマー片手に真剣そのものである。沸騰する鍋の音に耳を澄ます。
その合間に簡単な味噌汁も作る。出汁はパックでいい。冷蔵庫にある野菜を刻み、わかめを入れる。具沢山の味噌汁って多幸感が立ち上る。
漬物がないから大根を浅漬けに。薄切りにして塩で揉み、胡麻油と塩昆布をまぶしただけ。たいした手間ではないが、昆布のうまみに満たされる。しっかりスキンケアをした時と似ている満足感だ。わたしだけが知っている、まさに自己満足。そう、今夜はこういうことがしたかった。自己満の夜、最高。
炊きあがり、蒸らした米はつやつやと輝き、水分を含んでぱんとふくらんでいた。うやうやしくそっとお櫃に移す。しまいこんでいたお櫃を、この炊き方を始め、復活させた。だって、お櫃に移すにふさわしい高貴さなのだ。余分な水分を吸ってくれるため、さらに美味しく食べられる。口に甘みが広がる。
じぶんのためだけに米を炊き、じぶんのためにお櫃に入れる。たかがそれだけだが、特別なかんじがしてわくわくする。
今夜はさっと寝て、明日朝早くから活動したくなってきた。酒は控え、冷蔵庫に寝かせていたノンアルコールのビールにする。急な路線変更だが、誰に断る必要もない。わたしによるわたしのための米とノンアルである。とくとくと注いだ黄金色の液体がひかる。米も発光し、味噌汁は香り、浅漬けがリズムを整える。

キャンドルとか灯しちゃおう。こんな夜にはレコードプレイヤーがほしい。近々買おう。最初に買うレコードは何にしようかな。たのしくて妄想が止まらない。ノンアルなのに酔ってきたような。窓の外の白い月が、とてもきれいだ。
すべては永遠じゃない。いつかひとりで暮らす日だって訪れるかもしれない。その予行演習のような夜。その頃、わたしはひとりをどれだけ楽しめるか。ひとりを楽しめるじぶんで、他者と関わりたい。
もうすぐ息子と夫が帰ってきたら、ソロの夜は終わりを告げる。だいすきな彼らにわたしはこの晩餐を冒険譚みたいに話すだろう。わたしがわたしのために米を炊き、飲みたいものを、飲んだ。今日はその記念すべき初日だったんだよ、と。