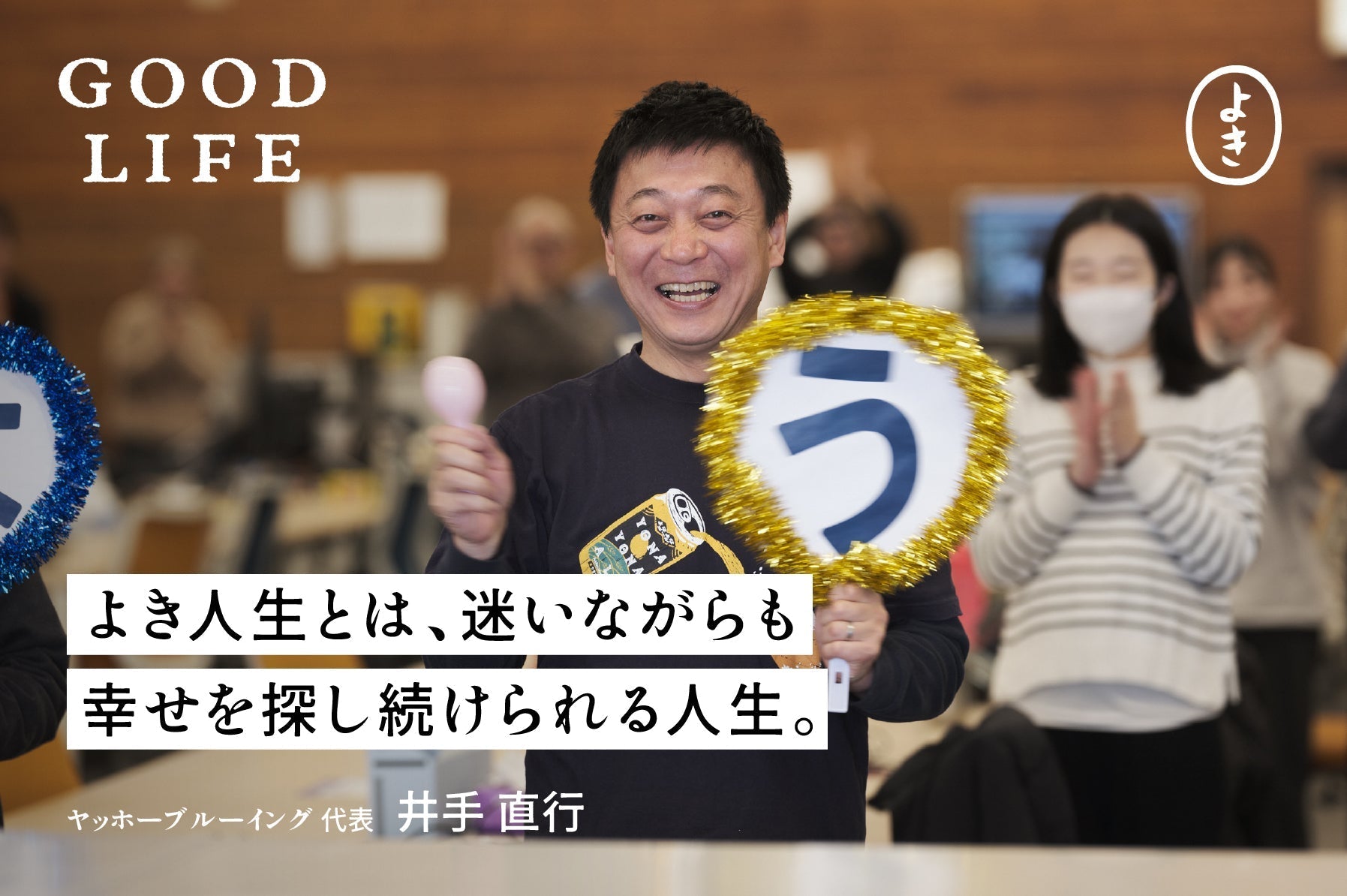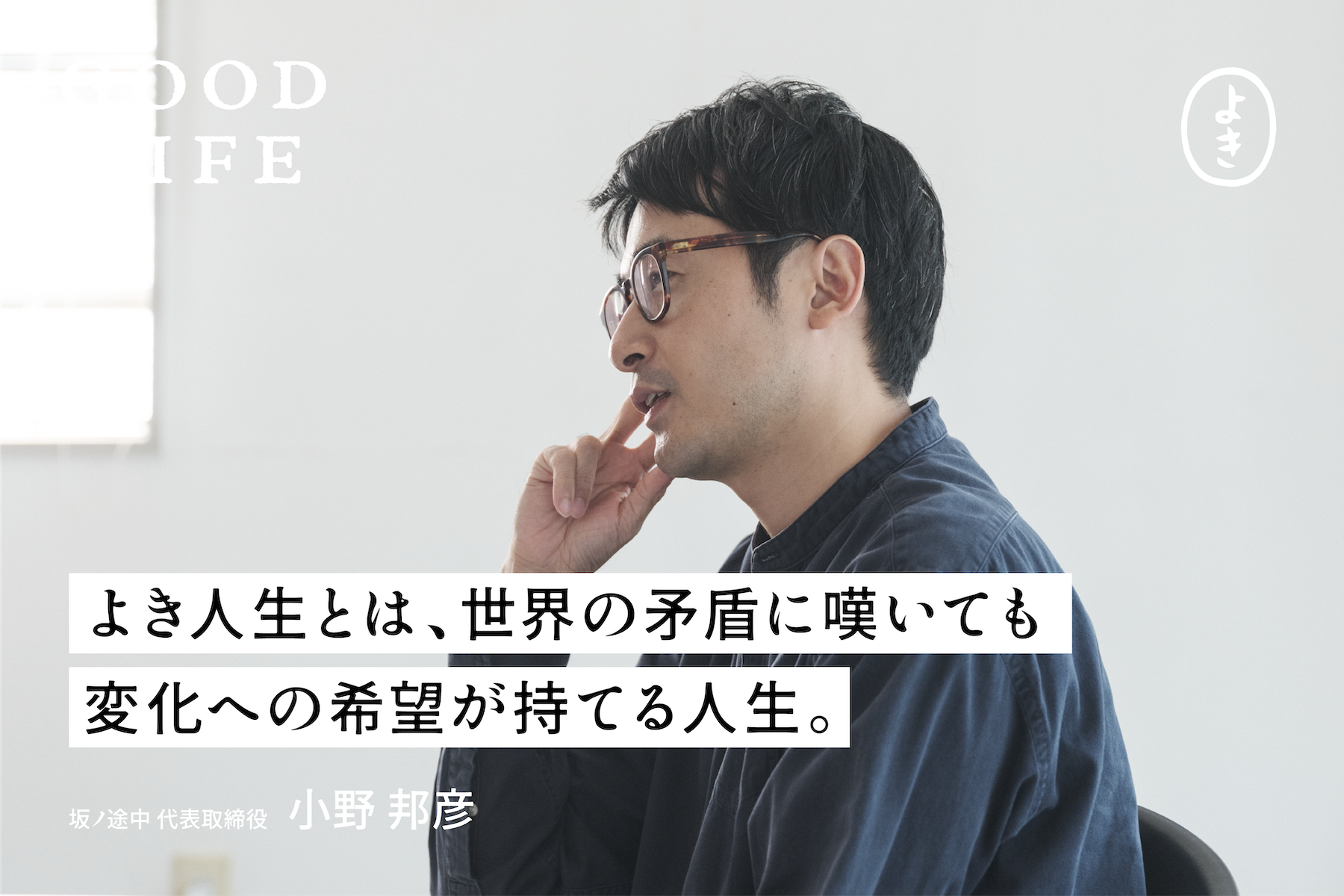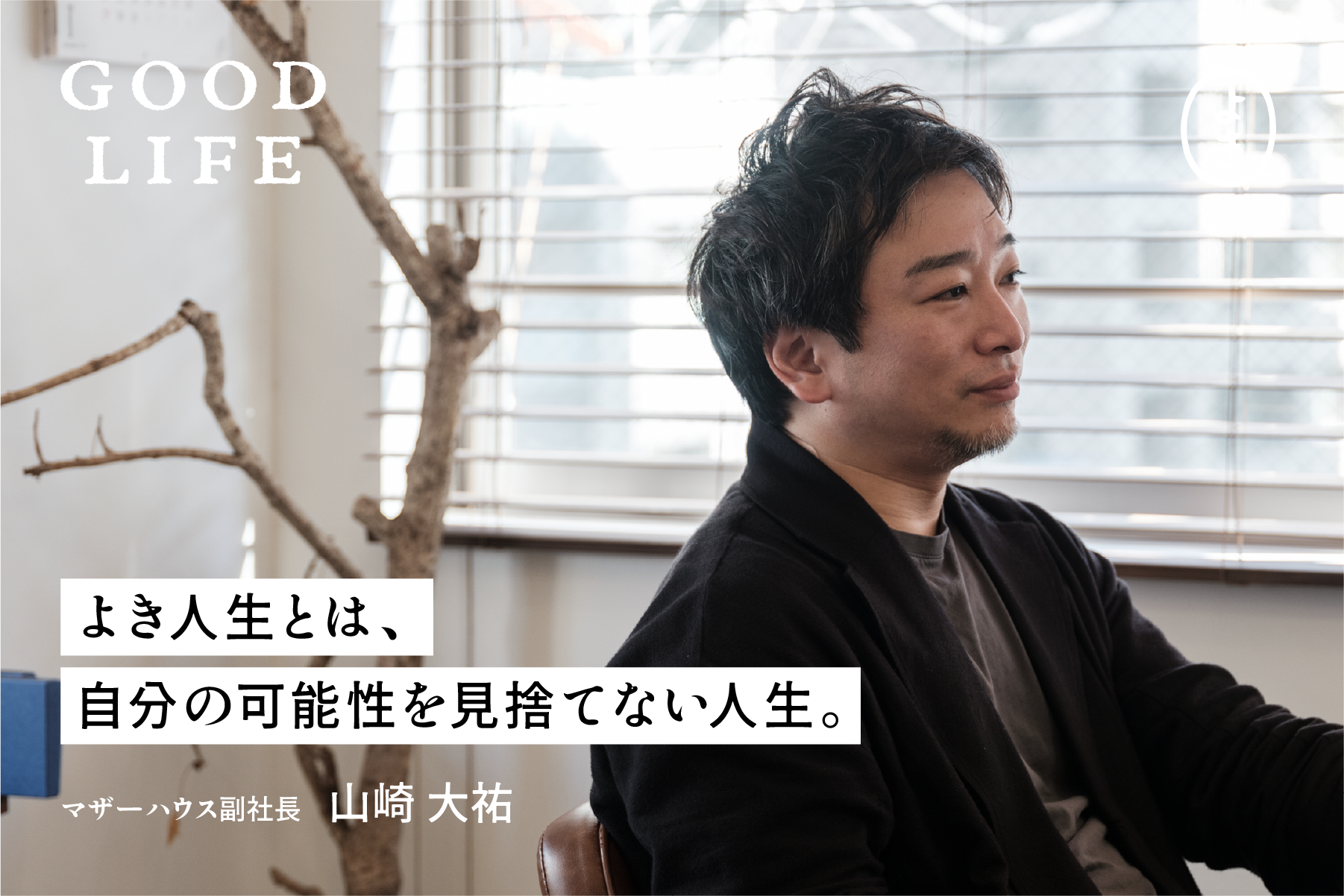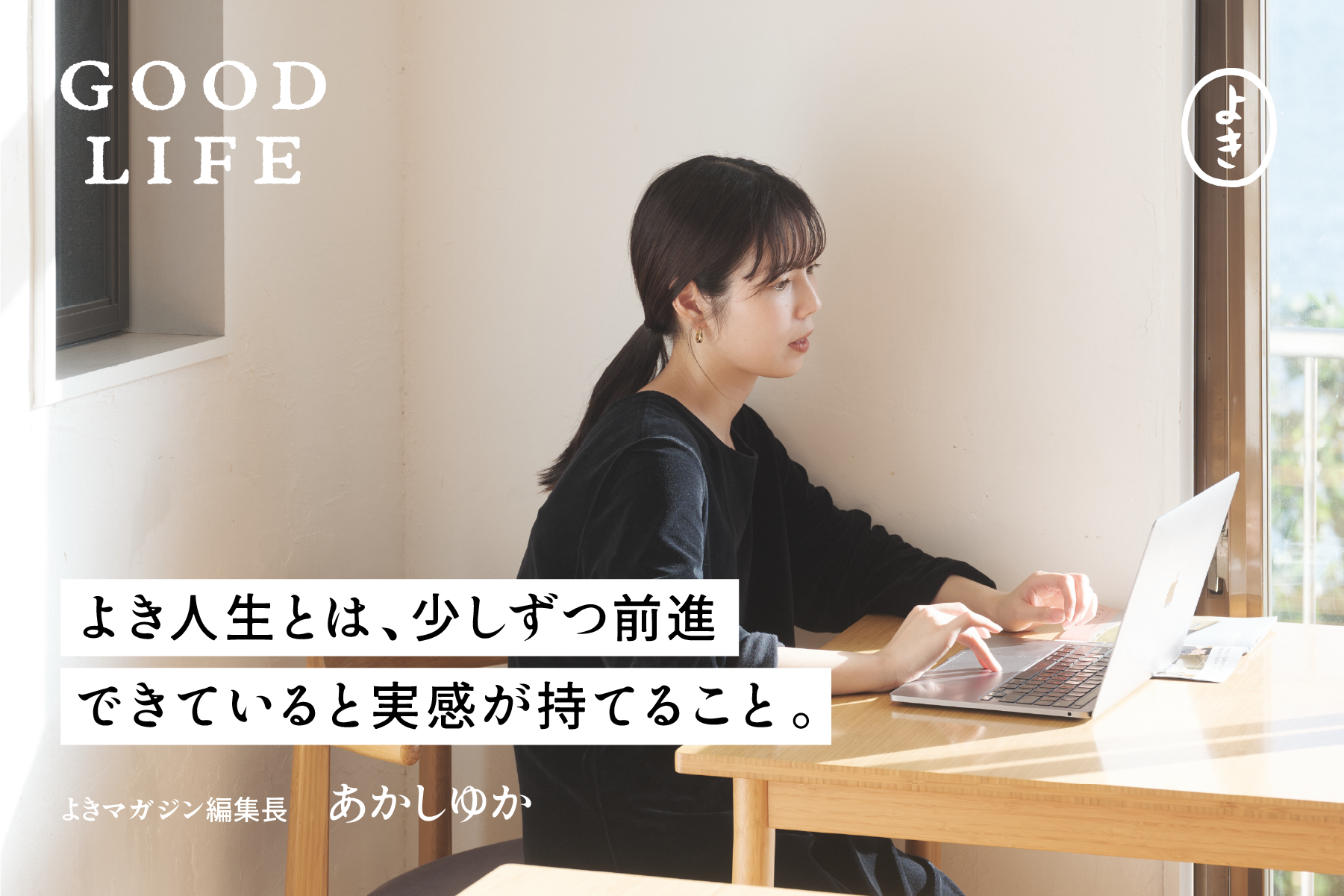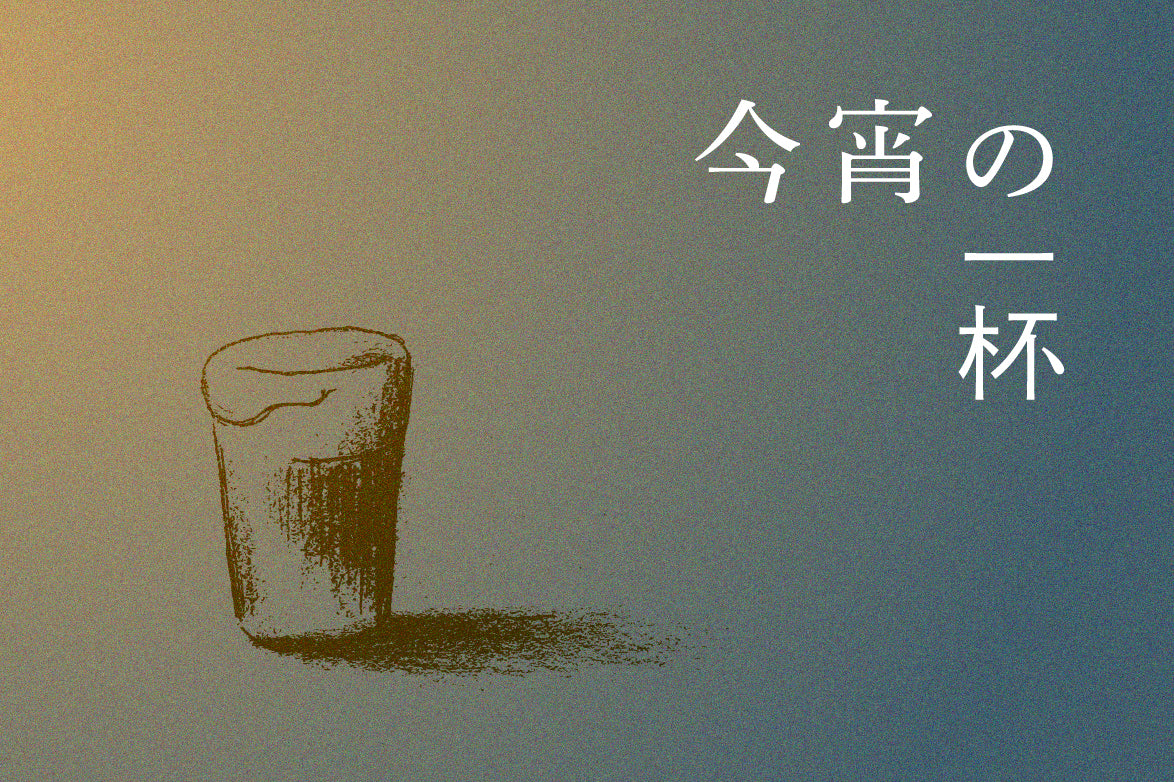目次
活発な性格は、子どもの頃から変わっていない
平田:有賀さんって活発で明るくて、一緒にいると楽しくなる人だなといつも思います。幼い頃からそういう感じだったんですか?
有賀:はい。子どもの頃からずーっとこんな感じです。

平田:素敵ですね。その性格は、家庭環境などから由来してるのでしょうか?
有賀:そうですね。私は東京生まれ東京育ちなのですが、父の兄弟6家族が、同じ土地に住んでいたんですよ。母屋には祖母もいて、大家族で村を作っている感じでした。
なにかと理由をつけて宴会したり、学校から帰ったらいとこが勝手にうちに来ていたり、叔父がいつもどこかで飲んでたり、その風景はまるで東京じゃないみたいでした。お正月などみんなが集まるときは叔母たちが料理を持ち寄るから、母にとってはめちゃめちゃプレッシャーだったと思いますけど(笑)。
平田:それは大変ですね(笑)。
有賀:さらに家が便利な場所にあったので、それぞれの知人友人もよく集まっていました。父も人を連れてくるのが好きだし、私のきょうだいもみんな友だちを連れてくるものだから、玄関を開けるといつも知らない靴が並んでいましたね。
平田:すごい……!

有賀:人がたくさんいるところでわちゃわちゃ育ったからこそ、大勢の中にいてもリラックスできる明るい性格が出来上がったんだと思います。知らない人がいるところで緊張するみたいなことが私には一切ない。よく「商店の子どもは人見知りしない」と言いますが、それと近いのかもしれないですね。
「あるから好きになった」料理と、「ないから好きになった」料理
平田:そういった環境が、有賀さんの食への興味を目覚めさせたのでしょうか?
有賀:影響していると思いますね。子どもの時から料理をしている母の周りをうろちょろして、「やらせろ、やらせろ」って言ってた記憶があります。目玉焼きを作らせてもらうところから始まって、みんなに食べてもらって「おいしいね」と言ってもらうと、それだけでもう楽しくて。
最初は、「みんなでおいしく食べる」状況を自分で作り出せることがおもしろかったんです。でも、私のそもそもの性質として、「何かに凝るととことんまでやりたくなる」というものがあったんでしょうね。カレーをずっと作り続けたり、パスタにはまったり、ひとつのことに凝ったら探究が止まりませんでした。特に夢中になったのはお菓子です。小学校3年生ぐらいの頃にクッキーを作って面白いなと思い、中学に入る頃には趣味が昂じていって、週末は朝から晩までお菓子を作っていたんですよ(笑)。

平田:私もそのタイプなので、感覚はすごくわかります。
有賀:母がさすがに悲鳴を上げて、「食材費が大変だからこの中でやりくりして」とお金を渡されるようになりました。それで本を買って、レシピを見てどんどん作っていったんです。お菓子作りの楽しかったところは、粉と卵と砂糖とバター、同じ材料なのに分量や配合を変えるだけで、クッキー、スポンジ、パウンドケーキ、パイ、全く違うものができるということ。
自分の性質と料理、そして環境がマッチしたんでしょうね。料理することでどんどん幸せが広がっていく感じでした。

平田:私も料理が好きなのですが、今の話を聞いていて、有賀さんとは全然違う方向性から料理を好きになってるんだなと感じました。
うちは逆に、母親がいなくて父親とおばあちゃんと兄と4人暮らしだったんです。すごく小さな家で、人の出入りもあまりありませんでした。祖母は料理は嫌いではなかったんですけど、私が小学生ぐらいの時にすでに老齢で、作るのが億劫な感じになっていたんですよ。
昔の人だから出汁とか味噌とか醤油とかにはこだわるしおいしいんだけど、食卓にはいつも質素な料理が並んでいました。一方で友達の家に行くと、いろんな華やかな料理が出てくる。それをどうしても家で食べたいという欲求から始まって、自分でレシピ本を買って、作って家族に振る舞うということを繰り返して好きになっていったんです。だから、「ある中で好きになった」有賀さんと、「ないから始めて好きになった」私と、対照的で興味深いなと思いました。
有賀:おもしろい。どういう理由で料理を始めるかは、やっぱり人それぞれですね。そしてそこには家庭環境がすごく影響しているんでしょうね。

「つくること」を求めて、就職はおもちゃメーカーに。
平田:でも有賀さんは料理の道には進まず、おもちゃメーカーに就職、結婚してフリーライターへ転身、そこから絵や写真をはじめ、日課だったスープ作りとかけ合わせて「スープ作家」になられたんですよね。すぐに料理の道に進みたいとは思わなかったのですか?
有賀:高校生の時に一度、お菓子職人になりたいと思って調理師学校に行きたいと言ったんですが、通っていた学校が進学校だったのと、時代的にまだ女性が料理人になる風潮がなくて周囲から反対されたんです。そこで食の道はあきらめて大学に進学し、もう少し広く「何かを作る仕事」に方向転換しようと、メーカーを中心に就職活動をして玩具メーカーのバンダイに入社したんです。

平田:なるほど! どのステップも明るく軽やかですね。切り替えが早いというか。
有賀:でも、その私の性質は「よくも悪くも」なんです。ダメと思うとさっと切り替えてしまうから、時間軸の中できちんと何かを積み上げて行くことができていなかった。悩まない分、基礎から何かを学んでいないことへのコンプレックスみたいなものはずっとありました。
私が40歳を前に絵を本格的に始めたのも、「一からちゃんと学んでみたい」という気持ちがあったのだと思います。
「適性」で人とつながることの幸せ
平田:おうちにお邪魔させていただいて驚きましたが、どれも本当にすばらしい絵ですよね。

有賀:ありがとうございます。
平田:有賀さんは、持ち前の明るさと好奇心でさまざまなことを経験されてきたと思いますが、「よき人生」を歩むうえで大事にしている哲学はありますか?
有賀:たくさんの仕事や趣味を経験してきたおかげで自分の「適性」がわかったことは本当によかったですね。自分の「好き」にこだわるよりも、自分の「適性」に気づき、それを大事にして動いていったほうが、どんどん先に進めるし、人にもいろんな価値を与えられて、人とつながって幸せでいられる。それが自分の「よき人生」の一部分であるような気がします。

平田:私も全く同じことをいつも講演会で話しています。少し言葉は違うんですけど、「好きなことじゃなくて、できることを仕事に」とよく言っているんです。私は7年間、ずっと大好きだったDJで食べていきたいと努力していたんですけど挫折して。それで、「できること」にシフトして今わざわざを経営しているのですが、それが自分のよき人生につながっていますから。
有賀さんにとって、ご自身の「適性」は何だと考えられていますか?
有賀:言葉を使って人に伝えることやSNSを使って発信をすることには適性があると思います。「ここでこういう言葉を使うのがいいだろうな」といった感覚がするするとわかるというか。だからある程度多くの方に興味を持っていただけるんだと思います。
SNSで発信を始めたのは、絵を描きはじめた頃です。その時にはじめて、食や絵や文章や何かを作ることなど、自分の趣味で人とつながっていく楽しさを知りました。高校や大学の友達って、大好きだけどそういうものを語り合う友だちではない。ご飯を食べたり飲みに行ったりするけど、じゃあそこで一生懸命絵の話をするかというと、しないんですね。ネットで知り合った人とはそういう話ができて、それが私にとっては当時衝撃的なことでした。どんどん会って、知り合いを増やして、そこから自分の世界も仕事も広がっていった。今私がやっている仕事って、ほぼその時にできた人脈でできているし、そうした人たちと知り合えたのは、いろいろやっていたから見つけられた自分の適性があってこそですね。
平田:スープ作りや絵をはじめたことで、「発信が得意だ」というご自身の適性に気づけたんですね。
有賀:そうですね。あとは、私は一本道でまっすぐ階段を登ってきた人とは全然違う人生だと思いますが、螺旋階段をゆるゆる登ってきたかわりに、いろんな人たちを横軸で繋げたり、人と人の間を行き来して何かをすることは人よりもできて、それも自分の適性なのだと思っています。「作ること」は好きだけれど、「発信すること」や「つなげること」という適性に気づけてから世界がより広がった。
私はもしかすると、料理に関する情報をどう発信して見てくれる人とつなげるかという、「編集者」に近い仕事をずっとやっているのかもしれないですね。

自分の「名前」を大切にする
平田:とはいえ、私や有賀さんが自分の「できること」に気づいたのはずいぶんと大人になってからですよね。まだ自分の適性がわからない人たちに向けてはどう思いますか?
有賀:「自分の適性で人とつながると幸せだ」と先ほど言いましたが、得意なことが見つかっていなくても、やっぱり「人とつながること」はとても大切で、それがよき人生につながると思うんです。じゃあ「人とつながる」ことで一番大事なことってなんだろう?と考えると、とてもシンプルだけど、「私は有賀薫です。あなたは誰ですか?」と人と向き合う姿勢を持つことなのかな、と思いました。
SNSを匿名でする人がいますが、私は個人的には名前をきちんと出してやったほうがいいと思っています。別にそれが芸名でもいいんですよ。でも、ちゃんと自分のアイデンティティみたいなものを乗せた、「私はこういう人間です」ということを世界に提示していかないと、本当の意味で人とは繋がれないんじゃないかなと思っていて。
平田:ああ、わかります。「有賀薫です」と言った瞬間、有賀薫ですと堂々と言える自分がそこにしっかりと立ち現れる。それが人と対峙する時には必要ですよね。自分がなかったら人とは向き合えないから、まず自分を名乗って、自分の存在を表す。「そこにあること 」は、他者とつながるコミュニケーションの第一歩なんだなという感じがします。架空の名前で人とつながっても、それって本当の自分の人生のつながりなのかと言われたらわからない。少し空虚な感じがしますよね。
有賀:そうですよね。これは別に子どもでもできることだと思います。自分に何か能力があるとかないとかじゃなくて、「ここに私はいるので話しましょう」と、「私と関係してください」と世界に提示すること。
私がSNSを最初から実名でやっているのには、そういう意味も含まれているのだと思います。大家族で育ち、いろんな人と出会ってきたからこそ、人とちゃんとつながりたいという思いがずっとある。
自分自身を提示して、よきつながり方をして大切な人を見つけ、自分の周りにいる人たちを大事にする。自分のやりたいことや適性がわからなくても、まずはそこから「よき人生」が始まっていくのではないでしょうか。